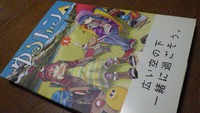2014年09月14日
山歩き 安達太良山 周回コース 20140913
前日のソロキャンプの場所の選定理由は、安達太良山で山歩きをする為だった。
今日は天気も良いので、気持ちよく歩けるだろう。
この時持っていった物
服装
ザック内(グレゴリー Z35)
水分補給は、ハイドレーションシステムを使う事にした。立ち止まってボトルを取り出して飲む、という動きが無駄だからだ。なるべく立ち止まらず歩きたいので、このハイドレーションシステムが役に立ってくれる事だろう。
今回登る安達太良山は、標高1700mながらも日本百名山の中の一座だ。安達太良山の最高峰は安達太良山ではなく、標高1728mの箕輪山だ。
安達太良山は別名を持っていて、乳首山(ちちくびやま)と呼ばれている。名前の通り、遠くから見ると、ぽっちりとした突起に見えるからだ。何とも可愛い。男としては押さえきれないみりょk
現在は大人しくなったそうだが、安達太良山は火山活動が活発な山で、周囲にはいくつもの温泉場がある。山の中腹にある、くろがね小屋にも、源泉かけ流しの温泉が備え付けられているほどだ。
山の傾斜は緩やかで、初心者にも登りやすいという。その為、冬山登山の初心者にも向いているそうだ。
標高1700ながら、森林限界地点からの眺めが素晴らしいそうで、福島市内を一望出来る。景色が本当に楽しみだ。
私が歩くコースは、安達太良山周回コースだ。
周回コースには、ゴンドラを使うコースと、使わないコースがある。ゴンドラを使うと頂上まで2時間、ゴンドラを使わないと3時間半だ。今回、私はゴンドラを使わないコースを選んだ。ゴンドラを使わないコースは、ゴンドラを使わないコースの逆ルートで歩くルートだ。山歩きを始めて半月、もっと難しい山にも登れるように鍛えねばならない。
このゴンドラを使わない周回コースはこうなっている。奥岳登山口から勢至平を経由し、くろがね小屋に向かう。小屋から峰の辻と牛の背を通り、頂上に到達する。
同じ景色を見ながら帰るのは勿体無いので、帰りはゴンドラのルートを帰る事にする。行きに3時間半、帰りに1時間半、計5時間という所だろうか。
朝8時、駐車場脇のゴンドラを横目に通り抜け、スキー場横の登山口から出発する。
まず最初の目的地はくろがね小屋だ。

歩きやすいように砂利で舗装されている。
登山道が荒れていないので、こちらから登る人はかなり少ない様だ。

30分程歩くと、あだたら渓谷自然遊歩道が見えてきた。道が舗装されていたのは、ここを見に来る客の為のようだ。
9月なのに、水が豊富に流れている。釣り針を垂れたら、イワナが釣れそうな渓相だ。
渓流脇に遊歩道が設置されており、この遊歩道を歩いていくと、登山口の脇に抜けられるようになっている。


このコースの登山道にも2種類あって、馬車道という新しい登山道と、旧道の登山道に分かれている。
旧道は荒れているので、登りにくそうだ。

こちらが旧道だ。
長い年月で登山道が荒れているし、湿っていてドロがかなり付きそうだ。

今回はこちらの馬車道という新道を進む事にした。こういう選択が軟弱者たる所以なのだと自分でも思う。
馬車道は、その名の通り、馬車でも走れるような整然とした道だ。

所々、木の隙間から、いい景色が目に飛び込んで来る。標高はまだ低いながらも、福島市が一望出来るようだ。
こうした景色の変化が登っている疲れを癒してくれる。森の中だけを延々と登り続けるのは苦痛だからだ。

このコースの小屋までの中継地点の勢至平だ。
勢至平にはちょっとした展望がきく場所があって、そこから鉄山を見る事が出来る。

歩きながら、ふと振り返ると雪山の様な盛り上がった雲が見えた。
あの形はK2だな、などと適当な事を考える。

さらに進むと水源が見えてきた。金明水神と書いてある。
綺麗で豊富な水が湧き出ているようだ。
手を洗い、手で水を掬い、口に含む。冷たくて美味い。
ハイドレーションシステムでなければ、水を補給したい所だったのに残念だ。


最初の目的地、くろがね小屋に到着した。ここまで1時間40分くらいだ。
小屋の名前の通り、鐘が吊るしてある。
この小屋には、温泉があって、大人は410円で入浴する事が出来る。温泉は10時からになっており、今は9時45分なので開いていないようだ。
行きに温泉に入ってしまったら、きっと何もかもが面倒になってしまう様に思われる。今回は我慢しよう。
この小屋は冬期も営業しており、冬山登山で利用する登山客も多いという。
私の今シーズンの山歩きの最終目標として、雪山を登りたいと考えている。勿論、安達太良山は無理だとしても、冬期の泉ヶ岳くらいには登れるようになりたいのだ。具体的な目標も持っていて、元旦、初日の出を泉ヶ岳頂上で見たいと考えている。装備を揃えるのにはかなりのお金がかかるだろうが、私は何故か雪に惹かれるのだ。本当に無謀な初心者だという事も解っている。でも、山をナメている訳ではない。事前に研究と勉強をしてから挑もうというのだ。そして、こうして頻繁なペースで山を歩いているのは、それに向けた体力作りを多少意識しているからだ。


小屋の場所が標高1400mなので、ここから頂上に向けて、1時間で一気に標高を300mを上げねばならない。当然、登りもキツくなってくる。
道も登山道然として来た。道が細くなり、岩がゴロゴロと転がっている。
赤い目印を辿って上へ登っていく。

息が上がってくるが、止まらずゆっくりでも足を進める。
森林限界地点を抜けた。一気に視界が開ける。景色を楽しみたい所だが、キツくてそれどころではない。
このくらい急だと、直進ではなく、ジグザグに進んでいく方が楽だと解った。

足元を見ながら進んでいると、黒い実がなった植物を見つけた。ブルーベリーのような色の実だ。結構実をつけている木が多い。
写真を撮ろうと軽く触れたら、実がポロリと取れてしまった。これは、山が食べろと言ってくれている気がした。山が私を殺したいと思っていないのであれば、毒はない筈だ。
軽く前歯で噛んでみる。ブルーベリーのようなさわやかな香りがする。舌の上で味わうと、優しい酸味とほのかな甘みを感じた。美味しい。飲み込むと、疲れが取れて、元気が出てきたように感じた。体がもっとよこせと言っている。
後で調べてみた所、クロマメノキという植物だったようだ。やはり食べられるそうだ。
高山植物の実を摘んではならないのは承知している。批判があれば甘んじる。でもこの一粒は、誰が何と言おうと、山が私にくれたものなのだ。

山頂に近づいてきた。
しかし、急に霧が立ち込め始めた。牛の背から見える爆裂火口も霧で殆ど見えない。楽しみにしていたのに残念だ。
それにしても、私は本当に霧男のようだ。

例の乳首が見えてきた。あれが安達太良山の本体だ。
頂上付近になって、にわかに人が増えてきた。ゴンドラ側から登ってきた人が大量に居る。小屋側のルートでは、2、3人にしか会わなかったが、ゴンドラ側からはこんなに登って来ているとは思わなかった。

山頂の目印があるが、ここは山頂ではない。あのポッチが本当の山頂だ。
急峻な岩のクサリ場があり、これを上っていく。当然、渋滞していた。
クサリ場は初めてだが、三点確保で登れば何と言う事はなかった。


頂上に着いた。
何とも狭い頂上だ。でも、今までいくつか山の頂上に立ったが、ここが一番頂上らしさがあるかも知れない。

三角点にタッチする儀式も忘れない。妙に手がむくんでいる。疲れが関係あるのだろうか。何だろう。
このむくみ、何なのかを調べてみた。
体内の水分不足が原因だ。人間は脱水症状手前になると、尿ではなく皮膚に水分を放出するホルモンが出るのだという。その皮膚の水分が、このむくみなのだ。
つまり、歩いている最中の水分補給が足りないのだ。
今回、ハイドレーションシステムで、こまめに水分補給を心がけてはいたのだが、補給が足りなかったのだ。恐らく、吸い口から少量の水を飲むと、水分補給したつもりになっていただけで、出て行く汗と飲む水分が釣り合っていなかったのだ。
私は、冬に向けて寒さに慣れようと、10度付近になる頂上付近でも終始半袖でいたが、それでも汗はじわりと出ていた。ハイドレーションシステムからチューと一口吸って水分補給した気分になるのではなく、ホースからチューチュー吸いまくるべきだったのである。
どこかで、胃も一つの水筒だと考えるべきだというのを読んだ。なるほど、今回その意味が解った。何でも経験だ。

いい景色だ。福島を一望出来る。霧さえなければと思ってしまう。
登ってきた道も小さく小さく見える。


さあ、昼食だ。山稜を眺めながら食べる昼食は美味い。山で食べる飯は、何でも美味い。

昼食を食べたら帰るだけだ。
ゴンドラを使わないで登ってよかった。一人で黙々と登れた事に満足した。さらば安達太良山の突起。
頂上を極めた時は特に感じなかったのに、帰りのゴンドラに乗って、降りていく瞬間が一番達成感を感じた。自分はこんなに高い場所へ自分の足だけで登ったのだという実感を強く感じたからだ。
ゴンドラの中で一人、やったぞ、と声を出してみた。

9月13日学んだ事:
・高山植物の実は美味い
・水分補給は十二分に行うべし
今日は天気も良いので、気持ちよく歩けるだろう。
この時持っていった物
服装
| 服装 | シャツ、パンツ、トレッキングシューズ |
ザック内(グレゴリー Z35)
| 服 | フリース |
| クッカー類 | スノーピーク トレック900、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | 握り飯、カップヌードルミニ、スープ、ティーバッグ、チョコバー、飴、水(プラティパスビッグジップSL 1000ml入)、予備の水(プラティパス2 1000ml入) |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、熊鈴、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、コンパクトデジカメ、トレッキングポール |
水分補給は、ハイドレーションシステムを使う事にした。立ち止まってボトルを取り出して飲む、という動きが無駄だからだ。なるべく立ち止まらず歩きたいので、このハイドレーションシステムが役に立ってくれる事だろう。
今回登る安達太良山は、標高1700mながらも日本百名山の中の一座だ。安達太良山の最高峰は安達太良山ではなく、標高1728mの箕輪山だ。
安達太良山は別名を持っていて、乳首山(ちちくびやま)と呼ばれている。名前の通り、遠くから見ると、ぽっちりとした突起に見えるからだ。何とも可愛い。
現在は大人しくなったそうだが、安達太良山は火山活動が活発な山で、周囲にはいくつもの温泉場がある。山の中腹にある、くろがね小屋にも、源泉かけ流しの温泉が備え付けられているほどだ。
山の傾斜は緩やかで、初心者にも登りやすいという。その為、冬山登山の初心者にも向いているそうだ。
標高1700ながら、森林限界地点からの眺めが素晴らしいそうで、福島市内を一望出来る。景色が本当に楽しみだ。
私が歩くコースは、安達太良山周回コースだ。
周回コースには、ゴンドラを使うコースと、使わないコースがある。ゴンドラを使うと頂上まで2時間、ゴンドラを使わないと3時間半だ。今回、私はゴンドラを使わないコースを選んだ。ゴンドラを使わないコースは、ゴンドラを使わないコースの逆ルートで歩くルートだ。山歩きを始めて半月、もっと難しい山にも登れるように鍛えねばならない。
このゴンドラを使わない周回コースはこうなっている。奥岳登山口から勢至平を経由し、くろがね小屋に向かう。小屋から峰の辻と牛の背を通り、頂上に到達する。
同じ景色を見ながら帰るのは勿体無いので、帰りはゴンドラのルートを帰る事にする。行きに3時間半、帰りに1時間半、計5時間という所だろうか。
朝8時、駐車場脇のゴンドラを横目に通り抜け、スキー場横の登山口から出発する。
まず最初の目的地はくろがね小屋だ。

歩きやすいように砂利で舗装されている。
登山道が荒れていないので、こちらから登る人はかなり少ない様だ。

30分程歩くと、あだたら渓谷自然遊歩道が見えてきた。道が舗装されていたのは、ここを見に来る客の為のようだ。
9月なのに、水が豊富に流れている。釣り針を垂れたら、イワナが釣れそうな渓相だ。
渓流脇に遊歩道が設置されており、この遊歩道を歩いていくと、登山口の脇に抜けられるようになっている。


このコースの登山道にも2種類あって、馬車道という新しい登山道と、旧道の登山道に分かれている。
旧道は荒れているので、登りにくそうだ。

こちらが旧道だ。
長い年月で登山道が荒れているし、湿っていてドロがかなり付きそうだ。

今回はこちらの馬車道という新道を進む事にした。こういう選択が軟弱者たる所以なのだと自分でも思う。
馬車道は、その名の通り、馬車でも走れるような整然とした道だ。

所々、木の隙間から、いい景色が目に飛び込んで来る。標高はまだ低いながらも、福島市が一望出来るようだ。
こうした景色の変化が登っている疲れを癒してくれる。森の中だけを延々と登り続けるのは苦痛だからだ。

このコースの小屋までの中継地点の勢至平だ。
勢至平にはちょっとした展望がきく場所があって、そこから鉄山を見る事が出来る。

歩きながら、ふと振り返ると雪山の様な盛り上がった雲が見えた。
あの形はK2だな、などと適当な事を考える。

さらに進むと水源が見えてきた。金明水神と書いてある。
綺麗で豊富な水が湧き出ているようだ。
手を洗い、手で水を掬い、口に含む。冷たくて美味い。
ハイドレーションシステムでなければ、水を補給したい所だったのに残念だ。


最初の目的地、くろがね小屋に到着した。ここまで1時間40分くらいだ。
小屋の名前の通り、鐘が吊るしてある。
この小屋には、温泉があって、大人は410円で入浴する事が出来る。温泉は10時からになっており、今は9時45分なので開いていないようだ。
行きに温泉に入ってしまったら、きっと何もかもが面倒になってしまう様に思われる。今回は我慢しよう。
この小屋は冬期も営業しており、冬山登山で利用する登山客も多いという。
私の今シーズンの山歩きの最終目標として、雪山を登りたいと考えている。勿論、安達太良山は無理だとしても、冬期の泉ヶ岳くらいには登れるようになりたいのだ。具体的な目標も持っていて、元旦、初日の出を泉ヶ岳頂上で見たいと考えている。装備を揃えるのにはかなりのお金がかかるだろうが、私は何故か雪に惹かれるのだ。本当に無謀な初心者だという事も解っている。でも、山をナメている訳ではない。事前に研究と勉強をしてから挑もうというのだ。そして、こうして頻繁なペースで山を歩いているのは、それに向けた体力作りを多少意識しているからだ。


小屋の場所が標高1400mなので、ここから頂上に向けて、1時間で一気に標高を300mを上げねばならない。当然、登りもキツくなってくる。
道も登山道然として来た。道が細くなり、岩がゴロゴロと転がっている。
赤い目印を辿って上へ登っていく。

息が上がってくるが、止まらずゆっくりでも足を進める。
森林限界地点を抜けた。一気に視界が開ける。景色を楽しみたい所だが、キツくてそれどころではない。
このくらい急だと、直進ではなく、ジグザグに進んでいく方が楽だと解った。

足元を見ながら進んでいると、黒い実がなった植物を見つけた。ブルーベリーのような色の実だ。結構実をつけている木が多い。
写真を撮ろうと軽く触れたら、実がポロリと取れてしまった。これは、山が食べろと言ってくれている気がした。山が私を殺したいと思っていないのであれば、毒はない筈だ。
軽く前歯で噛んでみる。ブルーベリーのようなさわやかな香りがする。舌の上で味わうと、優しい酸味とほのかな甘みを感じた。美味しい。飲み込むと、疲れが取れて、元気が出てきたように感じた。体がもっとよこせと言っている。
後で調べてみた所、クロマメノキという植物だったようだ。やはり食べられるそうだ。
高山植物の実を摘んではならないのは承知している。批判があれば甘んじる。でもこの一粒は、誰が何と言おうと、山が私にくれたものなのだ。

山頂に近づいてきた。
しかし、急に霧が立ち込め始めた。牛の背から見える爆裂火口も霧で殆ど見えない。楽しみにしていたのに残念だ。
それにしても、私は本当に霧男のようだ。

例の乳首が見えてきた。あれが安達太良山の本体だ。
頂上付近になって、にわかに人が増えてきた。ゴンドラ側から登ってきた人が大量に居る。小屋側のルートでは、2、3人にしか会わなかったが、ゴンドラ側からはこんなに登って来ているとは思わなかった。

山頂の目印があるが、ここは山頂ではない。あのポッチが本当の山頂だ。
急峻な岩のクサリ場があり、これを上っていく。当然、渋滞していた。
クサリ場は初めてだが、三点確保で登れば何と言う事はなかった。


頂上に着いた。
何とも狭い頂上だ。でも、今までいくつか山の頂上に立ったが、ここが一番頂上らしさがあるかも知れない。

三角点にタッチする儀式も忘れない。妙に手がむくんでいる。疲れが関係あるのだろうか。何だろう。
このむくみ、何なのかを調べてみた。
体内の水分不足が原因だ。人間は脱水症状手前になると、尿ではなく皮膚に水分を放出するホルモンが出るのだという。その皮膚の水分が、このむくみなのだ。
つまり、歩いている最中の水分補給が足りないのだ。
今回、ハイドレーションシステムで、こまめに水分補給を心がけてはいたのだが、補給が足りなかったのだ。恐らく、吸い口から少量の水を飲むと、水分補給したつもりになっていただけで、出て行く汗と飲む水分が釣り合っていなかったのだ。
私は、冬に向けて寒さに慣れようと、10度付近になる頂上付近でも終始半袖でいたが、それでも汗はじわりと出ていた。ハイドレーションシステムからチューと一口吸って水分補給した気分になるのではなく、ホースからチューチュー吸いまくるべきだったのである。
どこかで、胃も一つの水筒だと考えるべきだというのを読んだ。なるほど、今回その意味が解った。何でも経験だ。

いい景色だ。福島を一望出来る。霧さえなければと思ってしまう。
登ってきた道も小さく小さく見える。


さあ、昼食だ。山稜を眺めながら食べる昼食は美味い。山で食べる飯は、何でも美味い。

昼食を食べたら帰るだけだ。
ゴンドラを使わないで登ってよかった。一人で黙々と登れた事に満足した。さらば安達太良山の突起。
頂上を極めた時は特に感じなかったのに、帰りのゴンドラに乗って、降りていく瞬間が一番達成感を感じた。自分はこんなに高い場所へ自分の足だけで登ったのだという実感を強く感じたからだ。
ゴンドラの中で一人、やったぞ、と声を出してみた。

9月13日学んだ事:
・高山植物の実は美味い
・水分補給は十二分に行うべし
Posted by at 11:47│Comments(4)
│山歩き
この記事へのコメント
おはようございます。
またまた登山ですね!
頂上で食べると何でも美味しいですよね。
キャンプで食べる外飯とはまた一味違う美味しさがあります。
ゴンドラの中で一人、やったぞ、と声を出してみた・・・わかります。
といっても私はゴンドラ活用しちゃいますが(^^);
またまた登山ですね!
頂上で食べると何でも美味しいですよね。
キャンプで食べる外飯とはまた一味違う美味しさがあります。
ゴンドラの中で一人、やったぞ、と声を出してみた・・・わかります。
といっても私はゴンドラ活用しちゃいますが(^^);
Posted by r_island at 2014年09月16日 07:45
at 2014年09月16日 07:45
 at 2014年09月16日 07:45
at 2014年09月16日 07:45r_islandさん。こんにちはー。
汗をかいた所為か、しょっぱいものが美味しく感じました。
だから、みんなラーメン食べているのでしょうか。
にぎりめしとラーメンのセット、最高です!
ちなみに、帰りのゴンドラの高度感が凄くて、キ○○マがヒュッとなりました。
実は高い所は得意でないようです。
汗をかいた所為か、しょっぱいものが美味しく感じました。
だから、みんなラーメン食べているのでしょうか。
にぎりめしとラーメンのセット、最高です!
ちなみに、帰りのゴンドラの高度感が凄くて、キ○○マがヒュッとなりました。
実は高い所は得意でないようです。
Posted by saltpine at 2014年09月16日 14:23
at 2014年09月16日 14:23
 at 2014年09月16日 14:23
at 2014年09月16日 14:23ゴンドラからの眺めに、これだけの山をご自分の足で登られたんだわ…となにやら感動しました。
ブログを読んでるうちに、一緒に登ってるような錯覚になったのかもしれません。
山のくれた木の実の、口に広がる酸味や甘み、疲れた体に染み渡るようなエネルギー、どれも共感しながら読ませて頂きました。
ブログを読んでるうちに、一緒に登ってるような錯覚になったのかもしれません。
山のくれた木の実の、口に広がる酸味や甘み、疲れた体に染み渡るようなエネルギー、どれも共感しながら読ませて頂きました。
Posted by oto at 2014年09月16日 14:26
at 2014年09月16日 14:26
 at 2014年09月16日 14:26
at 2014年09月16日 14:26otoさん。こんにちは~。
一緒に登っているような感覚だなんて、嬉しいコメントありがとうございます。
実は、私のブログは詰め込みすぎてて良くないなぁ、といつも反省しているのです。
もっと端的に伝わるようになれればいいのですが・・・。
それにしても、あのクロマメノキの実は美味かったですよ。
苛酷な自然環境で結実したものだからこそ、パワーがあったのかも知れませんね。
一緒に登っているような感覚だなんて、嬉しいコメントありがとうございます。
実は、私のブログは詰め込みすぎてて良くないなぁ、といつも反省しているのです。
もっと端的に伝わるようになれればいいのですが・・・。
それにしても、あのクロマメノキの実は美味かったですよ。
苛酷な自然環境で結実したものだからこそ、パワーがあったのかも知れませんね。
Posted by saltpine at 2014年09月16日 20:22
at 2014年09月16日 20:22
 at 2014年09月16日 20:22
at 2014年09月16日 20:22※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。