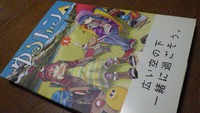2016年03月08日
ソロキャンプ 宮城県某所 20160305
2016年3月5日 宮城県某所
キャンプをしながら焚き火で渓魚を炙って食べたかったので、出かけてみた。
昨年、宮城でも大雨によって堤防が決壊するほどの被害があった。その影響で、沢にもダメージがあったようだった。
この時持っていった物
服装
| 服装(移動時) | アンダーウェア上下、フリース、パンツ、ネオプレンソックス、渓流シューズ |
| 服装(キャンプ時) | アンダーウェア上下、フリース、パンツ、マウンテンパーカ、ニット帽、スニーカ |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル コンフォートシステムパッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #0、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | ダグ 焚火缶、エバニュー ハンドル、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、割り箸 |
| 食料 | 鍋の材料(ジップロック)、予備食料、ビール3本、スキットル入りウイスキー、水1L |
| イス | ドッペルギャンガー フォールディング 超々ジュラルミン |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ、ダウンブーツ、マウンテンパーカ、スニーカー |
| 冬装備 | THERMOS 山専ボトル、ブラックダイヤモンド ディプロイ3 |
| 釣り道具 | 竿、仕掛け(ミャク釣り、チョウチン釣り)、エサ(ミミズ)、毛ばり |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、ファーストエイドキット、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、コンパクトデジカメ、ウェアラブルカメラ、トレッキングポール(スノーバスケット装着)、文庫本 |
冬は荷物が多い。寒さ対策、雪対策で否が応にも増えてしまう。荷物を減らすためにマットをリッジレストではなく、モンベルのエアマットにするという、ささやかな抵抗を試みたのだが、地面からの冷えが思った以上に強くて、夜中に何度も目を覚ましてしまった。
今年の冬は、異常な天候だったので、現地の雪の量が読めなかった。昨年の今頃は、雪だらけでスノーシューが必要だったので、スノーシューもアイゼンも準備して行ったが、今年は所々に雪がへばりついているだけだった。出発前に不要な冬装備を削ったつもりだったが、最終目的地の雪も少なく、スノースコップも結果的に不要になった。今年は装備の選定も難しい。
そして、渓流釣り時の足回りと、キャンプ時の足回りは同じものを使用出来ない。移動時は水に入れるもの、キャンプ時はそれを脱いで履けるもの、と分けなければならない。これがなければ荷物を減らせるのだろうが、釣りをやろうというのだから、こればかりはどうしようもない。
最後に、ドッペルギャンガーのイスは、持って行って失敗した。持っているローチェアは雪の場合だと、尻が雪で濡れてしまうので、座高が高めのこちらのイスを持ち込んだが、現地は雪も殆どなく、座っては苦痛だった。快適さをとるか、苦痛でも軽さをとるか、難しい所ではあるが、限界はあるという事を再認識した。
今回は、解禁日が過ぎたばかりの渓流に入り、釣りをしながら夕食の食料を調達するという、プチサバイバル的なソロキャンプを計画してみた。勿論、釣れなかった時の為と、温まる為の鍋の材料は持ち込むが、メインは渓流の魚たちだ。釣果を食料計画に組み込むという事は、貧相な夕食になるリスクもあるが、たった一回の食事への影響なので、仮にそうなったとしても大した事ではない。渓魚の調達も、釣った実績のある沢に入るので、釣れないという心配も無いだろう。
釣りの仕掛けはエサ釣りで、エサはミミズだ。過酷な環境に住んでいるイワナは何でも食う。エサが豊富な環境にいる魚はエサを選り好みするが、今回の行き先は水溜りのような砂防ダム下の淵なので、ミミズを食わないという事はないだろう。仕掛けは基本的にはチョウチン釣りで、竿の半分くらいの長さの道糸(竿に直接結ぶ糸)に錘と針を付けただけの、シンプルなものだ。今回はやや長めにチョウチン釣りの仕掛けを作ってしまったので手返しが悪かったが、これは途中で調整すべきだったかも知れない。
さて、現地へ向かう。仙台から1時間くらいの場所だ。雪があるかどうかは、付近のライブカメラでチェックはしていたが、3月上旬にあって、ここまで雪がないとは思わなかった。雪に踏み跡はない。今シーズン、解禁してから人が入っていないのだ。これは期待出来る。
雪に足を乗せてみると、殆ど沈まないので、スノーシューは不要そうだ。車に残置しよう。
最初はイワナの釣れる沢に入る。昨年、弟とタラノメを採りつつイワナを釣った場所だ。ここは結構釣れた実績のある沢なので、期待出来る。本日のキャンプ地は隣の沢だが、隣はやや渋い印象があるので、夕食はここでの釣果次第という事になりそうだ。
所々、雪が解けた場所からフキノトウが顔を覗かせている。持ち帰って天ぷらにして食べよう。この時期の山菜は、フキノトウ程度しか採れないので、これをキャンプの食料にする事は出来ない。もう少し経てば、コゴミ、タラノメなどの採って楽しい、食べて美味しい・・・という山菜も芽吹いてくる。山菜はタイミングが合うかどうかが大きな問題だが、今年も採れる事を楽しみにしている。

沢が荒れている。昨年の大雨のダメージのようだ。土砂が流れ出て地形が変わってしまった場所もある。これは魚にも影響があるかも知れない。
釣れるだろうと目論んでいたポイントにエサを投入するも、魚の反応がない。いくつかの場所を試してみるも、同じく反応が出ない。何かがおかしい。
渓流釣りは足で釣る釣りだ。釣れなければ移動するだけだ。良さそうなポイントで竿を出しつつも奥へと向かう。
昨年、元気なイワナが飛び出した砂防ダムの下に到着した。やはりここも少し様子が変わっている。少し淵が浅くなった様に感じるのだ。上流から堆積物となるものが流れて来たのだろう。
その淵(水溜り)へ早速仕掛けを投入する。グンと竿に反応があった。手応えは小さいものの、イワナの黄色い腹が見えた。周囲の木に注意しながら竿を手早く短く調整し、道糸を手繰り寄せる。やった。まずは一匹目だ。20cmちょっとの小さなイワナだが、焚き火でコイツの塩焼きが炙られている様を想像するとニヤけてくる。

この調子でいこう。
再び上流へ向かって進む。砂防ダムを乗り越える時の、斜面にへばりついた残雪をトラバースするのに神経を使う。ここで残雪が滑り落ちたり、足を踏み外すと、結構な怪我になる。渓流シューズのフェルト生地のソールが心もとないが、残雪に蹴りこんで確実にスタンスを切って降りきることが出来た。
さあ、ここが本日の本命ポイントだ。ここに至るまで、途中で何度か竿を出したものの反応は得られなかったが、ここでは間違いなく魚が釣れる予感がする。
水面に自分の姿が映りこまない距離感で竿の穂先をポイントへと向ける。エサが入るやいなや、流れ動く目印がピタッと止まった。アタリだ。イワナのアタリはあまりシビアではない。向こうアワセでいいくらいだ。一息おいてアワセる。グングングネグネという手応えがあった。結構デカい。コイツを引っこ抜くにはハリス(道糸から針を繋ぐ糸で道糸より細い)が細くて切れてしまいそうだ。一瞬の逡巡ののち方策なく引っこ抜くと、空中でイワナが暴れ、ハリスが切れてしまった。逃した魚はデカいというが、夕食のメインになりそうなサイズを逃しただけに、だいぶガックリときた。
もう一度仕掛けを投入する。再びアタリが出る。今度は手応えが小さい。今度は大丈夫だろうと引っこ抜く。げぇーーーっ!!またしてもバラす。ハリスは切れていない。針が外れたのだ。今回、いつも使っている針から別な形のものに変えている。これの影響だろうか。
運が味方していない日のような気がしてきた。

隣の沢に移動しよう。
キャンプ装備一式のザックをグイと背負うと、重くて息が漏れる。ウェストベルトを締めると加重が分散され、重さを感じにくくなった。最近は冬用のアルパインザックばかり背負っていたので、この久々の安定感に驚く。それでも荷物に水物が多く20kgはオーバーしているので、なかなかの負荷だ。ゆっくり歩くも、じわりと汗が出てきた。
林道が崩れている場所から、一旦ルートを外れ沢へ下る。重いザックを背負っていく必要はないので、釣り道具だけを持って、ザックはデポして進んだ。

こちらの沢は渓相が穏やかで歩きやすい。最初のポイントの砂防ダムの下へ向かう。砂防ダムの最上部から水が落ちてくるが、雪解けシーズンなので、水量が凄い。
こちらではヤマメが釣れる。ヤマメは、イワナに比べると神経質な魚だ。やや慎重にアプローチして、エサを流す。
何度か繰り返すも反応が出ない。時間帯が良くないというものあるが、解禁直後の最初の釣り人の仕掛けに反応もしないのが不思議だ。私がヘタクソなのは認めるが、もうちょっと姿を見せてくれてもいい筈だ。大雨の所為にばかりにも出来ないが、その影響で魚影が薄くなってしまったのではないかと考えながら竿を振る。
駄目だこりゃ。ねばっても意味がない。
こういう時は、山菜と戯れるに限る。魚は逃げる。山菜は逃げない。先ほどまでの沢は、ここより100m近く標高が高いので、雪も豊富でフキノトウも閉じていたが、こちらのフキノトウはフキノトウらしい可愛い姿をしている。さっき採取した方は天ぷらに、こちらはバッケ味噌(フキノトウ味噌)がいいだろう。

キャンプ予定地の砂防ダムに到着する。砂防ダムがいい風除けになるので、気に入っている場所なのだ。
その砂防ダムの上から周囲を見ると、様子が大きく変わった事が解った。上流側は土砂が堆積した様な地形になっていたが、それが強い流れで押し流された後が見える。砂防ダムの最上部には、こんな高さまで届く筈がない流木が乗っかっている。下流側も地形に変化が見られる。どうやら想像以上に、昨年の大雨が強かったようだ。沢にも魚にも強いダメージがあったのだ。そう思う事で、釣れない自分を慰める事にしよう。
残雪を利用してテントを張る。雪の上は踏む事で平らに出来るので、寝心地が良いのだ。天気も良い事から、テントのペグダウンも適当でいいだろう。

ネオプレンソックスと渓流シューズ。ネオプレンソックスの脛部分が摩擦で削れてしまっている。ここから水が入ってくるようだった。そろそろ寿命だ。渓流シューズも、8年くらい前のものだ。こちらはもう少し使えそうだ。

本日の食料。
焚き火鍋の材料と焚火缶。予備の食料として、餅2個とたまごスープ。こういう徒歩でのキャンプは段取り9割だ。現地で材料を切ったりするのはナンセンス。美味い食事が出来るかどうかの勝負は、出発前に決しているのだ。

早々に装備も整理したら、私にはやる事が残っている。
ヤマメよ、本日最後の勝負だ。昨年、ここで私は尺には至らないだろうものの、28cmくらいのヤマメを釣っている。
どうアプローチしたのかを書くのが面倒臭いので結果を書いてしまうと、釣れなかったという事だ。クソが。

渓魚に囲まれた夕食とは程遠い、イワナ一匹と焚き火鍋の貧相な夕食が確定した。焚き火をしながら自分を慰めるしかない。幸いにも薪となる流木は一晩で燃やし尽くせないほど転がっている。
焚き火をする位置を決め、流木を整理していて気が付いた。ガムテープを巻いてあるライターを持ってくるのを忘れた。ガムテープは火口として優秀で、少し流木が湿っていても、手順さえ間違えなければ火を熾す事が出来るので、毎回助けられている。
周囲を見渡すと、草の根っこが転がっている。良い具合に乾いているものもある。これだ。これを火口にするのだ。
やっつけで準備して火を点ける。乾いた根っこが一気に燃え上がり、準備が不十分で流木に火が移る前に消えてしまった。
丁寧さが足りない。自然と真摯に向き合わねばならない。火口となる草の根っこは草本体から毟って丸くし、草本体は最初に火を移す細枝として使用する。それに加えてスカスカで燃えやすそうなイタドリの枯れ枝を割って使う。これらに火が回った所で、細い流木をくべ、太い流木をくべ・・・よし、これでいこう。

作戦通り焚き付けは成功した。雪解けの影響で流木が湿りがちの状態だったので、少しほっとする。
転がっている枯れ枝を拾い、釣り上げた小さなイワナを刺す。準備してきた塩を塗りたくり、焚き火にかける。焚火缶に沢の水を汲み、火にかける。ウーン、この様になる画はどうだ。焚き火、イワナ、黒光りする焚火缶、このコントラスト。ハードな男の世界だ。私は原始人だ。

小さくて身の少ないイワナを食べ、焚き火鍋を食べる。イワナは骨酒が美味いので、熱燗に食べ終わった骨をぶち込みたいが、こういうキャンプではそれも叶わない。
焚き火鍋は鍋キューブでの味付けから、プチッと鍋という小さな液体スープタイプの調味料に変えてみた。これは正解だった。鍋キューブは、インスタントラーメンを思わせる味だが、こちらは中々美味い。液体だと少し重くなるので敬遠していたが、ビールを3本も担いで持って来ている事を考えると、こんなものは誤差だ。次もプチッと鍋を使ってみよう。

冷えてきた。持参のダウンジャケットとダウンパンツをインナー、マウンテンパーカをアウターとして着込むが、それでも結構冷える。空気の湿度が高い所為か、随分とひんやりするようだ。
テントの中に引っ込んで、ウイスキーのお湯割を飲みながら、本でも読もう。お湯はテルモスに詰めて持ってきたので、使い勝手が良い。
やや熱々のウイスキーのお湯割を飲みつつ、羽根田治の遭難ドキュメントの本を読む。ネット上で遭難ものの手記を最近読んでいて、ゾクリをしたのを思い出す。自分にも降りかかりかねない事だと思うと、里山だろうとこうして入っていくのが怖くもなる。山歩きでも、キャンプでも、そうならないように自己防衛の為の装備は準備はしているが、こうした危機意識と緊張感は常に持っておいた方がいいものだろう。
夜半から朝方にかけて、霧雨が降った。ポツポツという雨音を聞きながら、夜を過ごした。

翌朝。
テント設営時のペグダウンが甘かった所為で、テントの中は結露だらけになった。テント内部の側面は濡れ、スタッフサックやザックの中に仕舞っていなかった装備は湿っている。テント内は不快な状態なので、とっとと帰ってしまいたい。
私は宿泊翌日にダラダラするのが好きではない。翌日に行動をあまりしないのであれば、朝食も摂らなくても平気だったりする。一人で行動し、一人で判断する。気分次第でどうとでも動けるのが良い。
霧雨で濡れてしまったテントをたたむ。スニーカーから渓流シューズに履き替えるのも面倒なので、このまま帰る事にする。よし、準備は整った。

帰る前にする事がある。最後の大勝負だ。
結論を書くと、ヤマメはかかったけどバラしたんだよ!クソ!釣り人失格!

タグ :ソロキャンプ
2015年12月19日
ソロキャンプ 宮城県白石市某キャンプ場 20151218
更新が面倒でブログをだいぶ放置していた。いつの間にかナチュログにソロキャンプのカテゴリが出来ていたりして、こんなニッチな遊びが市民権を得たのかと思うと、何とも居心地が悪い。
キャンプに行っていなかった訳ではないのだけど、動画を編集したり、記事を書いたりするのが、とにかく面倒だったのだ。
特に動画の編集は面倒臭い。しかも、Youtubeの方は心無いコメントもあるので、いよいよ動画編集のやる気が削がれるのだ。
愚痴はこれくらいにしておいて、始めよう。
この時持っていった物
服装
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
ザック外の道具(使用したもののみ記載)
装備は最低限のものだけ使った。オシャレさなど微塵もないが、これでいい。
今回のキャンプ場は、2年程前に良く利用していたキャンプ場だ。
ここはネット上で、温泉が止まってしまって営業しなくなったというのを目にして以来、キャンプ場も一緒にやめたのだろうと勝手に思い、遠ざかってしまっていた。そもそも、キャンプ場でキャンプするというのが嫌になってしまった、という私の偏屈的な性格もある。
12月初旬、今シーズンの雪山の訓練も兼ねて、蔵王の刈田岳を登りに行った帰りにこのキャンプ場に立ち寄ってみた。車を駐車スペースに停めると、管理人のおかあさん(オバアチャン)が出てきて、日帰り温泉はやめてしまったのよ、と言う。よくよく聞くと、旦那さんの具合が悪くなってしまって以来、日帰り温泉をやめてしまった、というのが理由のようだった。しかし、今でもバーベキューやキャンプ場のみやっているという事で、キャンプ場自体は利用出来ない訳ではない事が解った。
あのドギツい温泉に入れなくなったのは残念だが、素晴らしいロケーションのキャンプ場が利用出来るのであれば、久々にここでテントを張ってみたくなった。
今年の冬はどうもおかしい。気温が高いままだし、雪も全く降らない。スキー場は営業出来ずに困り、スキー場のリフトを利用して山に登りに行く私の様な登山客も困っている。雪が降らずにどう遊べと言うのか。
私は、冬こそキャンプのシーズンだと考えているので、雪が降るであろうタイミングを待って、キャンプに出掛ける事にしようと考えていた。
ようやく、そして久しぶりに、雪の予報が出た。タイミング良く休みだったので、これは久々にキャンプせねばならないだろう。あのキャンプ場へ行こう。
クルマを1時間走らせ、キャンプ場へ向かう。
平地の気温が8℃なので、標高差で現地は5℃くらいだろうか。雪を期待しているのに、空が青空なのが気になるが、晴れていれば星が良く見えるのだから、これはこれで良いだろう。
現地に近づくと、路肩にうっすらと白い雪がかぶっている箇所も現れ始めた。雪中キャンプは無理でも、夜に向かって気温が下がれば雪が降ってくれる筈だ。

キャンプ場に到着すると、温泉犬が出迎えてくれる。管理人のおかあさんも外に居たので、キャンプで1泊したい旨を伝える。何も無いけどいいの、他に誰もいないけどいいの、と心配そうに聞かれる。何も無いのがいいのだし、誰も居ないのがいいのだ。誰かが居るようであれば台無しだ。
薪を一束欲しい事を伝え、車でキャンプ場に入って行く。オートキャンプだ。これは楽出来て良い。
ああ、それにしてもこのキャンプ場からの眺めは、何と素晴らしいのだろう。

雪が少しだけ積もっている。これが30cmも積もれば立派に雪中キャンプが出来る。しかしそれは、あと半月は待たねばならないような気がする。

焚き火台に火を熾す。
今日の私のキャンプサイトは、テント、焚き火台、イスのみだ。超シンプルな構成だ。
タープも面倒なのでいらない。テーブルもいらない。これで十二分にキャンプになる。だいいち、タープなんかあったら、座ったままで空を見上げられないだろう。
どう見ても、オシャレさなど微塵もない。人が見たら、みすぼらしく見えるかも知れない。でも、自然を相手に遊ぶのに、見た目なんかどうでもいいと思う。私はこれで十分なのだ。こっちの方が自然に近くてワクワクするし、無ければ無いで工夫するものだ。

寝床の準備をしよう。
マットは、リッジレストにするかモンベルのコンフォートシステムパッドにするか悩んだが、リッジレストを使わないとどれだけ冷えるか試してみたくて、エアマットの方を選んだ。その結果、寝具回りは全てモンベル製品となってしまった。

景色を眺めながらビールを楽しんだ後は、焼肉だ。スーパーで適当に選んだ肉だ。この安い肉は、食べた翌日に屁が強烈に臭くなる困ったヤツだ。シュラフの中でしようものなら、臭いで目が覚めてしまう。
生ラムも買ったものの、ラム肉で焼肉になるのかと、買ってからふと考えた。味は、可も無く不可もなく。
肉だけをしこたま食べて満足してしまったのか、準備してきた鍋の材料は使わずのままとなった。

ビールばかりで冷えてきたので、日本酒に燗をつけて飲む事にする。明るい内から日本酒を飲む事に、妙な罪悪感を感じるのは何故だろうか。
黒じょかに日本酒を注ぎ入れ、焚き火に直にかける。指を突っ込んで温度を確認しつつ、頃合を見て火から外す。直火の為、外側の陶器の余熱が強いので、引き上げるタイミングが難しい。
うん。旨い。体が温まる。
ビールに日本酒に、醸造酒ばかりなので、少し飽きた。ウイスキーも持って来れば良かった。

目の前の稜線が次第に茜色になっていく。ゆっくりと自然の色の変化を眺める。雲の上部は紅く、下部は紫。空の夕方と夜の境界線が赤から橙色に、そして黄色、黄緑色を経ながら、群青や紫へと変化し、自然が次第に夜を迎える準備をしていく。
ボーッと、その経過を眺める。何も考えない。考える必要もない。自然と一体になる。

暗くなった。18時過ぎにして、もう眠い。眠いのに起きている理由もない。
ええい、もう寝ちまおう。

夜半、目が覚める。
パラパラとテントのフライを雪が叩く音がする。積もったその雪がスルスルと下に流れる音もする。風も強く、時々ゴウゴウと声をあげながら、風がテントを強く押す。朝になったら銀世界になっていて欲しい。

翌朝、テント内が明るくなって目が覚めた。
期待を持ってテントから出ようとすると、フライがバリバリに凍っている。フライのジッパーを開けるも、そこに銀世界は無かった。うっすらと雪は見えるが、積もったとも言いがたい量だ。
残念だけど、また来ればいい。次は雪中キャンプだ。

キャンプに行っていなかった訳ではないのだけど、動画を編集したり、記事を書いたりするのが、とにかく面倒だったのだ。
特に動画の編集は面倒臭い。しかも、Youtubeの方は心無いコメントもあるので、いよいよ動画編集のやる気が削がれるのだ。
愚痴はこれくらいにしておいて、始めよう。
2015年12月18日 宮城県白石市某キャンプ場
この時持っていった物
服装
| 服装 | アンダーウェア上下、フリース、パンツ、マウンテンパーカ、ニット帽、グローブ、防寒ブーツ |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #0、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | ダグ 焚火缶、エバニュー ハンドル、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | 焼肉用の肉、鍋の材料(ジップロック)、ビール3本、日本酒、水 |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、双眼鏡 ビクセン アルティマZ 7x50 |
ザック外の道具(使用したもののみ記載)
| 焚き火 | スノーピーク 焚き火台S、耐火グローブ、火バサミ、炭、薪、イス、黒じょか |
装備は最低限のものだけ使った。オシャレさなど微塵もないが、これでいい。
今回のキャンプ場は、2年程前に良く利用していたキャンプ場だ。
ここはネット上で、温泉が止まってしまって営業しなくなったというのを目にして以来、キャンプ場も一緒にやめたのだろうと勝手に思い、遠ざかってしまっていた。そもそも、キャンプ場でキャンプするというのが嫌になってしまった、という私の偏屈的な性格もある。
12月初旬、今シーズンの雪山の訓練も兼ねて、蔵王の刈田岳を登りに行った帰りにこのキャンプ場に立ち寄ってみた。車を駐車スペースに停めると、管理人のおかあさん(オバアチャン)が出てきて、日帰り温泉はやめてしまったのよ、と言う。よくよく聞くと、旦那さんの具合が悪くなってしまって以来、日帰り温泉をやめてしまった、というのが理由のようだった。しかし、今でもバーベキューやキャンプ場のみやっているという事で、キャンプ場自体は利用出来ない訳ではない事が解った。
あのドギツい温泉に入れなくなったのは残念だが、素晴らしいロケーションのキャンプ場が利用出来るのであれば、久々にここでテントを張ってみたくなった。
今年の冬はどうもおかしい。気温が高いままだし、雪も全く降らない。スキー場は営業出来ずに困り、スキー場のリフトを利用して山に登りに行く私の様な登山客も困っている。雪が降らずにどう遊べと言うのか。
私は、冬こそキャンプのシーズンだと考えているので、雪が降るであろうタイミングを待って、キャンプに出掛ける事にしようと考えていた。
ようやく、そして久しぶりに、雪の予報が出た。タイミング良く休みだったので、これは久々にキャンプせねばならないだろう。あのキャンプ場へ行こう。
クルマを1時間走らせ、キャンプ場へ向かう。
平地の気温が8℃なので、標高差で現地は5℃くらいだろうか。雪を期待しているのに、空が青空なのが気になるが、晴れていれば星が良く見えるのだから、これはこれで良いだろう。
現地に近づくと、路肩にうっすらと白い雪がかぶっている箇所も現れ始めた。雪中キャンプは無理でも、夜に向かって気温が下がれば雪が降ってくれる筈だ。

キャンプ場に到着すると、温泉犬が出迎えてくれる。管理人のおかあさんも外に居たので、キャンプで1泊したい旨を伝える。何も無いけどいいの、他に誰もいないけどいいの、と心配そうに聞かれる。何も無いのがいいのだし、誰も居ないのがいいのだ。誰かが居るようであれば台無しだ。
薪を一束欲しい事を伝え、車でキャンプ場に入って行く。オートキャンプだ。これは楽出来て良い。
ああ、それにしてもこのキャンプ場からの眺めは、何と素晴らしいのだろう。

雪が少しだけ積もっている。これが30cmも積もれば立派に雪中キャンプが出来る。しかしそれは、あと半月は待たねばならないような気がする。

焚き火台に火を熾す。
今日の私のキャンプサイトは、テント、焚き火台、イスのみだ。超シンプルな構成だ。
タープも面倒なのでいらない。テーブルもいらない。これで十二分にキャンプになる。だいいち、タープなんかあったら、座ったままで空を見上げられないだろう。
どう見ても、オシャレさなど微塵もない。人が見たら、みすぼらしく見えるかも知れない。でも、自然を相手に遊ぶのに、見た目なんかどうでもいいと思う。私はこれで十分なのだ。こっちの方が自然に近くてワクワクするし、無ければ無いで工夫するものだ。

寝床の準備をしよう。
マットは、リッジレストにするかモンベルのコンフォートシステムパッドにするか悩んだが、リッジレストを使わないとどれだけ冷えるか試してみたくて、エアマットの方を選んだ。その結果、寝具回りは全てモンベル製品となってしまった。

景色を眺めながらビールを楽しんだ後は、焼肉だ。スーパーで適当に選んだ肉だ。この安い肉は、食べた翌日に屁が強烈に臭くなる困ったヤツだ。シュラフの中でしようものなら、臭いで目が覚めてしまう。
生ラムも買ったものの、ラム肉で焼肉になるのかと、買ってからふと考えた。味は、可も無く不可もなく。
肉だけをしこたま食べて満足してしまったのか、準備してきた鍋の材料は使わずのままとなった。

ビールばかりで冷えてきたので、日本酒に燗をつけて飲む事にする。明るい内から日本酒を飲む事に、妙な罪悪感を感じるのは何故だろうか。
黒じょかに日本酒を注ぎ入れ、焚き火に直にかける。指を突っ込んで温度を確認しつつ、頃合を見て火から外す。直火の為、外側の陶器の余熱が強いので、引き上げるタイミングが難しい。
うん。旨い。体が温まる。
ビールに日本酒に、醸造酒ばかりなので、少し飽きた。ウイスキーも持って来れば良かった。

目の前の稜線が次第に茜色になっていく。ゆっくりと自然の色の変化を眺める。雲の上部は紅く、下部は紫。空の夕方と夜の境界線が赤から橙色に、そして黄色、黄緑色を経ながら、群青や紫へと変化し、自然が次第に夜を迎える準備をしていく。
ボーッと、その経過を眺める。何も考えない。考える必要もない。自然と一体になる。

暗くなった。18時過ぎにして、もう眠い。眠いのに起きている理由もない。
ええい、もう寝ちまおう。

夜半、目が覚める。
パラパラとテントのフライを雪が叩く音がする。積もったその雪がスルスルと下に流れる音もする。風も強く、時々ゴウゴウと声をあげながら、風がテントを強く押す。朝になったら銀世界になっていて欲しい。

翌朝、テント内が明るくなって目が覚めた。
期待を持ってテントから出ようとすると、フライがバリバリに凍っている。フライのジッパーを開けるも、そこに銀世界は無かった。うっすらと雪は見えるが、積もったとも言いがたい量だ。
残念だけど、また来ればいい。次は雪中キャンプだ。

2015年02月09日
雪中ソロキャンプ 宮城県川崎町某所 20150207
山ばかり登っていて、しばらくソロキャンプから遠ざかっていた。solocampとブログ名で掲げておきながら、これでは看板に偽りありの状態だ。
少し億劫になっていたのは確かだ。人の居るキャンプ場には行きたくないし、ザックを担いでキャンプするにしても積雪のある現地にどうアプローチするかが課題だし、これをやるにはキッチリ準備してから向かう必要があるからだ。
最近、仕事が忙しくなってきた所為か、ソロキャンプをして一人になりたい欲求が強くなっていた。これは行くっきゃない!
この時持っていった物
服装
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
冬装備に切り替えた。ザックに装備を詰め込んで、これだけで冬にキャンプするのは初めてだ。
問題は現地へのアプローチと、焚き火をどうするかだった。アプローチはスノーシューでいいとして、焚き火は1週間考えても良い方法が思い浮かばなかった。薪として当てにしている流木は完全に雪の下だろうし、それを掘り出せたとしても完全に凍っている筈なので、駄目そうなのだ。
駄目なものを駄目でなくするにはどうするか。流木を掘り出し、それを薪として使うにはどうするかを考える事にした。雪の下からの掘り出しのスノースコップにブラックダイヤモンドのディプロイ3を、安定した火にしてから凍った流木を投入出来るよう、薪を持っていく事にした。
脳内でシミュレーションして大丈夫そうだという確信はあるが、これはもう半分賭けだ。
今日は本当に良い天気だ。青空だし風もなく、気温も高い。
現地に近づくにつれて雪が目に入るようになってきたが、どうもだいぶ融けてしまっている。ふかふかの雪は期待してはいなかったが、久しぶりの雪中キャンプでグズグズの雪というのは、ちょっと残念だ。
目的地に向かう廃林道に入る前、車を何処に止めるかを少し心配していたが、林道入り口に雪が解けてちょうど良いスペースがあった。そこに車を停め、準備を始めた。
ザックを背負う。うめき声が出そうな位に重い。夏装備でさえそこそこ重いのに、冬装備だと輪を掛けて重い。特にこの薪だ。重いし大きいが、今回のキャンプのキーアイテムなのだから仕方がない。

歩き始める。案の定、人の踏み跡が全く無い。こんな廃林道に入っていくのは、頭のおかしい私くらいのものだろう。動物の踏み後を追いつつ進んでいった。
しばらく進むと積雪量が増えてきたので、スノーシューに切り替えた。しかし、雪がグズグズに腐っているので、スノーシューに纏わり付いて非常に重ったるい。しかも今日は、登山靴ではなく重いSORELの防寒靴を履いているので、足元の重さは結構キツいものがあった。

イノシシの足跡?カモシカの足跡?

いつもの障害を越えながら目的地に到着した。冬は障害物が雪に埋まって歩きやすくなっている箇所があった一方、何でもない所が雪の溜まる場所になっていて苦労する事もあった。
今回の幕営地候補は、前回キャンプした場所、もしくはその直ぐ下流の砂防ダムの下だ。本命は、砂防ダムの下だ。理由は、砂防ダムの落ち込み近くの雪の下に流木が眠っている可能性が高いからだ。
前回のキャンプ場所も偵察してみたが、風の通り道になっているようで、雪が軽くクラストしていた。風を考えればここではテントを張れない。

本命の砂防ダムの下は良さそうだった。水の音は少し気になるが、砂防ダムが風よけになっているし、その脇にはテントを張れそうに雪が平らに積もったスペースがあった。どこでもテントを張る事が出来る様になるのが、冬のいい所だ。
ただ、砂防ダムの落ち込みの周辺は思ったよりも雪に覆われていて、流木を掘り出すのは難儀しそうだった。
ちなみに、この砂防ダムの下ではイワナが釣れる。今が禁猟期でなければ、イワナを釣って直火で焼いて食べたいのだが、それはまた別の機会に取っておこう。

いつもの手順でテントを張る。
雪を踏み均してスペースを作り、グランドシートで位置を決めて、テントを張る。雪は硬くて踏み鳴らさずとも大丈夫そうな程だった。



それにしてもこのロケーション。最高だ。テントから竿を出して釣りをしたいくらいだ。これを独り占め出来るなんて!

天然の冷蔵庫。またこれが出来るシーズンになった。

ここからが今日のキャンプの核心だ。
まずは、薪にする流木を掘り出す。スノースコップで雪を掘り続け、薪になりそうな流木を拾っていく。地味で結構キツい作業だ。しかも思った以上に流木が出て来ない。雪の中から流木が顔を見せてくれても、想像以上にガッチガチに凍りつき、素手で持つと指先が痛くなるほどなのだ。
頑張りに頑張って、これだけの流木を確保した。何とも、不安になるほどの凍りつき方だ。

竈も準備した。
どこもかしこも雪なので、雪の上に竈を準備せざるを得なかった。

さあ、焚き火だ。
いつもであれば、細い枝から太い枝までを拾い集めてそれを焚き付けに使用するが、冬は全てが雪の下だ。持ってきた薪に直接火を点けるしかないのだ。
薪ををやぐらの様に組み、その中心にガムテープを丸めたものを置き、それに火を点ける。ここでのポイントは、薪をケチってやぐらを低くしてはならない事だ。火は上に昇って行く性質があるので、やぐらを高く組む事で火が上に昇りながら一気に火が点いてくれるのだ。個人的に、これを「やぐら式焚き火点火法」と名付けている。
さて、ここからが本番だ。
安定した火に凍った薪をくべていく。最初は様子を見ながら火に投入したが、徐々に大胆に火にくべていった。なるべく火が上に上っていくように調整を行なう。濡れた薪というのは、ゆっくり燃えるので持ちが良いという事は知っている。それが凍っているだけだと思えばいいのだ。
持参した薪で焚き火を安定させ、凍った流木を使っていく。成功だ。持参の薪が無ければ、焚き火は成功しなかった。作戦の勝利だ。

食事の準備だ。
砂防ダム下で水を汲み、焚火缶を火に掛ける。焚火缶は良い具合に黒く育ってきて、焚き火の中で存在感を放っている。焚火缶は本当にいいアイテムだ。

食材はいつもの鍋だ。味付けは鍋キューブ2個。キムチ味は飽きたので、濃厚白湯という味だ。
食材を投入し、焚火缶を火に掛けながら、火が弱まらないように焚き火の世話をする。こんなに楽しい瞬間はそうそうない。
キャンプの手段が原始的になればなるほど、何故かワクワクしてくる。


どうも私はキャンプの時に食べ物に執着しないようだ。作る料理はいつも鍋だし、作ってもそれで満足出来てしまう。元々、量を食べる方でもないけれど、それがキャンプに来ると顕著になる。
キャンプをしていて、それ自体に満足してしまっているからだろうか。

食事をしたら焚き火をしてのんびりするだけだ。
気温も低くなってきた。冷えたビールを飲み続けるのは結構厳しい。
何故か尻が冷える。気付いたら臀部が濡れている。メイフライチェアのお尻の部分が地面に接触していて、その部分の雪が融けて尻を濡らしてしまっていたようだ。ローチェアは座りやすいが、地面に近い分、冬には向いていないようだ。
冬の夜の感覚を思い出してきた。寒い中で一人、焚き火をしながら時間の無駄遣いをする。指先が冷えてきたら、焚き火であぶる。

テントに入って、本を読んだり、ホットウイスキーを飲んだ。テルモスに入った湯は便利だ。改めて湯を沸かさずとも、テントの中でホットウイスキーを作れる。


装備の中でも、夜に役に立ったのがテントシューズだ。マウンテンイクイップメントのパウダーブーツだったと思う。去年の雪中キャンプでは湯たんぽで暖かい寝床を確保していたので出番が無かったが、湯たんぽを持ち込めないこういう環境では、これが暖かい足元を約束してくれた。
このアイテムの便利な所は、これを履いたまま外に出る事が出来る事だ。おしっこがしたくて少し外に出る程度であれば、このまま外に出ても大丈夫なように作られている。
テントシューズは、象足と言ったり、ダウンブーティとも言ったりする。何だブーティって。ブーツでいいだろ。格好つけんな。

気持ちよく寝ていて、テント内が薄ら明るくなり、ふと目を覚ました。時計を見ると、6時過ぎを指している。まだ夜明け前だからこの明るさなのだろう。
外に出てみる。
ん・・・?暗い。時計を見てみる。げぇーっ!!まだ1時半じゃねぇか!!
どうやら時計の短針と長針を見間違えていたらしく、1時半を6時過ぎと思っってしまったようだ。上を見てみると、月が煌々と光っている。この月明かりを夜明け前の薄ぼんやりした光と勘違いしたようなのだ。
一度脳が朝と認識したものだから、テントに入ってもなかなか寝付けない。何度も寝返りを繰り返したり、耳栓で外音を遮断したり、眠気がやって来るのを待ち続けた。


朝。
テントの入り口を開けると砂防ダムの水の落ち込みが見える。昨晩のヘンテコな事件はあったが、胸のすく朝だ。
現実の事は考えたくないが、今日は午後の便で北海道に向かわねばならない。朝食も食べずに帰る準備を開始する事にした。

自然の中で直火の焚き火をする事については、色々ご意見がある。最初の自然の中のキャンプでは、私も焚き火の始末が悪かった事もあった。
今では、可能な限り始末するようにしている。元の通りとはいかないまでも、灰は埋め、竈の石も元に戻す。今回は雪中なので、灰を雪の中に埋めても意味が無い。スコップで灰をゴミ袋の中に入れ、持ち帰った。
(写真で小枝が散乱しているように見えるのは、雪の下の堆積物)


久々のソロキャンプは実に楽しかった。またここに来たい。

少し億劫になっていたのは確かだ。人の居るキャンプ場には行きたくないし、ザックを担いでキャンプするにしても積雪のある現地にどうアプローチするかが課題だし、これをやるにはキッチリ準備してから向かう必要があるからだ。
最近、仕事が忙しくなってきた所為か、ソロキャンプをして一人になりたい欲求が強くなっていた。これは行くっきゃない!
この時持っていった物
服装
| 服装 | アンダーウェア上下、フリース、パンツ、マウンテンパーカ、ニット帽、グローブ、防寒ブーツ |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | サーマレスト リッジレスト ソーライト |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #0、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | ダグ 焚火缶、エバニュー ハンドル、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、割り箸、薪 |
| 食料 | 鍋の材料(ジップロック)、6Pチーズ、ビール3本、スキットル入りウイスキー、水1L |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ |
| 冬装備 | MSR ライトニングアッセント25、THERMOS 山専ボトル、ブラックダイヤモンド ディプロイ3 |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、ファーストエイドキット、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、コンパクトデジカメ、ウェアラブルカメラ、トレッキングポール(スノーバスケット装着)、文庫本 |
冬装備に切り替えた。ザックに装備を詰め込んで、これだけで冬にキャンプするのは初めてだ。
問題は現地へのアプローチと、焚き火をどうするかだった。アプローチはスノーシューでいいとして、焚き火は1週間考えても良い方法が思い浮かばなかった。薪として当てにしている流木は完全に雪の下だろうし、それを掘り出せたとしても完全に凍っている筈なので、駄目そうなのだ。
駄目なものを駄目でなくするにはどうするか。流木を掘り出し、それを薪として使うにはどうするかを考える事にした。雪の下からの掘り出しのスノースコップにブラックダイヤモンドのディプロイ3を、安定した火にしてから凍った流木を投入出来るよう、薪を持っていく事にした。
脳内でシミュレーションして大丈夫そうだという確信はあるが、これはもう半分賭けだ。
今日は本当に良い天気だ。青空だし風もなく、気温も高い。
現地に近づくにつれて雪が目に入るようになってきたが、どうもだいぶ融けてしまっている。ふかふかの雪は期待してはいなかったが、久しぶりの雪中キャンプでグズグズの雪というのは、ちょっと残念だ。
目的地に向かう廃林道に入る前、車を何処に止めるかを少し心配していたが、林道入り口に雪が解けてちょうど良いスペースがあった。そこに車を停め、準備を始めた。
ザックを背負う。うめき声が出そうな位に重い。夏装備でさえそこそこ重いのに、冬装備だと輪を掛けて重い。特にこの薪だ。重いし大きいが、今回のキャンプのキーアイテムなのだから仕方がない。

歩き始める。案の定、人の踏み跡が全く無い。こんな廃林道に入っていくのは、頭のおかしい私くらいのものだろう。動物の踏み後を追いつつ進んでいった。
しばらく進むと積雪量が増えてきたので、スノーシューに切り替えた。しかし、雪がグズグズに腐っているので、スノーシューに纏わり付いて非常に重ったるい。しかも今日は、登山靴ではなく重いSORELの防寒靴を履いているので、足元の重さは結構キツいものがあった。

イノシシの足跡?カモシカの足跡?

いつもの障害を越えながら目的地に到着した。冬は障害物が雪に埋まって歩きやすくなっている箇所があった一方、何でもない所が雪の溜まる場所になっていて苦労する事もあった。
今回の幕営地候補は、前回キャンプした場所、もしくはその直ぐ下流の砂防ダムの下だ。本命は、砂防ダムの下だ。理由は、砂防ダムの落ち込み近くの雪の下に流木が眠っている可能性が高いからだ。
前回のキャンプ場所も偵察してみたが、風の通り道になっているようで、雪が軽くクラストしていた。風を考えればここではテントを張れない。

本命の砂防ダムの下は良さそうだった。水の音は少し気になるが、砂防ダムが風よけになっているし、その脇にはテントを張れそうに雪が平らに積もったスペースがあった。どこでもテントを張る事が出来る様になるのが、冬のいい所だ。
ただ、砂防ダムの落ち込みの周辺は思ったよりも雪に覆われていて、流木を掘り出すのは難儀しそうだった。
ちなみに、この砂防ダムの下ではイワナが釣れる。今が禁猟期でなければ、イワナを釣って直火で焼いて食べたいのだが、それはまた別の機会に取っておこう。

いつもの手順でテントを張る。
雪を踏み均してスペースを作り、グランドシートで位置を決めて、テントを張る。雪は硬くて踏み鳴らさずとも大丈夫そうな程だった。



それにしてもこのロケーション。最高だ。テントから竿を出して釣りをしたいくらいだ。これを独り占め出来るなんて!

天然の冷蔵庫。またこれが出来るシーズンになった。

ここからが今日のキャンプの核心だ。
まずは、薪にする流木を掘り出す。スノースコップで雪を掘り続け、薪になりそうな流木を拾っていく。地味で結構キツい作業だ。しかも思った以上に流木が出て来ない。雪の中から流木が顔を見せてくれても、想像以上にガッチガチに凍りつき、素手で持つと指先が痛くなるほどなのだ。
頑張りに頑張って、これだけの流木を確保した。何とも、不安になるほどの凍りつき方だ。

竈も準備した。
どこもかしこも雪なので、雪の上に竈を準備せざるを得なかった。

さあ、焚き火だ。
いつもであれば、細い枝から太い枝までを拾い集めてそれを焚き付けに使用するが、冬は全てが雪の下だ。持ってきた薪に直接火を点けるしかないのだ。
薪ををやぐらの様に組み、その中心にガムテープを丸めたものを置き、それに火を点ける。ここでのポイントは、薪をケチってやぐらを低くしてはならない事だ。火は上に昇って行く性質があるので、やぐらを高く組む事で火が上に昇りながら一気に火が点いてくれるのだ。個人的に、これを「やぐら式焚き火点火法」と名付けている。
さて、ここからが本番だ。
安定した火に凍った薪をくべていく。最初は様子を見ながら火に投入したが、徐々に大胆に火にくべていった。なるべく火が上に上っていくように調整を行なう。濡れた薪というのは、ゆっくり燃えるので持ちが良いという事は知っている。それが凍っているだけだと思えばいいのだ。
持参した薪で焚き火を安定させ、凍った流木を使っていく。成功だ。持参の薪が無ければ、焚き火は成功しなかった。作戦の勝利だ。

食事の準備だ。
砂防ダム下で水を汲み、焚火缶を火に掛ける。焚火缶は良い具合に黒く育ってきて、焚き火の中で存在感を放っている。焚火缶は本当にいいアイテムだ。

食材はいつもの鍋だ。味付けは鍋キューブ2個。キムチ味は飽きたので、濃厚白湯という味だ。
食材を投入し、焚火缶を火に掛けながら、火が弱まらないように焚き火の世話をする。こんなに楽しい瞬間はそうそうない。
キャンプの手段が原始的になればなるほど、何故かワクワクしてくる。


どうも私はキャンプの時に食べ物に執着しないようだ。作る料理はいつも鍋だし、作ってもそれで満足出来てしまう。元々、量を食べる方でもないけれど、それがキャンプに来ると顕著になる。
キャンプをしていて、それ自体に満足してしまっているからだろうか。

食事をしたら焚き火をしてのんびりするだけだ。
気温も低くなってきた。冷えたビールを飲み続けるのは結構厳しい。
何故か尻が冷える。気付いたら臀部が濡れている。メイフライチェアのお尻の部分が地面に接触していて、その部分の雪が融けて尻を濡らしてしまっていたようだ。ローチェアは座りやすいが、地面に近い分、冬には向いていないようだ。
冬の夜の感覚を思い出してきた。寒い中で一人、焚き火をしながら時間の無駄遣いをする。指先が冷えてきたら、焚き火であぶる。

テントに入って、本を読んだり、ホットウイスキーを飲んだ。テルモスに入った湯は便利だ。改めて湯を沸かさずとも、テントの中でホットウイスキーを作れる。


装備の中でも、夜に役に立ったのがテントシューズだ。マウンテンイクイップメントのパウダーブーツだったと思う。去年の雪中キャンプでは湯たんぽで暖かい寝床を確保していたので出番が無かったが、湯たんぽを持ち込めないこういう環境では、これが暖かい足元を約束してくれた。
このアイテムの便利な所は、これを履いたまま外に出る事が出来る事だ。おしっこがしたくて少し外に出る程度であれば、このまま外に出ても大丈夫なように作られている。
テントシューズは、象足と言ったり、ダウンブーティとも言ったりする。何だブーティって。ブーツでいいだろ。格好つけんな。

気持ちよく寝ていて、テント内が薄ら明るくなり、ふと目を覚ました。時計を見ると、6時過ぎを指している。まだ夜明け前だからこの明るさなのだろう。
外に出てみる。
ん・・・?暗い。時計を見てみる。げぇーっ!!まだ1時半じゃねぇか!!
どうやら時計の短針と長針を見間違えていたらしく、1時半を6時過ぎと思っってしまったようだ。上を見てみると、月が煌々と光っている。この月明かりを夜明け前の薄ぼんやりした光と勘違いしたようなのだ。
一度脳が朝と認識したものだから、テントに入ってもなかなか寝付けない。何度も寝返りを繰り返したり、耳栓で外音を遮断したり、眠気がやって来るのを待ち続けた。


朝。
テントの入り口を開けると砂防ダムの水の落ち込みが見える。昨晩のヘンテコな事件はあったが、胸のすく朝だ。
現実の事は考えたくないが、今日は午後の便で北海道に向かわねばならない。朝食も食べずに帰る準備を開始する事にした。

自然の中で直火の焚き火をする事については、色々ご意見がある。最初の自然の中のキャンプでは、私も焚き火の始末が悪かった事もあった。
今では、可能な限り始末するようにしている。元の通りとはいかないまでも、灰は埋め、竈の石も元に戻す。今回は雪中なので、灰を雪の中に埋めても意味が無い。スコップで灰をゴミ袋の中に入れ、持ち帰った。
(写真で小枝が散乱しているように見えるのは、雪の下の堆積物)


久々のソロキャンプは実に楽しかった。またここに来たい。

2014年11月07日
ワイルドソロキャンプ 宮城県川崎町某所 20141106
2014年11月6日 宮城県川崎町某所
山歩きにばかり夢中になっていて、しばらくキャンプをしていなかった。ソロキャンプに飽きた訳ではないが、夏から秋にかけてのシーズンはキャンプ場に行けば人が居るし、野営しても雑草が凄いので、少し避けていたのかも知れない。
後1ヶ月もすれば、雪が降り始める。雪が積もってしまうと、渓流沿いで流木を集めて焚き火する事も難しくなるだろう。雪中キャンプは楽しみではあるが、流木焚き火もやりたい。
冬に入る前に、あそこでもう一度キャンプしよう。
(↑Youtubeの設定(歯車マーク)でHDを選択すれば、HDで見る事ができます)
この時持っていった物
服装
| 服装 | アンダーウェア上下、フリース、パンツ、トレッキングシューズ |
| 服装(持参) | マウンテンパーカ |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | ダグ 焚火缶、エバニュー ハンドル、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | 鍋の材料(ジップロック)、焼肉の肉(ジップロック)、ビール3本、スキットル入りウイスキー、水2L |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、熊鈴、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、コンパクトデジカメ、ウェアラブルカメラ、トレッキングポール、文庫本 |
装備の更新はなし。道具が揃ったら、食料と酒代だけで遊べるのがとても良い。
今回の野営先には、3回訪れている。この時とこの時とこの時だ。最後の時は一番奥まで行ったが、今回は最初にキャンプした場所にしよう。あそこは実に快適だった。あの時の楽しさが、今の私のソロキャンプスタイルを形成したと言ってもいい。
それにしても、純粋にソロキャンプだけを楽しむのは本当に久しぶりだ。実に3ヶ月ぶり位になるのではないだろうか。
私のソロキャンプの嗜好は、どこかで変に捻じ曲がってしまったらしく、人の居るキャンプ場でキャンプしたくない、などと言う、人嫌いにも似た方向へと向かってしまっている。その為か、キャンプのハイシーズンたる夏と秋は、キャンプから足が遠のいてしまっていたのだ。私は社交的なソロキャンパーにはなれそうも無い。
川崎町某所へと車を走らせ、林道を進めるだけ進み、車を停める。春や夏は渓流釣りをする人が入る為か、車が進める辺りであれば、折れた木の枝で道が塞がっていたりする事はなかったが、渓流は禁猟時期に入っているので、何度か車から降りて木の枝を退けたりしなければならなかった。
いつもの装備一式のザックは、ビール等の水物で重くなっている。船形山から泉ヶ岳をテント泊縦走した時の方が重かったので、これで15kg強といった所だろうか。これくらいであれば、もう屁でもない。

今回もビデオカメラで撮影する。
JVCから発売されているADIXXIONというウェアラブルカメラだ。GoProほど画質は良くないが、値段も安いし、そのままでも防水性、耐衝撃性、耐寒性が備わっており、結構タフに機能してくれるようなのだ。
これを、SONYのバックパックマウントというマウントツールにつけて使用した。手がフリーで歩きながら撮影出来るというのがいい。
しかし、このバックパックマウントの仕様には腹が立っている。
これだけを購入しても、マウント台とスタビライザーパッド(ザックに取り付ける方の事)を合体させる事が出来ず、装着バックルというのが別途必要になるのだ。その為、装着バックルを手に入れるべく、買いたくも無い別のマウントツールも購入する事になってしまった。
更に、このスタビライザーパッドの幅が広い為、ショルダーハーネスからはみ出し、背負うとそのはみ出し部分が痛くなるのだ。作った後、本当にテストしたのか。
SONYの業績が非常に悪化しているという。こうした小さな信用低下の積み重ねでそうなったのだと何故気づかないのか。
とりあえず、ここでこうして文句が言えたので、溜飲を下げる事が出来た。

廃林道を進む。ここは里山なので、まだ紅葉が少し楽しめる。
ああ、一人の旅は何と気楽なのだろう。山歩きと違って、コースタイムを気にして急ぐ必要も全くない。

林道の崩壊箇所や、倒木を乗り越える。
以前来た時は、結構険しい印象を持っていたが、山を歩いて色々経験した所為か、こうした障害には全く動じない。

目的地に到着した。
げぇーっ!!めっちゃ草生えてる!!
テント張るつもりだったスペースも、焚き火スペースも草だらけだ。これは草毟りしないとならない。
焚き火も、この状態でやってしまうと、枯れ草に飛び火してしまって危ない。
しかも、前回キャンプした時に、きっちり片付けて行かなかったらしく、焚き火跡が汚らしく残っていた。これはマズかった。

草毟りをし、テントを張るスペースを確保する。
良し。これで快適に過ごせる。

テントの中の準備を先にやってしまおう。焚き火を始めたらビールを飲んでしまうだろうから、やるなら今なのだ。

ザック一つでキャンプする上で一番ネックなのが、ビールと水だ。たらふくビールを飲んで飲み潰れたい私にビールは必須だとして、水は沢の状態が良く無かった時の為に必ず持ち込む必要があるのだ。
それでも、使う道具自体が限られているので、準備も片付けも楽なのが、このザック一つキャンプ(バックパックキャンプ)の良い所だ。食料、テント、マット、シュラフ、コッヘル・・・焚き火で調理するのであれば、これらがあればキャンプとして十分成立する。少し快適に過ごしたければ、イスやミニテーブルを持ち込んでも良い。

次は焚き火だ。
焚き火スペースの草を毟る。思わぬ所で体力を使っている。暑い。
スペースが確保出来たら、薪となる流木を探す。生い茂った枯れ草で視界が利かない。前回残った分がいくらかあるし、少し集めるだけで大丈夫そうだ。

さぁ、火を熾そう。この瞬間が一番ワクワクする。
細い枝、中くらいの枝、太い枝を準備し、ガムテープを着火剤として火を熾すのだ。これで、本当にこんなに簡単でいいの、というくらい簡単に火が熾きてしまう。

手順通りやって、1回で火が熾きた。

焚き火前にイスを準備する。
ウーン。下が砂利だと、このイスは安定しない。しかし石に座るよりは100倍良い。

何と言う素晴らしい時間なのだろう。
自然の中で、誰も居ない環境で、ビールを片手に、拾い集めた流木で焚き火をする。
自然よ、ありがとう。

ここに来る度、挨拶しているタラノメちゃん。可愛い。(芽が出たら)食べてしまいたい。天ぷらなどで。

のんびりし過ぎて薄暗くなってしまった。
夕食の準備をしよう。
今回は、焼肉と鍋だ。
焼肉は、焚き火の中に洗ったその辺の石を入れ、熱された石の上で焼くという、非常に原始的な方法で調理する。これは、こちらのブログで拝見したのを真似させて貰おうとしたものだ。
鍋はいつもの鍋キューブだ。鍋キューブはソロキャンパーの味方だ。

最初に焼肉をしようと思ったのだが、焚き火の中に入れた石が激しく破裂して驚いた。破裂しない石を見極めないと駄目なようだ。
まずは鍋からにしよう。
沢で焚火缶へ水を汲み、焚き火にかける。焚火缶も良い具合に育ってきた。もっと汚らしくなって欲しい。

鍋が出来上がった。
美味い!・・・けれど、キムチ味が続いたので、少し飽きたかな。次は別なのにしよう。

もう一度、焼肉にチャレンジする。
爆発しないだろうと思われる石を選ぶ。先ほどは、太古の粘土が固まったような石だったので、今回は花崗岩のような石を選んでみた。
良し。爆発しない。
熱された石の上に肉を置くと、ジュウという良い音がした。肉を引っ繰り返す際に、焚き火の中に手を突っ込まねばならず、非常に熱い。
しかし、食べると非常に美味い!網が無くとも野営地で焼肉が出来るのだ。これは良い方法だ。

腹が膨れた。後は焚き火をいじりながら酒を飲んで、酔うのを待つばかりだ。
このゆったりとした時間が心地良い。

雨が降ってきた。自然相手の遊びだから仕方が無い。焚き火をもっとしたかったが、テントの中に入ろう。
ソロキャンプをやってきて、雨の為にテントの中で過ごす事になったのは、今回が初めてかも知れない。テントの中で過ごすというのは、前回の山歩き縦走テント泊が初めてだったのだから、そうなのだろう。
なるほど、そう考えると今回のソロキャンプは、私のソロキャンプの1年間の集大成だ。ザック一つで目的地に向かい、テントを張る場所を確保し、流木を集めて焚き火をしてその火で調理、天候が悪くなればテントの中で過ごす・・・これまでの経験したものを生かしたキャンプだ。
私がソロキャンプを始めたのは、昨年の11月だった。こうした事が出来る様になったのも、知識と経験の賜物だ。

こんな事もあろうかと、本を持ってきている。
井上靖の「氷壁」だ。山の小説としては名作だそうだ。何とAmazonで1円だった。送料はかかるが、それでも安い。これは、どういうビジネスモデルになっているのだろうか。
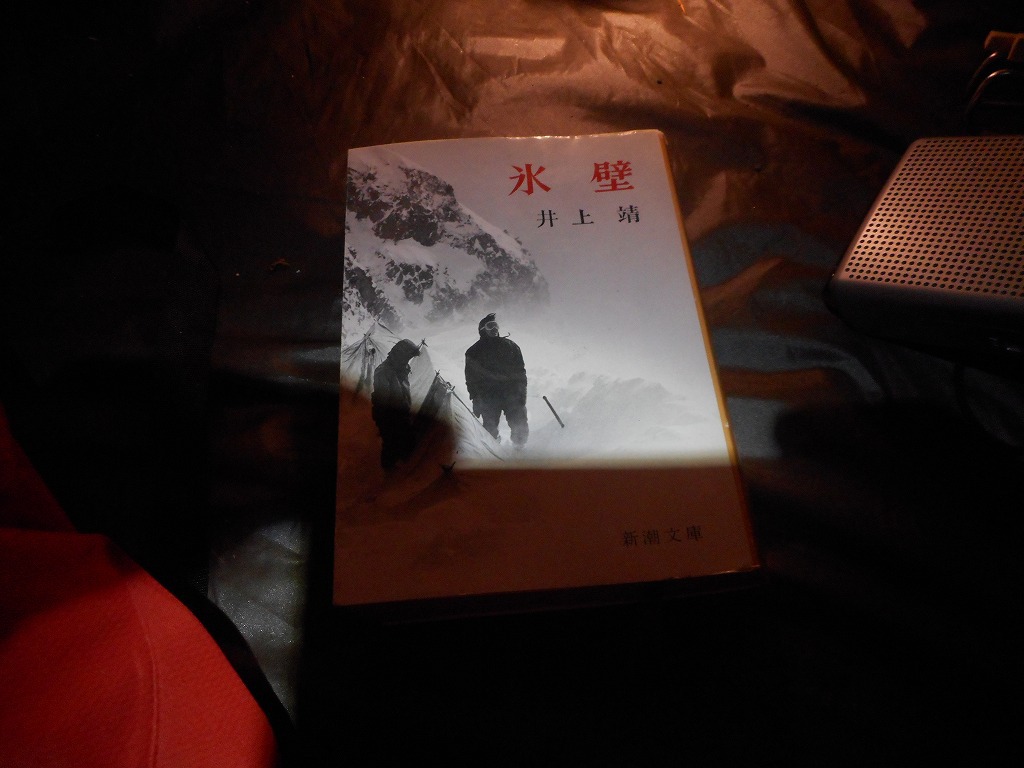
酔いも程良くなって来た。ウイスキーのお湯割を飲んだら寝よう。
シュラフに入って目を閉じる。雨はいつの間にか止んだようだが、風音が物凄い。ゴオーという音ではなく、ズゴゴゴゴゴオオオオオという音だ。山が吼えている様な音だ。
焚き火は消してあるので、風が強くても安心してシュラフに入っていられる。
寝に入っても、風の音や風がテントを押すのに気づいて、何度か目が覚めた。
テントが好き飛ばないかが心配になる。林道に放置してきた車も気になる。この風で木が林道を塞いで出られなくなったりしないか心配になる。
良くない妄想もしてしまったが、それでも朝まで疲れず眠る事が出来た。

朝になって風は弱まっていたが、まだ若干吹いている。

帰る際の林道の状態が気になるし、今回は早く帰ろう。
楽しいキャンプだった。またこんなキャンプがしたい。

2014年09月13日
ソロキャンプ あだたら高原野営場 20140912
2014年9月12日 あだたら高原野営場
天気や仕事の都合で、前回のキャンプから1ヶ月以上も間があいてしまった。
キャンプに行けないフラストレーションを山歩きにぶつけてはいたが、根がキャンパーなので、不完全燃焼していた。やはり、夜に一人で焚き火に向かい孤独に酒を傾ける、そんな夜を渇望しているのだ。
さあ、久々のソロキャンプ日和だ!
この時持っていった物
服装
| 服装 | 長袖シャツ、Tシャツ、ジーンズ、スニーカ |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | ダグ 焚火缶、エバニュー ハンドル、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | おでんの材料(ジップロック)、肉、ビール3本、プラティパス入り日本酒、スキットル入りウイスキー、水 |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、双眼鏡 ビクセン アルティマZ 7x50 |
ザック外の道具(使用したもののみ記載)
| 焚き火 | スノーピーク 焚き火台S、耐火グローブ、火バサミ、炭、黒じょか |
装備の更新はなし。
今週末、とことん山で温泉天国のソロキャンプ後、キャンプ場から30分強で行ける栗駒山の須川コースで山歩きをするという計画を立てていた。しかし、太平洋側は晴れなのに、日本海側は雨という、非情な天候である事が解り、急遽計画の変更が余儀なくされた。
ソロキャンプを楽しんだ翌日に山歩きをするという段取りだけは変えたくなかったので、行きたいと思っていた山をいくつかピックアップし、選んだ山の周辺のキャンプ場で一泊する事にした。
山は、私の住む仙台市から車で2時間程度で行く事が出来る、安達太良山を選択した。安達太良山も立派な百名山の中の一座だ。安達太良山周辺のキャンプ場には、フォレストパークあだたらという高規格のオートキャンプ場と、あだたら高原野営場という無料のキャンプ場がある。
周りに人が居て欲しくないという、私のソロキャンプの好みがある為、あだたら高原野営場を選択した。
このあだたら高原野営場は、1年中使われていて、雪中キャンプを楽しむキャンプ場としても選ばれる事があるようだ。かくいう私も、冬場に使えるキャンプ場を探していた際、目をつけていた事があった。
しかし、このキャンプ場には、個人的に大きな問題があるので、選択から外していたのだ。それは、トイレが汚いらしいという事だ。
私は汚いトイレというのが、大大大大大嫌いなのだ。汚いトイレで用を足すならば、そこらで立小便で済ませたい位なのだ。
トイレが汚いという噂のあるキャンプ場、今回ばかりはここを選ばざるを得なかったが、果たしてどうか・・・。
昼食を食べて一息ついた頃に自宅を出発する。
高速を走り、二本松インターで降りる。キャンプ場は、この二本松インターから、たった20分だ。安達太良山は都市に近い山なのだ。
キャンプ場に到着した。既に一張りのテントがあった。
空気はひんやりしている。
雑草が生え放題という感じでもなく、結構いいキャンプ場じゃないか。下もペグが効きやすそうな感じだ。

キャンプ場内を散策する前にテントを張ってしまおう。
場所は、タープを張るつもりはないので、木の下がいいだろうか。天気もいいし、雨も降らないだろう。
このキャンプ場中央の木の下にしよう。

さくっとテントを張る。
いいぞ。これは画になる。
優雅なソロキャンプといった雰囲気だ。これはのんびり出来そうだ。
キャンプ客が増えてきた。金曜だからだろうか。バイクに乗った人が、ツーリングでの一泊でここを結構選んでいるようだ。夕方までで、ライダーソロキャンパーが5名も到着した。
誰もいない夜を過ごしたかったが、ここは皆のキャンプ場なのだ。仕方ない。
バイク乗りは複数名でツーリングしているのを良く見かけるが、ここに来ているライダーは一人だ。孤高のライダーだ。一人で乗る乗り物に、一人で乗って、一人で旅をする。カッコイイじゃないか。私だったら話しかけられたくないので、声はかけないでおこう。

さて、キャンプ場の様子を見に行こう。
まずは炊事棟だ。無料のキャンプ場にしては、綺麗だ。みんな綺麗に使っているのだ。
次は懸案のトイレだ。・・・こりゃ駄目だ。評判通りだ。
今晩のトイレ、どうしよう。困った。
私はビールが好きなので、グビグビ飲んだら、それなりに出るものは出るのだ。しかし飲まない訳にもいかない。「小」の方は、ここで我慢するしかないようだ。
問題は「大」の方だ。急にしたくなったらどうするのだ。それを考えるだけで頭が痛かった。
近くにスカイピアあだたらという温泉施設があって、そこのトイレを借りるといい、というのを読んだが、徒歩では結構距離があるようなのだ。酒を飲んでからは車で行く事は出来ないのだ。
これは本当に困ったぞ。
いいキャンプ場なのに、本当に勿体無い事だ。

悩んでも仕方ない。
明日やっつける山を見ろ。トイレなどという、ちっぽけな心配事は忘れろ。
安達太良山は美しい。
しかし、トイレの悩みは帰るまで続いた。

このキャンプ場は、高原と名がつくだけあって、結構星が綺麗らしい。
しっかり双眼鏡を準備してきた。
夜が楽しみだ。

さあ、夕飯の準備だ。
今日はおでんだ。冷えてくる季節になったし、一人で食べたい分だけ作るのにも向いている。
タマゴと大根だけ下準備をして来て、焚火缶に練り物と一緒に投入し、味付けすればそれで終わりだ。本当に簡単だ。
ただ、味が染み込まねば美味しくない。
煮物もそうだが、一旦熱を加えた後に火から外しておくと、味が染み込みやすい。焚火缶で少しグツグツとやってから火から外しておく。これを楽しむのは、日が完全に暮れてからになるだろう。


おでんに味が染み込むまでは、焼肉で食いつなごう。
ビールをグイグイ飲み、肉をハフと食べる。
美味い。安い肉でも美味い。
一人焼肉なんて、一般的にははばかれる行為だが、ソロキャンプで焼肉するなら当然一人だ。何も変な事はない。
一人で焼肉を楽しみたい時は、ソロキャンプに限る。

日も暮れた。
そろそろおでんもいいだろう。
いい具合にすすけた焚火缶を焚き火台へと戻す。焚火缶は本当にいいアイテムだ。
箸でおでんをよそい、エバニューのハンドルで焚火缶を掴み、汁を食器へ少し注ぐ。
美味い。
夜になって冷えてきたから、なお一層美味い。
焚火缶でおでん、成功だ。


おでんには熱燗だろう。
日本酒をプラティパスの500mlのものに入れて持って来た。これを黒じょかに注ぎ、焚き火台に掛ける。
火加減に注意して燗をつけ、ぐい飲みで飲む。
美味い。クソ美味い。
おでんとの相性バッチリだ。
日本酒は、あまり好きでない酒だったが、キャンプをするようになってから、その良さが良く解ってきた。寒い時には日本酒である。

美味しいものを食べ、燗酒を飲んで体も温まった。
星は、あまり良く見えない。例のトイレの光が煌々としすぎていて、星を見るのに全く適さない環境になってしまっている。
今日の私の敵はトイレのようだ。
月も丸々として大きいので、今晩の星は期待出来ないようだった。
9時頃にキャンプ場に来た2人がテントを張り始めた。翌日からの休みを有効活用したいのは解るが、9時とは。それでも、そっと気をつけながら設営している様なので、気を使ってくれているのだ。
テントにもぐって眠くなるのを待つか。
いつの間にか寝てはいたが、ふと目を覚ました。2時だ。
人の声がぼそぼそと耳元で聞こえてた気がしたからだ。足音も聞こえる気がする。ビニール袋がカサリと音を立てた。
人が居るキャンプ場の深夜いうのは、本当に人なのか、それとも幽霊なのか良く解らない。
ふとした音で目を覚ましては寝てを繰り返した。

朝、暑くて目が覚めた。
太陽の光でテントの中が暑くなったからだ。寝汗をかいていた。短い夢を途切れ途切れで見て起きてを繰り返していたようで、どうもスッキリしない朝だった。
私の神経が細いからかも知れない。

さあ、「大」もしたい事だし、とっとと撤収したら二本松市内に戻って用を足して、安達太良山に向かおう。
天気は最高だ!

9月12日~13日学んだ事:
・トイレが綺麗だとは限らない
・深夜は人か幽霊か解らない
2014年08月03日
ワイルドソロキャンプ 宮城県仙台市O川S沢 20140802
2014年8月2日 宮城県仙台市O川K沢付近
1ヶ月以上もソロキャンプから遠ざかっていた。
週末は梅雨で雨になったり、玄関まで装備を準備していたのに、昼食を食べたら面倒になってしまって出掛けなかったり。
学生達は夏休みに入り、キャンプ場には人がいっぱい居るだろう。私は人の居る所には行きたくない。キャンプに行っても人が沢山居ると思うと、足が遠のいてしまう。
しかし、自然の中がひどく恋しい
久しぶりに人の居ない山でキャンプする事にした。
この時持っていった物
服装
| 服装 | 半袖シャツ、Tシャツ、速乾パンツ、スニーカ |
| 服装(持参) | 長袖シャツ |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | ダグ 焚火缶、エバニュー ハンドル、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | 豚汁の材料(ジップロック)、ソーセージ、ビール3本、スキットル入りウイスキー、水は現地調達 |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | 防寒着不要 |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、双眼鏡 ビクセン アルティマZ 7x50、てんから釣り道具 |
今回は、自然の中でキャンプをする。焚火の薪も現地調達だ。
そうしたキャンプでは、使うコッヘルもワイルドでなければならない。この日の為にダグの焚火缶を購入したのだ。
そして、焚火缶には吊るせるようにする為の持ち手がついてはいるが、吊るす為の道具(木の枝等)のない環境だった場合、焚き火にかかっている状態でこの持ち手を掴むのは結構難儀しそうだ。火の中にある焚火缶を自在に操作出来るようにエバニューのハンドルを購入した。
綺麗な沢が目的地なので、水は現地調達とする事にした。こうする事で背負うザックも軽くなるだろう。
久しぶりにザックを背負って、その装備だけでソロキャンプをする。
このザックだけのキャンプというのは、凄く楽しい。何かこう、やりきった、というような満足感を得られるのだ。自分の求めていたキャンプというのは、これなのだと。
そして何より、自然の中に入り、自然と一体となってキャンプするのは、すがすがしい気持ちになれる。
ああ、想像しただけでワクワクしてくる。
さあ、ザックを背負って進もう。
今回の目的地は、仙台市の奥地にある、O川の支流のS沢だ。私の自宅から1時間ちょっとという場所だ。
林道を車で進み、程よい場所で車を止め、目的地に向かって歩く。
キャンプをしようとしている場所の目星はついている。この沢でよく渓流釣りをしていたので、キャンプの出来そうなスペースのある場所を知っているのだ。

水の持込をしない為、ザックが軽く、足の進みも早い。
程なくして目的地に到着した。
想像よりも草が生えていたが、何とかテント1張分程度のスペースはあるようだ。
夏の渓流は、気をつけねばならない。
夏特有のスコールのような夕立が突然来る事がある。自分の居る場所で降らなくとも、上流でそれが降ると、知らぬ間に一気に増水するからだ。昨日も川の中州でキャンプしていて、急な増水で流されてしまい、家族が亡くなったというニュースがあったばかりだ。
しっかり注意しながらキャンプをする事にしよう。



テントを張って、薪となる流木の調達を行う。
この場所は、流木が少ないようだ。そして、その流木は殆どが湿ってしまっている。
焚き火をおこす。湿ってはいるが、流木は火がつきやすいので、何とかなる筈だ。
着火剤となるガムテープに火を点け、極細の枝から順に火にくべ、徐々に火を大きくしていく。手順さえしっかり守れば、少し湿っていても何とかなる。
薪を自然から得て、工夫しながら火をおこす。
最高に楽しい瞬間だ。


明るいが、もう5時半だ。夕食の準備を始めよう。
豚汁の材料をジップロックに入れて持って来た。こいつを焚火缶でワイルドに調理しようというのが、今回の大きな楽しみの一つだ。
沢から直接焚火缶へ水を汲み、焚き火に投入する。この画づらは、実にいいぞ。キャンプはこうあるべきだとすら思える。

ビールをプシュッとやり、自然に感謝してからグビグビと飲む。美味い。
薪が湿っている為に安定しない火の世話しながら、ビール片手に、豚汁を作る。
ふう、と溜息が一つ漏れる。
嫌な溜息ではない。自然の中に居ると、楽しくて溜息が出る瞬間があるのだ。きっと、ストレスが溜息になって外に出て行っているのではないかと思う。


いよいよ豚汁が出来上がった。
エバニューのハンドルが、実に良い働きをしてくれた。焚火缶とこのハンドルはセットで使うのがいいようだ。
豚汁をよそう為のおたまはない。最低限の装備しか持ってきていないのだ。おたまなどという、荷物になる道具など持って来る訳がない。
綺麗に洗ったシエラカップを、焚火缶の中に突っ込み、豚汁を強引にカップへとおさめる。作り方もワイルドならば、食べ方もワイルドだ。
美味い。自然の中で食べる物は何でも美味いが、今日の豚汁は特別美味い。

腹も落ち着いてきた所で、ゆっくりしよう。
ここの渓流は、ブユも居ないし、蚊も少ない。アブが少しいるが、焚き火の煙で寄り付かない。
夏のキャンプにしては、とても快適だ。
ザックで持ち運べるようにと購入した、エーライトのメイフライチェアに腰を下ろす。下が砂利なので、やや安定感に欠けるが、石に座ったりしていた事を考えると、大きな進歩だ。

本を持って来た。
私の大好きなクライマー、山野井泰史さんのお父上の本、「いのち五分五分 息子・山野井泰史と向き合って」だ。
山野井泰史さんは、奥多摩の山中で質素に暮らし、殆どスポンサーをつけずにアルパインスタイルで難度の高い山に向かっていく。考え方も、その世界第一線の実力も、実にカッコイイのだ。尊敬している。
そして、私は山野井泰史さんよりも、奥さんの妙子さんの方が大好きだったりする。
妙子さんも女性を代表出来るほどのアルパインクライマーで、度重なる極限の登攀で足の指2本を除いて、全ての手足の指が無くなってしまっている。それでも、岩登りを続けているのだ。
妙子さんは、柔和で可愛い性格なのに、逞しい生活力があって、それがとても美しい。素敵な人だ。
結婚するなら、妙子さんのような人と結婚したい。
知れば知るほど、もっと知りたいと思わせる二人なのだ。

湿っているというよりも、濡れていると表現した方が適切な流木を、だましだまし使う。
火の上の方に湿っている薪を乗せ、熱気で乾かし、乾いてきた物を、直火にくべる。
この焚き火の世話が楽しい。特にこの、ワイルド焚き火が最高だ。一日中でもやっていられる。
何でこんなに楽しいのか。

真っ暗になった。
本当の山奥なので、周りに明かりは一切ない。
小さなLEDランタンと、焚き火の火だけが、私の拠り所だ。
でも、全く怖くはない。この精神的に充実した時間がずっと続いて欲しいと思う。
たった一人で、こんな山奥なのに、何でこんなに楽しいのか。

昼間はあんなに暑かったのに、少しずつ冷えてきた。やはり山なのだ。
焚火缶の一番小さなものに沢の水を汲み、湯を沸かす。焚き火の灰が少し入ってしまったが、こんな事は一切気にならない。このお湯で、ウイスキーのお湯割を作る。
美味い。
命の水ことウイスキーと、沢の水、本当に美味しい。この体の中が綺麗になっていくようだ。

酔いも回ってきた。
焚き火の火を眺めていたら、うつらうつらし始めたので、テントに潜り込んだ。
夏特有の湿気でペタペタして不快だが、酔いに任せて寝た。

雨も降らず、実に快適なソロキャンプだった。
ただ、夏のキャンプというのは、暑さや湿気でとても不快だ。何度目の前の沢にドブンと入ってしまいたかったか。
夏がキャンプのハイシーズンと言うが、暑さや湿気という、どうにも対処出来ない問題がある。冬から始めた私としては、冬こそシーズンだとすら思う。
ああ、早く冬にならないかな。

8月2日~3日学んだ事:
・冬が恋しい
2014年06月25日
ソロキャンプ 須川湖キャンプ場 20140624
2014年6月24日 秋田県東成瀬村須川湖キャンプ場
平日に休みが取れたので、ファミリーキャンパーが多い為に土日に行くには躊躇われる、とことん山に行く事にした。
しかし・・・。
この時持っていった物
服装
| 服装 | 半袖シャツ、Tシャツ、ジーンズ、スニーカ |
| 服装(持参) | モンベルクリマエアジャケット |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | スノーピーク トレック900、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | ザックには入れず |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、双眼鏡 ビクセン アルティマZ 7x50 |
ザック外の道具(使用したもののみ記載)
| 焚き火 | スノーピーク 焚き火台S、耐火グローブ、火バサミ、炭 |
装備の更新はなし。
新しい道具を試す楽しみはないが、お金を使わずに済んでいるのだから、それでいい。
装備は、もうほぼ揃っていて、ザック一つでのキャンプの場合、食料等を除けば、私としては、これが完成形のように思う。ザックの他に、コンテナを持ち込んでいるが、実はその中身は使わない事もある。重い思いをして、コンテナをテントサイトへ運んで使わないのであれば、もう持って行かなくてもいいのだろうか。
現地到着目標を午後2時に設定して、自宅を出発する。
途中の花山で、昼食のそばを食べつつ、のんびりと向かう。
想定より30分近く早い13時半にとことん山に到着した。
おお、駐車場に車が停まっていない。もしかして今日は独り占め出来るかもしれないと考えながら、車を降りた。
駐車場の様子を見ると・・・何か、毛虫がいっぱい死んでいる。道路を横断している毛虫もいる。しかもかなりデカい。
前回、とことん山でキャンプをした時、小さな毛虫が結構いて、気持ち悪い思いをしていて、今回、その毛虫が大きくなっているのではないかと、少し心配していたのだ。
不安は的中していた。あの小さかった毛虫が成長し、5cm位になっているのだ。
ま、まぁ、もしかしたら、駐車場だけかも知れない。まずは、テントサイトの様子を見に・・・げぇーーっ!!入り口からして毛虫の糞だらけじゃねぇか!
この糞の上の木に、何百、何千という毛虫たちが居ると考えるだけで、もう駄目だった。そんな中で、のんびりイスに座りながら読書なんか無理だ。風が吹いてきて、突然ボドッと降ってくるに違いない。
この時期のとことん山は、毛虫の王国なのか。もしかして、それだから人が居ないのだろうか。
温泉に入りたくて、とことん山に来たのだが、入り口から奥に進むのすら躊躇われるのだ。もう、とことん山は諦めるしかない。
寒かったり暑かったりを我慢するのとは違うのだ。

さて、半分こうなるかも知れない事を予測していたので、代案は考えていた。
須川湖キャンプ場か須川野営場のどちらかだ。
この二つのキャンプ場は、とことん山から30分位で行ける距離のようで、特に須川湖キャンプ場は、素晴らしいロケーションで、星も綺麗だという前評判を聞いていた。
とことん山周辺は、携帯の電波が弱い為、スマホで調べる事ができない。記憶を頼りに探しに行こう。
とことん山へ通ずる国道398号線を戻り、須川方面を指す案内板があるので、そこを進んでいく。山道なので、それっぽい場所になれば解るだろう。
しばらく進むと、少し開けた場所に来た。湖が見える。これが須川湖だろう。辺りを探すと、キャンプ場を指す看板があったので、それに従い、細い道を進む。
湖のバックには、栗駒山か。凄くいい風景だ。

立派な管理棟で、受付をする。管理人は優しそうなおとうさんで、細かく説明してくれた。
テントサイトは沢山あるのだが、湖が増水しており、車で奥まで進めないようになっているとの事で、管理棟の近くのテントサイトを勧められた。テントサイトは、須川湖を取り囲むように配置されており、どこからでも眺めは最高なようだ。
近くの栗駒山荘の入浴券の優待券を発行するから利用してね、と券を貰った。
キャンプ場の利用料金は420円だという。私は薪も欲しかったのでお願いした。1020円を渡したら、400円が返ってきた。と言う事は、薪は200円か。安すぎる。

車から荷物を降ろしていると、私が背負っている大きなザックに管理人のおとうさんが気がついたようで、明日登山にいくの、と問われた。私は、とっさに、はい、と答えてしまった。何でこんな無意味なウソをついたのか、良く解らない。おとうさんは、ここは登山にいくにはいい場所だよ、目の前に見える山を縦走するにはうってつけだ、という事だった。いいなぁ、山。ソロキャンプなんかより、敷居が高くて、一人ではチャレンジ出来ない。
テントサイトに向かうと、確かに湖が増水状態で、道路が冠水している場所がある。進めなくは無いだろうが、大人しく近場に陣取ろう。
テントサイトは、テントを張るためのスノコ(?)が設置してある。そして、何より素晴らしいのは、テントサイト一つ一つに、直火可能な竈が用意されているのだ。
ロケーションは最高で、個別の竈付きだ。ここは、凄くいいキャンプ場だ。


私のテントは一人用なので、スノコの上に張ろうとすると、小さすぎて張り網の長さが足りず、テントを固定出来ない。大き目の石でもあれば、張り網を石に結わえて固定出来るので、スノコの上にテントを張っても良かったのだが、手頃な石もないので、竈の前の地面に張った。竈が使えなくなるが、焚き火台があるし、まぁいいだろう。
ただ、ペグが奥まで刺さってくれない。もしかすると、土の直ぐ下が岩盤なのかも知れない。


テントも張って落ち着いたので、少し散歩をしようと歩いていたら、管理棟の前で再び管理人のおとうさんに会った。
話をすると、案の定、今日のキャンパーは私一人だという。よしよし、そうこなくっちゃ。
虫が出るから、これを持っていきな、とバドミントンラケット型の虫避けアイテムを貸してくれた。やっぱり優しい。

さて、散歩しよう。須川湖を取り囲んでいるテントサイトを探検するのだ。
それにしても、この景色、本当に素晴らしい。風が殆どないので、湖面が鏡のようだ。


少し歩くと、コシアブラの木があった。
木を見て、一目でコシアブラだと解った。
私はこれまで、コシアブラを採取した事がなくて、山菜採取をする際は血眼になって探していたのだが、木を見つける知識がないのではなくて、その木の無い場所に行っていたから見つけられなかっただけだと、この時解った。
私の中の、スーパー山菜人の血が騒ぐ。当然、採取した。私は、このコシアブラの天ぷらが大好きなのだ。
それにしても、もう7月になろうかという頃だ。今頃、コシアブラが採取出来るとは、ここは標高が高いに違いない。後で調べてみた所、標高1200mだという。
散歩の道すがら、山菜採りのおかあさんが居て、私が握っている山菜は何、と聞かれた。これはコシアブラで、良く見ると食べ頃のが採れますよ、とコシアブラの白い木を優しく曲げながら採り方を教えてあげた。おかあさんは、丸裸にしないようにしなきゃね、と少しだけ採っていた。
初めて木を見たくせに、よくも人に偉そうに教えたものである。


さて、温泉に行こう。
栗駒山荘だ。山荘というからには、丸太小屋的な、前時代的な建物を想像していた。到着すると、近代的な宿泊施設がそこにあった。
キャンプ場で貰った優待券を使うと、日帰り入浴700円の所、400円になった。
結構客がいるようで、私が入った時で10名近く入っていた。
露天風呂から見る景色が、本当に凄かった。開けた眼下に泥炭地のシラタマノキ湿原が広がっている。空には、イワツバメ達が飛びまわっている。
湯はやや白濁していて、匂いは硫黄、温度も丁度良い。湯に入っては上がって、また入る事が出来る、重くない湯だ。
他の客もいるので、カメラを持ち込む事が出来なかったのが本当に残念だ。
露天風呂から見える風景としては、これまででナンバーワンだった。
http://allabout.co.jp/gm/gc/66624/

キャンプ場に戻り、湖の周辺から、流木を調達して、焚き火をする。
温泉で乾いた喉がビールを欲している。
焚き火を目の前に、ビールをプシュッと開け、自然に乾杯し、グイグイやる。美味い。


この自然を望みながら飲むビールは、本当に最高だった。
そして、私は一人だ。
この景色は、今、間違いなく私だけのものだ。


焚き火を始めてから、にわかに虫が集まりだした。小さいハエの様な虫だ。
普通、焚き火をすると、煙を嫌う虫はどこかに消えていくのだが、この虫は煙をもろともせず、私にアタックしてくる。
掃っても掃っても、常に30匹以上が私の周りに纏わりつく。
イテッ!
コイツ、刺すのか。刺された場所を見ると、針で突いた様な傷が出来、血が滲んでいる。
これは、ブユだ。
管理人のおとうさんから借りた武器を振り回すものの、全く効果がない。蚊取り線香だって焚いているが、全く効果が見られない。
ブユは、皮膚を噛み切って血を吸おうとするので、刺された瞬間からして痛い。そのブユが、何十匹も私に集って来る。
蚊でなく、ブユという事は、水が綺麗な場所の証拠なのだが、痛いし、痒いし、困り果てた。
日が暮れて、真っ暗になった頃から、ブユの攻撃は治まった。
後で被害箇所を見てみた所、足が9箇所、手が13箇所やられていた。ブユは蚊より厄介な敵だ。

夜は、霧が出た。
楽しみにしていた星は出なかったが、ブユからも開放され、やっとのんびり出来た。
やはり、標高1200mという事もあって、結構冷えるので、熱燗を飲んで、温まった。

気づくと、テント内が明るくなっていた。
もぞもぞと起きて、真正面の栗駒山を眺める。朝は朝の表情があって美しい。
早くもブユの大群が、私に攻撃を仕掛けてくる。
何故か、ブユは焚き火台の周りに集まっている。焚き火台は、昨日の炭の残りが燻っている。もしかすると、二酸化炭素か熱のどちらかに反応しているのではないだろうか。
これからの季節、虫対策をよく考えねばならないようだ。


6月24日~25日学んだ事:
・虫対策を講じろ
後日談:
ブユに噛まれた約20箇所は、噛まれた当日は大して痒くもなかったけれど、翌日の夕方頃から、激しく痒みが出てきた。蚊のそれとは比べ物にならない強い痒さ。
患部がぷっくりと赤く腫れ、キンカンを塗ろうとも、全く改善されずに痒さで頭を悩ませる。夜寝ては痒さで目を覚まし、気休めにもならないキンカンを塗っては寝る。目を覚ましては塗るの無意味な繰り返し。
とうとう我慢出来なくなって、皮膚科の病院に行った。
医者は、これは放っておくと患部が硬くなってしまい、なかなか治らないから早く来て正解だ、という事だった。
面倒でも朝晩、必ず薬を付ける様に、という指示だった。薬は、ステロイド系の塗り薬と、痒み止めの塗り薬、そして夜に飲む飲み薬。
先生、私はこの痒さから開放される為なら、サボらず塗ります。
ブユには本当に気をつけて欲しい。この尋常ではない痒さ、後悔すると思う。
キャンプをする時は、蚊取り線香などと言うぬるい対策ではなく、ブユも想定に入れて対策を考えて欲しい。
2014年06月15日
ソロキャンプ 浄土平野営場 20140614
2014年6月14日 福島県福島市浄土平野営場
土日は、もうどこのキャンプ場に行っても、人だらけだ。
この1週間、この週末を目指して、なるべく人が居なさそうで、そして星が綺麗なキャンプ場を探していた。
吾妻連峰の吾妻小富士の近くに、浄土平野営場という場所があり、とても良さそうだったので、ここへ行く事にした。
この時持っていった物
服装
| 服装 | 半袖シャツ、Tシャツ、ジーンズ、スニーカ |
| 服装(持参) | モンベルクリマエアジャケット |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | スノーピーク トレック900、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | ザックには入れず |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、双眼鏡 ビクセン アルティマZ 7x50 |
ザック外の道具(使用したもののみ記載)
| 焚き火 | スノーピーク 焚き火台S、耐火グローブ、火バサミ、炭 |
| 調味料 | コールマン スパイスボックス |
| タープ | アライテント ビバークタープM、アライテント コンパクトポール150 |
これまで、星が良く見えそうな時、天体望遠鏡をキャンプ場へ持って行き、天体観測をしていたが、天体望遠鏡は結構大きく、設置がやや面倒な事もあって、最近は出番が少なくなっていた。
手軽に天体観測を楽しむ為、双眼鏡を購入する事にした。ネットで評判を調べると、ビクセンのアルティマZ 7x50が入門機としても、性能としても評判が良いと言う事だった。
重量も750g程度と、近似タイプに比べると軽く、持ち運びにも良さそうで、ザックにも入れられそうだった。早速、これを購入した。
双眼鏡での天体観測というのは、結構ポピュラーで、星1個ずつを観察するというよりかは、星雲などのやや広い範囲を見るのに向いているのだという。楽しみだ。
東北も梅雨に入り、週末が雨になると出掛けられず、悶々する事が続いていた。
当初の予定では、福島の浄土平野営場ではなく、秋田の須川湖キャンプ場に1泊し、翌日、同県のとことん山にもう1泊する計画としていたが、週末の秋田は雨の為、作戦変更せざるを得なかった。
双眼鏡も買ったことだし、星の良く見える場所でテントを張りたかった。そして、人の居ないであろう場所が良かった。
マイナーなキャンプ場で、星が綺麗、という条件で調べていた所、福島の浄土平野営場を見つけた。
ここは、日本百名山の吾妻連峰の標高1600m地点という、非常に高度の高い場所にあって、吾妻小富士という山を望めるキャンプサイトがあるという事だった。
吾妻連峰の吾妻小富士と言えば、雪兎の事くらいしか知らなかった。雪兎というのは、5月くらいになると、山肌の雪が兎に見えるようになり、この兎が出現すると、田植えのシーズンなのだという知識しか持って居なかった。
よくよく調べてみると、吾妻連峰へ続く吾妻スカイラインは有料だったのが無料開放されるようになり、気軽に向かえる場所になったようだった。そして、今回の目的地の近くには、浄土平天文台というのがあり、紹介サイトで「天の川など当たり前」と書かれている位で、星空の美しさは補償付きと言っても良かった。
目の前に吾妻小富士の見えるキャンプサイト、満点の星空、もうここに行きたくて仕方がなくなっていた。
この浄土平野営場は、仙台市からだと、2時間弱という所だ。
東北自動車道に乗り、福島西インターで降り、その後は吾妻スカイラインを進んで行く。
ぐねぐねという山道をひたすら走ると、急に風景が変わって来る。木の少ない、ハゲ山の風景になってくるのだ。
森林限界だ。標高が高くなると、高木が生きる事が出来なくなり、森林を形成出来なくなる。森林限界は東北だと標高1600m程度からという事で、この吾妻連峰は標高1600mはゆうに超えた高さにあるのだ。
この吾妻連峰は、活火山で、しかも噴煙が立ち上っている。道路には、火山ガスの為にここに駐車しないように、という旨の注意を促す為の看板も多く立っている。ここは、まさに生きた山だ。

今回の目的地のキャンプ場は浄土平野営場だが、浄土平キャンプ場だとか、地図や看板を見ると兎平野営場だとか書いてある。兎平というのは、前述の雪兎の事だろう。それにしても、名前が統一されていない感が、何ともマイナーさを感じさせる。
付近へ行ったものの、キャンプ場の場所が良く解らなかったので、浄土平ビジターセンターに寄り、場所を教えて貰う。ビジターセンターから更に進んだ先に、兎平駐車場というのがあり、その真向かいの道から進んだ先がキャンプ場だという事で、パンフレットを貰った。このパンフレットには、浄土平野営場と書いてある。ウーム。
兎平駐車場に到着した。
平地では晴れの予報だが、この山は雨が降っている。しかも風もかなり強い。
キャンプ場へは、車でも進めそうだが、先が良く解らないので、まずは徒歩で向かうしかない。
車内でレインウェアを着、ザックにはザックカバーを被せ、浄土平野営場へ向かう。
ここは、思った以上に季節が進んでいない。道の脇に雪があるのだ。雪の脇には可愛いフキノトウも居る。

3分程度進むと、車が見えてきた。何だ、駐車場があるのではないか。歩いて、しかもびしょ濡れになって損をした。
受付は、吾妻小舎という小屋で行うという事で、小屋の戸を開き、こんにちは、と声を掛ける。電気が付いておらず、人が居ないと思ったら、はい、と声がした。
声の主のおとうさんに、ここでキャンプしたい旨を伝え、受付簿に所定の情報を記入し、テント1張分の500円と、基本料金の400円で、計900円を支払った。空いているから、場所は何処でも自由に選んでいいよ、という事だったので、吾妻小富士の望めるサイトにしたい事を伝えると、AサイトのA1という場所を勧められた。
そのような話を、そのおとうさんとしていたら、調理中だったようで、加熱中のおかずを焦がしてしまったようだった。ごめんなさい。
テントサイトに向かうと、素晴らしい風景が待っていた。
目の前が吾妻小富士だ。雨でもあまり霞んで見えないのは、本当に近いからだ。
星を目当てに来たのに、雨というのは、出鼻を挫かれた感があるが、この眺めで、ふと気持ちが切り替わった。

さて、雨の中でテント設営をしなければならない。
ウッドデッキにテントを張るべきなのだが、雨が気になる事や、この強風の中でペグでなく石でテントを固定しようものなら、テントが飛ぶ様がありありと想像出来たので、ウッドデッキの脇に設営した。

雨を凌がねばならないので、久しぶりにタープも張る事にした。
久しぶりだが、結構短時間で張ることが出来た。

テントとタープの位置関係はこんな具合となった。

タープの中で雨が止むのを待っていると、一気に晴れてきた。
山の天気は変わりやすいというが、本当に変わりやすい。強風は相変わらずだが、さっきまでの雨が上がり、青空になった。
本当に、どうなっているんだ。


少し、辺りを散策しよう。
さっきの吾妻小舎の先に道があって、その先に桶沼という火山湖があるという。行ってみよう。
吾妻小舎の前に差し掛かると、さっきのおとうさんが居て、少し話をした。テントサイトの景色が素晴らしかった事、この場所の自然が美しい事。
おとうさんは、熊に気をつけてね、と言った。私がテントを張ったAサイトの奥のBサイトで熊の足跡を最近見たというのだ。冬では、この吾妻小舎の前にも出没し、大きな糞をしていくのだという。
私はどうも、熊の神様に愛されているのか、結構行く先々で熊の影を感じさせられる。
さて、桶沼を目指して、吾妻小舎の先の細い細い道を進んでいく。
雨の後だから、結構ぬかるんでいる。人の足跡はあるが、熊の足跡はないようだ。
10分位上ると、開けた場所に出た。桶沼だ。
ああ、美しい。
ソロキャンプをするようになって、色々出かけるようになったが、山の自然の持つダイナミックさというのは、他とは一味も二味も違う魅力を持っていて、どうだと言わんばかりにグイグイ来るパワーがある。

テントサイトに戻って、夜の準備をしていると、吾妻小舎のおとうさんが来て、タープはテントと見なす事になっているから駄目だよ、という事を言われた。
そして、テントサイトでは、ガスストーブはいいが、薪や炭を使った調理は駄目で、そういうのは、炊事場でやって欲しい、という事だった。
理由は、言わなくても解る。この自然を継続していく為だ。タープは、まあ、ルールはルールだ。仕方ない、片付けよう。
先程も経験した様に、山の天気は変わりやすい。それに、タープ無しで荷物を野ざらしにするのは勇気が要る。
荷物類は、テントに入れられるものはテントに入れ、コンテナなどは、炊事場に避難させ、炊事場で夜を待つ事にした。
炊事場は、Aサイト、Bサイト、Cサイトそれぞれに設けてあって、水場も竈もあって、自由に使っていい事になっている。意外と、結構施設は整っているのだ。

焚き火の火が点かない。
1時間もチャレンジしている。
通常であれば、落ちている細い枝などを集めて、焚き付けに使ったりするのだが、さっきの雨で、全部濡れてしまって、火が点いても弱々しく、薪までどうにも火が点かないのだ。
ガムテープ着火法や、新聞紙も試してみたが、駄目だった。
今日は、火の神様に見放されているとしか思えない。
ガムテープも尽きかけ、最後のチャレンジを行った。湿っている小枝は一切諦め、ガムテープの着火剤にだけに賭ける事にした。薪も、乾いている物と、火の付きやすそうなものだけを厳選し、キャンプファイヤー方式で、縦横を交互に組み上げて見た。
火をつける。
半ば湿った草や小枝に火が邪魔されず、上へ上へと火が伝っていく。小さな火が徐々に薪に燃え移り、やがて大きな火になり、完全に薪に火が移った。
成功した!
この感動は、私にしか解らない。1時間も失敗を繰り返したのだ。ようやく大きな火になった焚き火を見た私の気持ちは、原始人がようよう火を熾し、これから夜を迎える準備が出来た喜びと近しいものがあると思う。
新聞紙も無くなり、本当に最後のガムテープだった。これで駄目だったら、今日は焚き火無しで、ガスストーブで調理する事を覚悟していた。
本当に安心した。

それにしても、この電灯の点く中の焚き火と言うのは、どうにも様にならない。興が削がれるというか、何とも味気ないキャンプだ。
所謂完ソロで、いつもの通り一人ぼっちだが、今日は火の神様にも嫌われ、いつもより強く疎外感を感じる。
ネットのどこかで、ソロキャンプに行く理由は、家族の大切さを再確認しに行く為だ、というのを読んだ事がある。
私も、今日、家族を想った。
ソロキャンプをした事がある人なら、解る感情だと思う。

さて、待ちに待った夜だ。
星だ。星を見るのだ。星を撮影する為に、マニュアル撮影での長時間露光の方法も勉強して来た。
どれどれ、天の川が当たり前の星空は・・・そこには無かった。
やはり、少しもやがかかっており、星が余り見えなかった。
北斗七星付近を撮影してみるも、イマイチだった。私のやり方が悪いのだろうか。感度をもっと上げた方が良かった様だ。
撮影が駄目なら、双眼鏡だ。
双眼鏡を目に当て、星にピントを合わせる。
おお、と声が出た。肉眼では見えない小さな星の光が見える。あの暗い空間に星があったのかと思う。
双眼鏡での天体観測の場合、手振れが気になるという事が書いてあったが、このアルティマZ 7x50程度の倍率であれば、それもあまり気にならなかった。

それにしても、冷えてきた。
ここは標高1600mだ。
こんな、とことん山でくつろいでいた時のような、自然をナメた格好で過ごせる筈がない。ザックの奥から、ダウンジャケットとダウンパンツを引きずり出し、フリースの下と、パンツの下に履いた。体温で温まるまでは少し寒いが、じきに暖かくなる。やはり臨機応変に対応出来る装備を持っておくというのは、大事な事だ。
少し経つと、月が出てきた。
もしかして、満月か。凄い光で輝いている。
この光では、星はもう観測できない。
それでもしばらく星を眺めていたが、何とも贅沢な時間だ。
テントに入り、酔いに任せて寝る。
ふと目が覚めると、雨が降り、風が更に強まっていた。
炊事場に放置していたイスは大丈夫だろうか、酔っ払って道具を放置していないかを心配した。

朝、早々に片付け、吾妻小富士に登ることにした。
この、ナメた格好でも、すぐ登れるのだ。
ビジターセンターの前に車を停める。
ここが、浄土平天文台だ。実は、土曜日の夜は、開館していて、浄土平野営場から歩けば見に行けるのだが、酔っ払った私は、星が好きなくせに、元よりそれを放棄していた。

標高1707m、吾妻小富士。
誰でも登れるように、階段がついている。
ゆっくりと登っていく。

振り返ると、絶景だ。
仙台から、たった2時間弱で、これまでの景色を見られるのだ。本当に凄い。



頂上だ。
頂上まで、10分もかからなかった。ちょろいもんである。
あの、とことん山の「動物たちの小道」の地獄坂の方が、100倍キツかった。
ああ、私はやったのだ。
吾妻小富士、単独無酸素無補給登頂!
なんて。


2014年06月02日
ソロキャンプ とことん山キャンプ場 20140601
2014年6月1日 秋田県湯沢市とことん山キャンプ場
連休が取れなかったり、プライベートの用事などの理由で、1ヶ月近くキャンプに行く事が出来なかった。
だいぶフラストレーションも溜まっていたので、キャンプに出掛ける事にした。
この時持っていった物
服装
| 服装 | 半袖シャツ、Tシャツ、ジーンズ、スニーカ |
| 服装(持参) | モンベルクリマエアジャケット |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | スノーピーク トレック900、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | ザックには入れず |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | ザックには入れず |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン |
ザック外の道具(使用したもののみ記載)
| 焚き火 | スノーピーク 焚き火台S、耐火グローブ、火バサミ、炭 |
| 調味料 | コールマン スパイスボックス |
| その他 | 本 |
5月下旬から、異常な暑さが続いている。仙台でも30℃オーバーも珍しくない。
今回キャンプした日も真夏日の予想だった。キャンプ場は山だとは言っても、気温も高く、日差しもあるだろう。
服装は夏仕様で行こう。寒かったら着ればいい。
これまで使用して来た貰い物のミニLEDランタンだが、光が弱いくせに電池の消耗が激しく、対コスト効果が全く得られていなかった。小型で光量のあるLEDランタンを探し、購入した。ジェントスのエクスプローラーEX-837NXだ。評判も上々だから、役に立ってくれるに違いない。
今回のキャンプはキャンプ場だからいいとしても、ザック一つを担いでキャンプするスタイルの場合、イスを持っていけず、お尻が痛くなる事が多かった。重さと使用感の両方が満足出来るイスを探した。何と重量635gで座り心地が抜群という、エーライトのメイフライチェアというのを見つけた。収納サイズもかなりコンパクトなので、ザック内にパッキングしてもかなり余裕だ。使うのが楽しみだ。
今回キャンプするとことん山キャンプ場は、秋田県湯沢市にある。以前は、皆瀬村という地名だったが、2005年に湯沢市と合併したと言う。
私の住む仙台市からは、急げば2時間半弱、のんびり行って3時間強といった距離だ。
何と言ってもとことん山の良さは、温泉だ。掃除の時間を除けば、24時間いつ入っても自由、入り放題なのだ。風呂場には、源泉掛け流しの温泉が3段並んでいて、作りも美しい。お湯の質も良い。
ここはオートキャンプ場ではないが、非常に人気のあるキャンプ場で、ゴールデンウィークやお盆などは超満員のようだ。
そして、とことん山は、私の特別な思い入れのあるキャンプ場だ。
何故なら、私が初めてキャンプを体験したのは、このキャンプ場だからだ。それは約20年前だ。
今、こうして大人になってキャンプを楽しんでいるのも、このとことん山でキャンプの楽しさを学んだからだ。あの時の体験が、大人になって思い出され、再びキャンプを始めるきっかけになったとも言える。
あの当時は、アウトドアブームになるちょっと前で、まだアウトドア人口も少なかった様に思う。
キャンプ道具も、今の様に洗練されたデザインの物は少なく、テントはロッジ型を使用している人が殆どだった。私の家族もご多分に漏れず、ロッジ型テントだった。
キャンプ道具と言えば、コールマンがその象徴だった。コールマンのキャンプ道具が皆のあこがれの品で、それを買おうにも非常に高く、なかなか手が出せない時代だった。例えば、コールマンのドーム型のテントは10万円弱したような記憶がある。
今でこそオシャレな道具を揃え、オシャレなアウトドア系のファッションに身をつつんでキャンプする人が殆どになったが(私は今でもイモいキャンプスタイルだけど)、当時は皆、手探りでアウトドアを楽しんでいた。
それは情報が無かったからだ。インターネットも無かったし、アウトドアの本も僅かだった。
皆、手探りで試行錯誤していたけれど、今のカタログのイメージ通りのキャンプスタイルよりも、余程生き生きしたキャンプではなかっただろうか。皆、思うがまま、自分のキャンプスタイルでキャンプしていたし、それを楽しんでいた。
これは私が大人になって、楽しかった当時を思い出すからそう思うだけだろうか。
当時の思い出を少し書きたい。
約20年前の初めてのキャンプ、あの時、私は小学5年生だった。
確か7月下旬に2泊3日でキャンプに行ったのだ。1泊目はとことん山で、2泊目は鳥海山のふもとにあるキャンプ場だった。鳥海山のキャンプ場の名前は覚えていない。
初めてのキャンプは興奮した。
1泊目のとことん山では、温泉に入りまくり、1日で10回以上入った。弟も10回以上入り、何と鼻血を出した。
夜になってバーベキューをし、お腹いっぱいになった所で、懐中電灯を片手にカブトムシやクワガタを探しに行った。カブトムシたちは光に集まる習性があるので、自動販売機の前に行くと、ミヤマクワガタなどを捕まえる事が出来た。
キャンプ場の近くには大噴湯という、超高温の源泉が噴出する観光名所があって、早朝、そこに温泉卵を作りに行った。源泉の温度は98℃なので、温泉卵にはならず、出来上がったのは、ただのゆで卵だった。それでも楽しくて美味しくて、全部食べた。
2泊目はキャンプ場の名前は覚えていないが、鳥海山のふもとにあるキャンプ場で、キャンプ場というよりも、ただの草原だった。
山を見ると鳥海山の万年雪が見えた。
この夜、私は生まれて初めて天の川を見た。天の川は形容しがたい美しさだった。当時の私は目が良くて、星々の中を動く人工衛星も、つぶさに見る事が出来た。この時以後、天の川を見る事が出来ていない。私は、この時の星空を今でも追っている。だから天体望遠鏡を購入したのだ。
当時としては珍しいビデオカメラでキャンプの様子を撮影しており、そのビデオテープが擦り切れるまで何度も何度も家族皆で見返しては、楽しかったね、と話をした。
この2泊3日は、本当に楽しかった。
その思い出があってこその、今の私のソロキャンプなのだ。
さて、とことん山だ。
国道398号線をひたすら秋田に向かうと、とことん山に到着する。非常に解りやすくていい。
到着すると、あの懐かしい、リスのマークの看板が見えてきた。初めてのキャンプ以来、何度かとことん山には来ていたが、今回こうして来るのは、本当に久しぶりなのだ。この看板を見たら、こみ上げる懐かしさを感じた。

駐車場に車を停める。
思ったよりも、人が居るようだ。知らない人が周囲にいる環境でソロキャンプするのは、一番最初の時以来だ。
他のキャンパーが少ないのを期待して、土日ではなく日月のスケジュールを組んだのだが、やはり人が居るのは仕方ないか。
受付棟にいって受付をする。この受付棟は、20年前は東屋として無料開放されていた。雨の日はこの中でオセロやトランプをした記憶がある。
このキャンプ場は利用料が非常に安い。施設は綺麗だし、素晴らしい温泉に入り放題で1人820円なのだ。破格である。
受付で受付カード(?)に記入していると、以前利用された事はありますか、と柔和そうな管理者のおとうさんに問われたので、20年前くらいですがあります、と回答すると、では案内は不要ですね、と言われた。まあ、大丈夫だろう。

20年ぶりだ。様子を見て回ろう。
確か、釣り橋があった筈だ。この東屋の横を抜けると・・・げぇーっ!!毛虫が3匹釣り下がって道を塞いでいる!!
毛虫が上の木からお尻から出した糸で垂れ下がっているのである。
私は毛虫が嫌いだ。ゴキブリも嫌いだが、それ以上に嫌いだ。何故あんなに醜く、気味が悪いのだろうか。
哺乳類でも爬虫類でも、赤ちゃんというのは大抵可愛い。しかし、昆虫の赤ちゃんは醜いのが多い。毛虫も、天敵から身を守る為に醜く、そして毒を持つなどして進化したのだろうが、もうその姿を見るだけで悪夢である。
知らずに進んで体に毛虫がくっつくのを想像するだけで、蕁麻疹が出そうだ。
釣り橋の奥に行くのは諦めよう。
それにしても、暖かくなったのだから、多少の虫が居るのはいいのだが、毛虫とは困った。毛虫が嫌いなアウトドアマンは失格だろうか。

テントを設営しよう。
人が少ないから場所を選び放題だ。
温泉に何回も入りたいので、温泉棟の近くに陣取ろう。
近くにテーブルなんかもあって、結構いい場所を確保出来た。
キャンプ場の外は真夏のような日が差しているが、ここは木漏れ日が気持ち良い。

さあ、温泉だ。
これの為にここに来た様なものだ。
子供の頃を思い出して、今回も温泉に何度入れるかチャレンジしてみよう。
久しぶりだが、温泉は変わっていなかった。
半露天のヒノキ風呂が1段目にあって、2段目3段目が露天風呂となっている。
温度は熱くも無く、ぬるくもなく、実に丁度良い塩梅だ。熱い温泉ばかり入っていたせいか、熱さに物足りなさを感じる自分がいるというのも不思議だ。
お湯に濁りは殆どなく、湯質もさらさらしていて、匂いは温泉らしい硫黄の匂いがほんのりとする。ガツンとパワーのあるお湯ではないので、何度でも入れるし、入った後も疲れたりしない。
私の温泉と言えば、やっぱりこの、とことん山の温泉なのだ。



のんびりしよう。
のんびりしたキャンプをするつもりだったので、今回は本を持って来た。本を読んでは温泉に入り、温泉に入っては本を読むのだ。
夢枕獏の神々の山嶺だ。
本のレビューをしても仕方ないので、ここではしない。
少し前に漫画版を読んで、その素晴らしさに感動し、原作小説を購入したのだ。私は結構漫画も読む方なのだが、この神々の山嶺は、私の好きな漫画の3本の指に入ると思えた程だった(実際入った)。
これは登山の小説なのだけれど、私は登山をしない。興味がないか、というとあるのだけど、きっかけがないので、していない。してみたいな、登山。

日が暮れて来たので、夕食にしよう。
今回は、焼肉と常夜鍋だ。
焼肉は岩塩プレートの上に味の付いていない肉を焼いて食べる。ほんのりとまろやかな塩味がついて美味しいのだ。
そして常夜鍋だ。学生の頃、これが好きで良く食べていた。鍋と言っても、材料は豚肉とほうれん草のみだ。鍋に酒を加えた湯を沸かし、その中に食べたい分だけの豚肉とほうれん草を入れ、頃合になったら湯から引き上げ、ポン酢につけて食べるのだ。この、鍋に入れては食べ、を繰り返すのだ。
シンプルながら、非常に美味い。一晩中食べていられる事から、常夜鍋という名前になったそうだが、本当にそれ位美味しいのだ。
しかし、私は小食なので、焼肉を食べたら、かなり満足してしまい、食べたかった筈の常夜鍋は少し食べただけとなってしまった。私のような人間は、順番など考えずに食べたいものから先に食べた方がいいようだ。



ビールを飲んでは温泉に入り、日本酒を飲んでは温泉に入った。
酒を飲んだら温泉に入らない方がいいというが、飲みながら入らないだけまだいいだろう。
それにしても贅沢な時間だ。焚き火の火を見つめながら、考え事をしたり、嫌な事を思い出したらラジオを聴いてみたりする。温泉に入りたいと思った1分後には湯船に入れる。
こんな素敵なキャンプ場、他にあるだろうか。
キャンプ場に到着してから寝るまでに6回温泉に入った。

目覚めて最初にする事は、朝風呂だ。
二日酔いになりかけの寝起きの目をこすりながら、おもむろに温泉へ向かう。
朝5時半、誰も入っていない。独り占めだ。
昨日も温泉で人と一緒になったのは1回だけだった。やはり土曜宿泊にしなくて良かった。

さて、早く目覚めたのだから探検しよう。
夏だったら、クワガタでも探しにいく所だが、まだ6月だから散歩してみよう。
キャンプ場の脇に、「動物たちの小道」という遊歩道が最近出来たようだ。
山頂まで830mか。大した事ない。朝の散歩に丁度いいのではないか。

なだらかとは言えない傾斜の道を進んでいく。
何の花だろうか、綺麗だ。植物を見ながら進んで・・・いや、登って行く。
だんだんキツくなってきた。
これは二日酔い一歩手前の人間が歩くコースじゃない。しかも、新調したスニーカで靴擦れを起こしており、かかとを踏んだ状態なのだ。
早朝とは言え、日光が結構強い。息が上がり、背中から汗が噴出す。水分補給用の水を持ってくるべきだった。
もうかなり歩いた。
たった830mだし、そろそろ目的地が見えてきてもいいのではな・・・げぇーーっ!!この坂は傾斜角度40度はあるんじゃないか?
「動物たちの小道」恐るべし。いや、こんなの小道じゃない。地獄坂と呼ぶべきだ。
よし。自分を孤高の登山家、羽生丈二(前述の神々の山嶺の主人公の一人)だと思って登ってみよう。黙々と登る。むしろこれは余計にキツい・・・ストイック過ぎて全然休めん!馬鹿か。


じわりじわりと登り、最終目的地に到着した。
ここは、とことん山に隣接しているスキー場のリフトの降り口だ。
ずっと下の方にとことん山の緑色の建物が見える。
凄い傾斜だ。高くて足がすくむ。
こんな傾斜をスキーで下っていくのか。エクストリームスポーツ会場か、ここは・・・。


さて、予想外のキツい登り下りをしたが、私にはまだやらなければならない事がある。
大噴湯に温泉卵を作りに行かねばならないのだ。あの楽しかった小学生の時のキャンプをなぞるのだ。
しかしだ。大きな問題が一つある。私は卵を持ってくるのを忘れたのだ。
志を曲げてはならぬ。
よし。世界初、エア温泉卵作りに行く事にする。
いざ行かん大噴湯へ。

大噴湯は、深い渓谷の下にあり、激しく熱い蒸気が常時噴霧している。
その蒸気の音は、キャンプ場に居てすら、夜中はゴオオと聞こえる様な気がするし、実際、何か地鳴りのような音が聞こえる。それ程、強烈なのだ。
「動物たちの小道」で消耗した体力で、この深い谷に入らなければならないのは結構キツい。頑張ろう。
深緑色の川の水にはイワナが住んでいる様で、魚影が見える。イワナは冷たい水を好む筈だが、こんな場所に居るとは、自然は不思議である。
小安峡温泉(とことん山のある温泉の事)の源泉は、98度もある。大噴湯では、その源泉が、そこかしこから流れ出ていたり、ゴボゴボと噴出している。
一番の見所は、写真の様に、激しい蒸気が噴出している場所で、ここを通ろうとすると、否が応でもこの蒸気を浴びねばならない。熱くて通れないという事はないが、蒸気で服が湿る。
子供の頃、みかんのネットのような物に卵を入れ、この湧き出ている源泉に浸して、温泉卵が出来るか実験したのだ。出来上がった温泉卵は単なるゆで卵だったが、それでも良かったのだ。
辺りに漂う硫黄臭を嗅ぎながら、あの当時のゆで卵の匂いに結び付けてみようとする。
やっぱりここも、私の思い出の中では重要な場所なのだ。

それはそうと、温泉にはトータル8回入った。
鼻血は出なかった。
6月1日~2日学んだ事:
・ソロキャンパーはロマンチストだ
2014年05月07日
渓流ソロキャンプ 宮城県川崎町某所 20140506
2014年5月6日 宮城県川崎町某所
私の連休の残りは2日ある。
しかしゴールデンウィークだ。どこに行っても人だらけだ。
キャンプ場に行こうものなら、ファミリーキャンパーだらけで、一人でキャンプをして周りの目に耐えられそうにない。
人の居ない場所に行くしかない。
そうだ。4月5日、4月12日にチャレンジして駄目だった、あの一番奥の砂防ダムを目指そう。
この時持っていった物
服装
| 服装(遡行) | ニット帽、Tシャツ、ネオプレンタイツ、ネオプレンソックス、渓流シューズ |
| 服装(キャンプ) | ニット帽、モンベルクリマエアジャケット、ブレスサーモウールヘビーウェイトアンダーウェア上下、パタゴニアの防寒着、裏地がフリースのパンツ、スニーカ |
ザック内(グレゴリー バルトロ65)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー、イスカ ゴアテックスシュラフカバーウルトラライト ワイド |
| クッカー類 | コッヘル、ストーブ、ガス、シエラカップ、スポーク |
| 食料 | 鍋材料(刻んだ野菜や肉をジップロックに)、鍋キューブ、アルファ米1個、サトウのごはん1個、スープ、お茶、ビール500ml3本、ウイスキー入りスキットル、水2L(プラティパス)、いろはす(水) |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ、パタゴニアマウンテンパーカ、モンベルクリマエアジャケット、ブレスサーモウールヘビーウェイトアンダーウェア上下、スニーカ、防寒パンツ |
| その他 | ラジオ、熊よけ鈴、ナイフ、コンパクトデジカメ、ヘッドライト、ミニLEDランタン2個、トレッキングポール、てんから竿、仕掛け一式 |
5月に入り、仙台では毎日20℃を越えるようになった。
今回も目的地の川崎町の里山も、大きくは変わらない筈だ。そして今回はド晴天で、日差しが結構きつい。移動時の上半身はTシャツにする事にした。
移動時の服装をTシャツにしたのに伴って、キャンプの際の防寒具をザックに詰め、背負って持っていかねばならなくなった。マウンテンパーカ、フリース、アンダーウェア上下である。キャンプ時に寒い思いをしたくないが為のものだが、これの所為でザックはパンパンである。それに加えて、困り者のスニーカもザックに入っている。
季節の端境とは言っても、早く荷物を減らしたいものだ。
そして水だ。前回まで、プラティパスのビッグジップSLというハイドレーションシステムを使用していたが、これを止め、いろはすに変更した。こまめに水分補給が出来るので最高に素晴らしいのだが、2日分の水を担いでいくというのは、どうも冗長なのだ。ペコペコのいろはすのペットボトルを持って行き、無くなったらプラティパス2から補充すればいいのだ。
勿論、ビッグジップSLでも同じ事は出来るのだが、これはザックの奥に水筒が格納されるので、取り出すのが厄介なのだ。
ザックのバルトロ65には、水筒ホルダーが付いているので、作戦観点としても悪くはないだろう。
現地に向かうべく林道を進むと、車がスタックしており、おじいちゃんとおばあちゃんが困った顔をしていた。私は仙台男児だ。放っては置けない。助ける事にした。
おじいちゃん達は、山菜を取りに来た所、車をUターンしようとしたら曲がる位置が悪く、沿道に乗り上げる形になってしまったのだという。その沿道に突っかかった状態の上、車の片輪が丁度轍の上にある為、スタック状態となってしまっていた。
おばあちゃんがしきりに、ごめんねというので、何とかしなければならない。
前後が土にめり込む形になっているので、それをスコップで少し取り除いてみた。
おじいちゃんが試みるも駄目だったので、私がハンドルを握らせてもらった。ハンドルを目いっぱい切ってみてバックしてみた所、車が後ろに進んだ。次に、少し勢いをつけて前に曲がると、脱出出来た。
おじいちゃんとおばあちゃんの安堵した表情がとても良かった。
人助けをしたのだ。今日はいい事があるかも知れない。
余談だが、この先で何をするのと問われ、キャンプですと答えたら、一人でキャンプとは寂しいね、と言われた。
普通の人から見たらそうなのだ。
ソロキャンプしていると、あまり人に言わない方がいいのかも知れない。
さて、車を止めて、いつもの様にパンツ一丁になって下半身を装備し直し、ザックを背負い、いざ進もう。
1ヶ月前に比べると、随分と緑色の風景になった。
今はいいが、夏になって鬱蒼と草や葉が覆うようになったら、こうやってキャンプしようとするのは難しくなるのだろうか。夏に向かって、キャンプのシーズンとなり、キャンプ場にも行きにくくなる。これは私が他の人の目を気にするからであろうけれど。今後どうやってキャンプして遊ぼうか、等と考えながら歩いた。

前々回キャンプした場所を横目に進む。
ここは砂利で平坦だからキャンプしやすかった。ただ、夏場のスコールのような夕立が来たら増水して非常に危険だと思う。

ここは前々回、増水で横断を諦めた場所だ。
どうやら増水も落ち着いてきたようだ。増水が落ち着いて来たという事は、渓流釣りのシーズンインという事か。
しかし、蔵王連峰はまだ雪化粧のままである。まだ当分、雪解け水は続くのだろう。

心細い橋を超え、倒木ポイントを迂回して進む。
前回は全く来た事のない場所だった為、緊張しながら進んだが、今回は2回目という事もあってグイグイ進めた。


ここだ。
前回、雪が迫り出していて、更にその下が空洞状になっており、危険を感じて進むを断念した場所だ。
何と雪がまだ残っている。
これは・・・雪があった場所の下が崩れたようになっている。前回、雪の上を歩いて無理をして渡っていたら雪が崩れて、崖下に落ちていたかも知れない。断念した判断は正しかったのだ。


さて、この先を少し進むと最終目的地が見えてくる筈だ。
見えた!一番奥の砂防ダムだ!
コイツを目指して3回もチャレンジして、ようやく辿りついたのだ。3度目の正直とは良く言ったものだ。
ん?人影が見える。
釣り人が砂防ダムの下で釣りをしている!
私が3回目にしてようよう辿りついた場所で、釣り人が釣りをしているのである。何とも喜び半減だ。
釣り人に、こんにちは、釣れますか、と話しかける。
釣り人は、先行者が居たので自分は2番目で、先行者は大きなのを釣って持ち帰ったようだよ、という事だった。
私は3番目という事か。
自己擁護するならば、前々回は増水に阻まれ、前回は雪に阻まれたのだから、人に負けたのではなく、自然に負けたのだ。ふん!
キャンプをしてはトラブルばかり、目的地を目指して3回チャレンジして歩いても今日だけで3番手である。私は一体何なのであろうか。まぁ、これも私らしくていいのではないだろうか。

それはそうと、これを目指してきたのだ。
別に砂防ダムマニアでも何でもないが、3回目にして辿り着けたのだから感慨もひとしおである。
私は目的を達成したのだ。
それにしてもデカイ。一番奥にして、一番デカイ。
この奥へ、これまで辿ってきた道を使って資材を運んで、これを作ったのだ。
良く見ると、所々ボロボロである。出来てどのくらいなのだろう。竣工の年月日を示すものがあるか探したが、見つからなかった。



よし、キャンプだ。ソロキャンプだ。
運がいいのか、この砂防ダムの上に、テントを張れそうなスペースが見つかった。
ザックを下ろすと、ほっとする。やはり重かった。防寒具類とスニーカをどうにかしないと荷物は減らない。

テントを張る前に、目の前の渓流でビールを冷やそう。
流れていかないように、石で固定する。
ああ、私の体は今、水分を欲している。これを我慢して、キャンプの準備をしてからビールを飲むのだ。

テントの設営は随分慣れた。
手早くやれば5分程度で終わる。
この手早くやれば短時間で済むのも山岳テントの利点だ。

そして焚き火の準備だ。
一人用の小さな竈を作り、薪拾いをする。
やはり渓流沿いは流木が多くて薪拾いが楽だし、何より乾いていて燃えやすい良質の薪なのだ。


いつもの様に、ガムテープを着火剤に使用して焚き火に火を付ける。
それにしても流木は良く燃える。
これでビールが飲める。
乾杯前の儀式、山の神様、川の神様、竈の神様に少しビールをおすそ分けする。
乾杯!ングングング・・・美味い!
川の水で冷やすというのは、何とも清涼感があって良い。しかもこのまま飲めそうな位に綺麗な水だ。ナントカの天然水とか言うのよりも、こっちの水の方が綺麗なのではないだろうか。

今日のキャンプはこの様な場所に陣取った。
ビールでひと心地ついたし、夕食でも食べよう。
ジップロックに刻んだ野菜や肉を入れて持ってきた。これを鍋にする。味付けは鍋キューブだ。
これは以前やって、結構美味かったのだ。



それにしても、日が長くなった。
鍋を食べ、ビール1本を空け、ほろ酔い状態である。周辺に山菜がないか、少し散歩をしよう。






く、熊だ。
この木は、テントを張った場所から20mと離れていない。
この爪あとはそんなに時間が経ったものではない。剥いだ後が生々しい。どうみてもここ1週間から数日といった所だ。
戦慄した。血の気が引いた。動悸が激しくなり、頭が混乱した。
正直言うと、ナメていた。川崎町の里山なんかで熊なんか居ないと思っていた。
この場所に来るまで、熊の痕跡がないかずっと見てきて、何も無かったから安心し切っていた。
この場所に到着しても、周囲に熊棚がないかも確認したのだ。熊棚も無かったのだ。
これは熊剥ぎというものだという。
この動画の熊の力、恐ろしい。
http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/research/results/20130917.html
もう酒も飲んでしまったし、もう6時だ。どう考えても帰る事は出来ない。
ラジオをガンガンに鳴らし、焚き火をこれでもかと燃やし、ここに泊まるしかない。
もしここで熊に襲われでもすれば、今日の様なこんな所まで来る奇特な釣り人が来ない限り、発見しては貰えないのだ。
本当に怖い。
焚き火の前に戻り、ラジオをガンガンに鳴らす。
時々、熊鈴もチリーンと鳴らす。
頭の中には熊しか居なかった。
いつの間にかラジオがブーーーンという低い音しかしなくなった。
げぇーーーっ!!電池が切れている!!
何でこの時に限って電池が切れるのだ。
人助けして、いい事があるのではなかったのか。
こんな不安な夜をどうして越せばよいのか。
テントに入ってはみたものの、外を熊がうろつく妄想が頭を悩ませる。
今は、突撃!お前が晩御飯!が全く笑えない。
熊は夜には行動しない。早朝と夕方だと解っている。それでも怖いのだ。
シュラフを頭からかぶり、じっとしていたらいつの間にか寝ていた。

朝5時に目が覚めた。
のんびりはして居たくない。
熊の行動時間だろうとも帰りたいのだ。
マッハで撤収し、急いで戻った。
5月6日~7日学んだ事:
・人を助けてもいい事があるとは限らない
・熊の痕跡が突然出ることもある