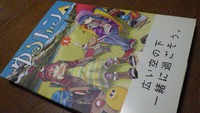2015年06月02日
レビュー:味の素 アミノバイタル
味の素から販売されているアミノバイタルをレビューします。
レビュー内容は、山歩き、登山においてアミノバイタルを活用するとどんな変化があり、有用だったかについて述べたいと思います。
あくまで個人的感覚なので、そこだけ注意して下さい。

購入経緯です。
私は山歩きをしていると、行動食を余り食べない傾向にあります。休憩を余りとらないという事もありますが、行動食を食べるのが面倒だったり、食べた後の腹の感覚が余り好きでないという事もあります。自業自得なのですが、その結果、バテ気味になる事もあります。一度、フラフラにバテた経験があり、それ以来は意識して行動食を食べるようにしたり、休憩するようにはしています。
行動食として必要な栄養素は、糖質、タンパク質、脂質だそうですが、糖質と脂質は割りと摂取しやすいとしても、タンパク質は摂取しにくいです。そして、タンパク質がアミノ酸となって体で使われるには、食事後3~4時間もかかるそうなので、行動食に干し肉などを持って行っても非効率という事になります。
アミノ酸ならば、栄養補助食品として様々なものが売られていますが、その中でも名前が売れているのが味の素のアミノバイタルです。
アミノバイタルは飲んだ後、20分程度で吸収されて効果が現れるそうなので、タンパク質の行動食を摂るのと違い、即効性があります。運動の前中後に飲むと良いと評判の良いようです。ネットでアミノバイタルプロを購入して試してみる事にしました。
手元に届きました。箱を開けてみると、小さな袋が入っています。私の購入したのは、お試しのつもりだったので、14袋入りのもので1700円でした。1袋当たり約120円です。
正直な所、こんなモンで違いがあんのかよ、という猜疑心でいっぱいでした。ザックの雨蓋に入れている行動食のスタッフザックに4袋放り入れ、総距離35kmの山行で出かけてみました。

この日は体調が良くないのか、荷物が重すぎるのか、妙に調子が上がらない日で、歩き始めて1時間半で帰りたくなる山でした。最初の休憩ではチョコやクッキーを食べてみましたが、調子は依然として変わりませんでした。
2回目の休憩で、アミノバイタルプロを試してみる事にしました。
小袋を取り出し口を切ると、中にはやや黄色い顆粒が入っています。口にサラサラと含んでみると、最初は美味しいかなとも思いましたが、味の奥の方に苦味がある為、味わって飲むというよりは、水で流し込んだ方が良さそうです。
問題は、飲んだ後にどんな効果が得られるかという事です。
アミノバイタルプロを飲んだ20分後、体を覆いそうになっていた倦怠感や疲労感が改善され、体の調子が良い時に山歩きの有酸素運動状態になっている時の様な、心地よい運動感になりました。その後も順調に歩く事が出来、およそ1時間半程度はこの状態を維持出来たように感じます。
1日3袋程度と箱に書いてあるので、摂り過ぎは良くないのかも知れませんが、ここぞという時にこれを飲めば、山で大いに役に立ってくれる事が実証されたと思います。私自身、こんな小袋を飲んだだけで大して変わらないだろうと疑っていました。しかし、まさかここまでとは思いませんでした。
今後もこれを行動食の補助として持って行くかと聞かれたならば、間違い無く持って行くと答えるでしょう。

私が飲んだのは、アミノバイタルプロで、これの1袋には3600mgのアミノ酸が含まれているといます。更にその上があって、アミノバイタルGOLDというのがあり、これの1袋には4000mgのアミノ酸だそうです。他にも色々とアミノバイタルシリーズがあるようですが、値段の手軽さと効果を考えるとアミノバイタルプロがバランスが良くて良いのではないかと思います。
山の行動食の補助としてのアミノバイタル、かなりオススメです!
レビュー内容は、山歩き、登山においてアミノバイタルを活用するとどんな変化があり、有用だったかについて述べたいと思います。
あくまで個人的感覚なので、そこだけ注意して下さい。

購入経緯です。
私は山歩きをしていると、行動食を余り食べない傾向にあります。休憩を余りとらないという事もありますが、行動食を食べるのが面倒だったり、食べた後の腹の感覚が余り好きでないという事もあります。自業自得なのですが、その結果、バテ気味になる事もあります。一度、フラフラにバテた経験があり、それ以来は意識して行動食を食べるようにしたり、休憩するようにはしています。
行動食として必要な栄養素は、糖質、タンパク質、脂質だそうですが、糖質と脂質は割りと摂取しやすいとしても、タンパク質は摂取しにくいです。そして、タンパク質がアミノ酸となって体で使われるには、食事後3~4時間もかかるそうなので、行動食に干し肉などを持って行っても非効率という事になります。
アミノ酸ならば、栄養補助食品として様々なものが売られていますが、その中でも名前が売れているのが味の素のアミノバイタルです。
アミノバイタルは飲んだ後、20分程度で吸収されて効果が現れるそうなので、タンパク質の行動食を摂るのと違い、即効性があります。運動の前中後に飲むと良いと評判の良いようです。ネットでアミノバイタルプロを購入して試してみる事にしました。
手元に届きました。箱を開けてみると、小さな袋が入っています。私の購入したのは、お試しのつもりだったので、14袋入りのもので1700円でした。1袋当たり約120円です。
正直な所、こんなモンで違いがあんのかよ、という猜疑心でいっぱいでした。ザックの雨蓋に入れている行動食のスタッフザックに4袋放り入れ、総距離35kmの山行で出かけてみました。

この日は体調が良くないのか、荷物が重すぎるのか、妙に調子が上がらない日で、歩き始めて1時間半で帰りたくなる山でした。最初の休憩ではチョコやクッキーを食べてみましたが、調子は依然として変わりませんでした。
2回目の休憩で、アミノバイタルプロを試してみる事にしました。
小袋を取り出し口を切ると、中にはやや黄色い顆粒が入っています。口にサラサラと含んでみると、最初は美味しいかなとも思いましたが、味の奥の方に苦味がある為、味わって飲むというよりは、水で流し込んだ方が良さそうです。
問題は、飲んだ後にどんな効果が得られるかという事です。
アミノバイタルプロを飲んだ20分後、体を覆いそうになっていた倦怠感や疲労感が改善され、体の調子が良い時に山歩きの有酸素運動状態になっている時の様な、心地よい運動感になりました。その後も順調に歩く事が出来、およそ1時間半程度はこの状態を維持出来たように感じます。
1日3袋程度と箱に書いてあるので、摂り過ぎは良くないのかも知れませんが、ここぞという時にこれを飲めば、山で大いに役に立ってくれる事が実証されたと思います。私自身、こんな小袋を飲んだだけで大して変わらないだろうと疑っていました。しかし、まさかここまでとは思いませんでした。
今後もこれを行動食の補助として持って行くかと聞かれたならば、間違い無く持って行くと答えるでしょう。

私が飲んだのは、アミノバイタルプロで、これの1袋には3600mgのアミノ酸が含まれているといます。更にその上があって、アミノバイタルGOLDというのがあり、これの1袋には4000mgのアミノ酸だそうです。他にも色々とアミノバイタルシリーズがあるようですが、値段の手軽さと効果を考えるとアミノバイタルプロがバランスが良くて良いのではないかと思います。
山の行動食の補助としてのアミノバイタル、かなりオススメです!
タグ :レビュー
2015年05月26日
山歩き 船形山~泉ヶ岳 テント泊縦走 20150523 その2
その1からのつづき。
トラブルで時間をロスしてしまってはいるが、休憩を取らない訳にはいかない。自分の体力が無いのは解っているので、無理に行動しても、後がもっとつらくなるだけだ。
三峰山の稜線上、ザックをどっかと下ろし、潅木に腰かけて休憩する。汗ばんだ肌に風が気持ち良い。
アミノバイタルプロを水で胃に流し込む。本日3本目であり、最早アミノバイタルジャンキーである。へっへ、こいつを一本打てば元気が出てくるってもんよ。

三峰山山頂だ。
本日最後の山頂なので、ちょっとした達成感がある。そしてここまで来ると、今日はほぼ下りのみになる。ひ弱な肉体が、もはやこれまでと悲鳴を上げているが、後はダラダラ歩きなので、極端なキツさはないだろう。


三峰山を下る前に、最終目的地の泉ヶ岳と北泉ヶ岳を見る。ここから先は長い長い林間歩きになり、展望は得られない。
あんなに遠くに見える山に、自分の足で向かうのだから、自分も大したものだと少し思う。

三峰山から長倉尾根を歩き、水源というテント場に到着するまでは2時間かかる。この時は、景色の変化の乏しい林間歩きで、さぞつまらない思いをするだろうと考えていた。
三峰山から長倉尾根に向かって下りていくと、残雪だらけの様子だった。船形山から三峰山にかけての稜線上では、雪を踏む場所は一切無かったのに、ここに来て残雪だらけなのだ。林間で日陰だから残雪が多いのだろうか。
当然ながら、雪があると登山道が隠れてしまう。冬に自分で道なき道をルートファインディングしながら進んだが、まさかここでやる事になるとは思ってもみなかった。

地図とGPSで位置と方向を確認して進む。残雪に隠されて、本来の登山道がどこにあるかは解らない。残雪が切れて、藪になった。周囲に登山道は見当たらない。GPSを確認して登山道と交わるように方向どりをして進んでみるものの、登山道にぶつからない。登山道を探しながら藪漕ぎを続けていると、再び残雪の場所に出る。残雪を抜けると藪漕ぎ・・・これを繰り返した。
はっきり言って、精神状態は最悪だ。登山道を探しつつ先に進んでいるのに、一向に登山道に出ないのだ。当然イライラもする。ラジオから聞こえてくる小娘のクソみたいな歌がイライラを加速させる。GPS上では登山道の上を歩いている事になっているのに、やっている事は藪漕ぎという矛盾に腹が立つ。
方向だけは合っている、登山道と平行して進んでいる、それだけが精神を安定させる材料だった。歩いていれば、必ず登山道に交わる筈だと。

登山道に出る事が出来た。今考えると、きちんと進んでいたのだから何も不安になる必要はないのだが、登山道でない場所を進むというのを覚悟していなかっただけに、少し心が乱れてしまった。
この時ばかりは、GPSを持ってきて良かったと感じた。コンパスも持ってきているので、これでも登山道への復帰は出来ただろうが、やはりGPSの便利さには適わない。一人で歩く人ほど、不測の事態の為にGPSは持った方が安心だと思う。

残雪歩きと藪漕ぎでも結構距離を稼げていたらしく、思ったよりも早くテント場の水源に到着した。トレッキングポールの置き忘れ、雪渓でのルート誤り、長倉尾根でのルートロスまがい、とトラブル続きだったにも関わらず、30分から1時間程度の遅れで収まってくれた。
でも、肉体的にも精神的にも、今日はクタクタだ。早く休みたい。

素早くテントを設営したい所だが、ノロノロ動きでテントを建てた。
風もないし、四つ角の張り網は不要だろう。

外はブヨの大群でのんびり出来ないので、テントの中に引き篭もる事にする。煮炊きも一人宴会もテントの中だ。
私のテントはアライテントのエアライズ1なので中は狭いが、一人で煮炊きする程度は可能だ。
あー、焚き火してぇ。

調理を始めようと、コッヘルを取り出す。コッヘルの中にスタックされているガスとストーブを取り出すと、ガスをストーブへ接続する部分が錆びている。
キャンプで焚き火で調理ばかりしている所為か、ストーブは全く使っていなかった。キャンプには念の為にと、ガスもストーブも持っていっているが、取り出さないので、サビている事に気が付かなかった。装備は出発前に点検すべきだった。
まぁ、ガスは普通に燃焼してくれるので、このまま使う事にしよう。疲れているから、小さな事は気にしない。

食事はいつもと代わり映えしないが、鍋キューブの鍋と、それを食べきった後、サトウのご飯で雑炊だ。
生野菜と肉を持ち込んで、重いだけだと思われるが、私は新鮮な野菜を食べたいのだからいいのだ。多少重くても運ぶ。疲れている時にカップラーメンを食べても元気がでないのだから、そういう事だ。
ただ、締めの雑炊にサトウのご飯は重くて失敗した。次回から雑炊をする時は、アルファ米にしよう。

夜、ビールを飲んでまどろんでいると、外から何の鳴き声だか解らないが、しきりに会話するような動物の鳴き声が聞こえる。声に太さがあるので、大きい動物ではないかと思う。カモシカとかだろうか。
久しぶりに自然の中に、テントの布一枚で隔たれた空間で過ごすと、自然の近さを感じる。オシッコをしたくなって外に出ようと思っても、結構勇気が要る。何が怖いという訳ではないのだけれど、光のあるテントの中から、真っ暗な外に出るのを躊躇する。暗闇が怖いという、原始的な恐ろしさ。

朝5時半起床。
朝食を簡単に済ませ、出発の準備をする。
今日の分の飲み水のストックはない。自然の水を利用するしかない。
プラティパス2を片手に、水場へと向かう。ちょろちょろの水の流れの、水の溜まった場所からプラティパスに汲み入れる。とても冷たい水だ。
地図上に記載されている水場の水は、そのまま飲んでも構わない、という言葉を信じて、ハイドレーションシステムにそのまま補給する。
飲んでみると、柔らかで非常に美味しい水だった。


出発の前にまだやる事がある。
この水源という場所の周辺は、コシアブラが沢山生えているのだ。昨日の夕方から摘みたくて仕方が無かった。しっかり採取していこう。

さあ出発だ。
2日目は、ゆったりの行程だ。北泉ヶ岳、三叉路、泉ヶ岳、下山、というゆっくり歩いても4時間のコースだ。靴擦れも痛むし、筋肉痛だし、ちんたら歩く事にしよう。
1時間ほど歩くと、北泉ヶ岳の山頂に到着した。
虫が凄い。猛烈な勢いでアタックしてくる。早朝だからブヨも活発なのだ。


三叉路。泉ヶ岳方面と水神への分かれ道だ。
足が痛いので下りたい気持ちが出てしまうが、ここで泉ヶ岳に登らないと昨日からの山旅が台無しになってしまうので、頑張ろう。

泉ヶ岳山頂手前で、視界が開ける。2日かけて歩いてきた山が遠くに見える。
感慨深い。順調な山よりは、今回の様に多少のトラブルがあった方が思い入れが強くなるのだろうか。

泉ヶ岳山頂。人が多い。船形山からここまで、殆ど人に出会わなかったが、人に会えて嬉しい気持ちは特に湧いて来ない。私は一人が好きなのだと再認識する。
泉ヶ岳で、このサイズのザックを背負っていると目立つ。デカいザックを背負って格好付けているんじゃない、というような視線を感じる・・・と、勝手に思い込んでしまう。高尾山でガチ装備をしていると蔑まれるような、そんな感じ。私の勝手な妄想。


人に会いたくないのと、林間歩きは飽きたので、下りはカモシカコースを選択した。
カモシカコースは、岡沼と兎平という開けた場所を経由するルートなので、泉ヶ岳の違った一面を楽しめるのだ。そして、傾斜がキツいコースなので、人も少ない。
傾斜がキツいので下りは足に堪えるが、岡沼と兎平を歩く気持ち良さは格別だった。

兎平を超えると、泉ヶ岳スキー場のゲレンデに出る。目の前に仙台平野が海まで見渡せる。
山旅が終わってしまうのが残念で、下りきってしまうのが少し勿体無かった。

トラブルで時間をロスしてしまってはいるが、休憩を取らない訳にはいかない。自分の体力が無いのは解っているので、無理に行動しても、後がもっとつらくなるだけだ。
三峰山の稜線上、ザックをどっかと下ろし、潅木に腰かけて休憩する。汗ばんだ肌に風が気持ち良い。
アミノバイタルプロを水で胃に流し込む。本日3本目であり、最早アミノバイタルジャンキーである。へっへ、こいつを一本打てば元気が出てくるってもんよ。

三峰山山頂だ。
本日最後の山頂なので、ちょっとした達成感がある。そしてここまで来ると、今日はほぼ下りのみになる。ひ弱な肉体が、もはやこれまでと悲鳴を上げているが、後はダラダラ歩きなので、極端なキツさはないだろう。


三峰山を下る前に、最終目的地の泉ヶ岳と北泉ヶ岳を見る。ここから先は長い長い林間歩きになり、展望は得られない。
あんなに遠くに見える山に、自分の足で向かうのだから、自分も大したものだと少し思う。

三峰山から長倉尾根を歩き、水源というテント場に到着するまでは2時間かかる。この時は、景色の変化の乏しい林間歩きで、さぞつまらない思いをするだろうと考えていた。
三峰山から長倉尾根に向かって下りていくと、残雪だらけの様子だった。船形山から三峰山にかけての稜線上では、雪を踏む場所は一切無かったのに、ここに来て残雪だらけなのだ。林間で日陰だから残雪が多いのだろうか。
当然ながら、雪があると登山道が隠れてしまう。冬に自分で道なき道をルートファインディングしながら進んだが、まさかここでやる事になるとは思ってもみなかった。

地図とGPSで位置と方向を確認して進む。残雪に隠されて、本来の登山道がどこにあるかは解らない。残雪が切れて、藪になった。周囲に登山道は見当たらない。GPSを確認して登山道と交わるように方向どりをして進んでみるものの、登山道にぶつからない。登山道を探しながら藪漕ぎを続けていると、再び残雪の場所に出る。残雪を抜けると藪漕ぎ・・・これを繰り返した。
はっきり言って、精神状態は最悪だ。登山道を探しつつ先に進んでいるのに、一向に登山道に出ないのだ。当然イライラもする。ラジオから聞こえてくる小娘のクソみたいな歌がイライラを加速させる。GPS上では登山道の上を歩いている事になっているのに、やっている事は藪漕ぎという矛盾に腹が立つ。
方向だけは合っている、登山道と平行して進んでいる、それだけが精神を安定させる材料だった。歩いていれば、必ず登山道に交わる筈だと。

登山道に出る事が出来た。今考えると、きちんと進んでいたのだから何も不安になる必要はないのだが、登山道でない場所を進むというのを覚悟していなかっただけに、少し心が乱れてしまった。
この時ばかりは、GPSを持ってきて良かったと感じた。コンパスも持ってきているので、これでも登山道への復帰は出来ただろうが、やはりGPSの便利さには適わない。一人で歩く人ほど、不測の事態の為にGPSは持った方が安心だと思う。

残雪歩きと藪漕ぎでも結構距離を稼げていたらしく、思ったよりも早くテント場の水源に到着した。トレッキングポールの置き忘れ、雪渓でのルート誤り、長倉尾根でのルートロスまがい、とトラブル続きだったにも関わらず、30分から1時間程度の遅れで収まってくれた。
でも、肉体的にも精神的にも、今日はクタクタだ。早く休みたい。

素早くテントを設営したい所だが、ノロノロ動きでテントを建てた。
風もないし、四つ角の張り網は不要だろう。

外はブヨの大群でのんびり出来ないので、テントの中に引き篭もる事にする。煮炊きも一人宴会もテントの中だ。
私のテントはアライテントのエアライズ1なので中は狭いが、一人で煮炊きする程度は可能だ。
あー、焚き火してぇ。

調理を始めようと、コッヘルを取り出す。コッヘルの中にスタックされているガスとストーブを取り出すと、ガスをストーブへ接続する部分が錆びている。
キャンプで焚き火で調理ばかりしている所為か、ストーブは全く使っていなかった。キャンプには念の為にと、ガスもストーブも持っていっているが、取り出さないので、サビている事に気が付かなかった。装備は出発前に点検すべきだった。
まぁ、ガスは普通に燃焼してくれるので、このまま使う事にしよう。疲れているから、小さな事は気にしない。

食事はいつもと代わり映えしないが、鍋キューブの鍋と、それを食べきった後、サトウのご飯で雑炊だ。
生野菜と肉を持ち込んで、重いだけだと思われるが、私は新鮮な野菜を食べたいのだからいいのだ。多少重くても運ぶ。疲れている時にカップラーメンを食べても元気がでないのだから、そういう事だ。
ただ、締めの雑炊にサトウのご飯は重くて失敗した。次回から雑炊をする時は、アルファ米にしよう。

夜、ビールを飲んでまどろんでいると、外から何の鳴き声だか解らないが、しきりに会話するような動物の鳴き声が聞こえる。声に太さがあるので、大きい動物ではないかと思う。カモシカとかだろうか。
久しぶりに自然の中に、テントの布一枚で隔たれた空間で過ごすと、自然の近さを感じる。オシッコをしたくなって外に出ようと思っても、結構勇気が要る。何が怖いという訳ではないのだけれど、光のあるテントの中から、真っ暗な外に出るのを躊躇する。暗闇が怖いという、原始的な恐ろしさ。

朝5時半起床。
朝食を簡単に済ませ、出発の準備をする。
今日の分の飲み水のストックはない。自然の水を利用するしかない。
プラティパス2を片手に、水場へと向かう。ちょろちょろの水の流れの、水の溜まった場所からプラティパスに汲み入れる。とても冷たい水だ。
地図上に記載されている水場の水は、そのまま飲んでも構わない、という言葉を信じて、ハイドレーションシステムにそのまま補給する。
飲んでみると、柔らかで非常に美味しい水だった。


出発の前にまだやる事がある。
この水源という場所の周辺は、コシアブラが沢山生えているのだ。昨日の夕方から摘みたくて仕方が無かった。しっかり採取していこう。

さあ出発だ。
2日目は、ゆったりの行程だ。北泉ヶ岳、三叉路、泉ヶ岳、下山、というゆっくり歩いても4時間のコースだ。靴擦れも痛むし、筋肉痛だし、ちんたら歩く事にしよう。
1時間ほど歩くと、北泉ヶ岳の山頂に到着した。
虫が凄い。猛烈な勢いでアタックしてくる。早朝だからブヨも活発なのだ。


三叉路。泉ヶ岳方面と水神への分かれ道だ。
足が痛いので下りたい気持ちが出てしまうが、ここで泉ヶ岳に登らないと昨日からの山旅が台無しになってしまうので、頑張ろう。

泉ヶ岳山頂手前で、視界が開ける。2日かけて歩いてきた山が遠くに見える。
感慨深い。順調な山よりは、今回の様に多少のトラブルがあった方が思い入れが強くなるのだろうか。

泉ヶ岳山頂。人が多い。船形山からここまで、殆ど人に出会わなかったが、人に会えて嬉しい気持ちは特に湧いて来ない。私は一人が好きなのだと再認識する。
泉ヶ岳で、このサイズのザックを背負っていると目立つ。デカいザックを背負って格好付けているんじゃない、というような視線を感じる・・・と、勝手に思い込んでしまう。高尾山でガチ装備をしていると蔑まれるような、そんな感じ。私の勝手な妄想。


人に会いたくないのと、林間歩きは飽きたので、下りはカモシカコースを選択した。
カモシカコースは、岡沼と兎平という開けた場所を経由するルートなので、泉ヶ岳の違った一面を楽しめるのだ。そして、傾斜がキツいコースなので、人も少ない。
傾斜がキツいので下りは足に堪えるが、岡沼と兎平を歩く気持ち良さは格別だった。

兎平を超えると、泉ヶ岳スキー場のゲレンデに出る。目の前に仙台平野が海まで見渡せる。
山旅が終わってしまうのが残念で、下りきってしまうのが少し勿体無かった。

タグ :山歩き
2015年05月25日
山歩き 船形山~泉ヶ岳 テント泊縦走 20150523 その1
キャンプからも、山からも随分と遠のいてしまっている。時間が無いと言ってしまえば確かにそうなのだが、何となくやる気が起きなかったのも確かだ。
ある理由があって、体力をつけねばならなくなったので、またロングコースの船形山から泉ヶ岳にかけての縦走テント泊をやってみよう。
この時持っていった物
服装
ザック内(グレゴリー アルピニスト50)
荷物を小さくまとめたかったので、ザックを新調した。グレゴリーのアルピニスト50だ。アルピニスト35を日帰り用として使っていて、これが非常に良かったので、50も購入した。私は背面長(トルソー)がサイズSなので、表記上50であっても、ザックの容量は44Lとなる。44Lで一部の冬装備を含めたテント泊装備をパッキングしなければならないので、今回はより効率的な装備選びが必要だった。
それでも、テント場でビールをどうしても飲みたいので、ビール2本はどうしても持ちたかった。いつもの事だが、ビール1L、ハイドレーションに2L、予備に2Lの水は、これだけで重かった。
ツボ足でもいけそうな気はする。しかしアイゼンとピッケルを持たない事で進退窮まる状況だけは避けたかった。雪渓登りがある筈なので、アイゼンは必要だ。ピッケルも必要そうではあるが、今回は装備から外した。その他、グローブ等の冬用装備がザックの容積を圧迫した。
いざパッキングを終えてみると、パンパンだが、全て詰め込む事が出来た。しかし、非常に重い。この重さに相当苦しめられる事になった。
実は、次週、北海道の芦別岳本谷コースを登る事になっている。この芦別岳本谷コースは、「岳人あこがれの」と枕詞が付く事もある、北海道屈指の難コースらしい。
そんな難コースに挑もうというのに、しばらく山から遠ざかっていたので、私の体力は落ちてしまっている。一人で挑む訳ではなくて、ガイドも付いているが、参加者は私の他にも数名居るので、私の体力の無さで迷惑がかかりかねない。
次週の山行に向けて、今更トレーニングしても微妙だというのは解っているが、悲惨な未来を手をこまねいて待つ訳にもいかない。
規模も性格も全く違う山だが、雪渓登りとロングコース、仮想芦別岳として頑張ってみよう。
うーむ、動機が不純だ。
それと、今年の山の目標として、一つ考えている事がある。
東北にはテント泊する山文化がない。指定のテント場がないからというのもある。しかし、ゲリラ的にテント泊山行しているのもポツポツと見かける。
「東北のテント泊」と銘打って、テント泊を目的とした山歩きをやりたい。アイデアを曝け出すのもアレだが、今、頭にあるのは2つの山だ。
一つ目は、宮城と山形の県境の笹谷峠から仙台神室方面、更に大東岳方面に向かい、樋ノ沢避難小屋前のスペースでテントを張りつつ焚き火して一泊、翌日大東岳を登り、二口へ抜けるか、面白岳方面へ抜ける、というコース。
二つ目は、岩手県の焼石岳だ。ルートは何でも良いのだが、銀明水の手前がテントを張るのに適しているらしいので、焼石岳に登ってそこで一泊したい。日帰りも出来るが、テントを張りたいのだ。
うーむ、これは夢があるぞ。
さて、自宅を6時に出発し、高速を使って現地へと向かう。高速を使うと早い。1時間後の7時に到着してしまった。前回が8時スタートだったので、今回は1時間余裕を持ってスタート出来る事になる。
今回のルートも、前回船形山から泉ヶ岳にかけて縦走したのと同じで、升沢コースで船形山に登り、その後、泉ヶ岳への縦走ルートに入った後、蛇ヶ岳と三峰山を登り、長い長い長長倉尾根を歩き、テント場の水源で一泊、翌日は北泉ヶ岳と泉ヶ岳を登り、下山して縦走完了となる。全長30kmのコースだ。
さあ行こう。
旗坂キャンプ場の入り口の可愛いフクロウに挨拶してスタートする。何も無ければ、15時頃にテント場の水源に到着出来る筈だ。

歩き始めて、何だか調子が上がらない。歩いていて疲れる。歩き始めの20分位はいつもキツいのだが、40分経っても未だにキツい。
何と言うか、ザックの重さに負けている感覚がする。アルピニスト50、背負いやすい事は背負いやすいのだが、前に使ったバルトロ65よりもウェストハーネスがしっかりしている訳ではないので、それに比べると腰よりも肩に加重がかかりやすいようだ。その違いに体がついて来ていないらしい。
それもそうだ。アルピニスト50はアルパインクライミング用のザックで、ウェストハーネスも外せたり、何と背中のフレームすら外せるようになっている。縦走向きのバルトロ65とは、基本的な考え方からして違うのだ。
それと、まだグレゴリーの公式サイトにも載っていない事だが、今回私が使っているアルピニスト50は、マイナーチェンジの入ったリニューアルバージョンだ。ロゴも新ロゴになっていて、デザインや機能に改良が加えられている。ネットにも一切そんな情報は出ていなかったので、私の山行が最速の使用リポートかも知れない。

足に違和感を感じる。プチッとした痛みを感じる。これは靴擦れだ。去年と同じ靴と靴下を履いているのに、まさか靴擦れになるとは。この先30kmも歩かねばならないのに、先が心配になる。
それに加えて、私の大嫌いなブヨ(ブユ)が大群となって纏わりついてくる。噛まれた後の苦痛を思い出し、大きな嫌悪感が湧いてくる。
一度ザックを下ろし、靴擦れの処置を行う。その後、ハッカ油を取り出し、体にシュッシュと吹きかける。爽やかなハッカの香りと共に、ブヨが霧散した。ハッカ油はこの時期の必須アイテムの様だ。

靴擦れの痛みとザックの重みと戦いながら、三光宮手前まで辿り着いた。
船形山の升沢コースは、1~30の番号がルート上に表示されている。30がスタートで、1が頂上だ。この三光宮は15なので、丁度中間地点だ。
三光宮は眺めが良いので、ここで休憩しようと足を向けたその時、恐ろしい事に気が付いた。
げぇーーっ!!トレッキングポールを手に持っていない!!
どうやら、先程靴擦れの手当てをした場所に置き忘れて来たらしい。靴擦れの手当てをした場所なんて、かなり前の場所だ。番号で言うと20の辺りだ。番号を5も戻らねばならないという事は、1/6の距離を往復(つまり1/3の距離)しなければならない事になる。しかし、これからの長い距離を考えると、取りに戻らない手はないだろう。
三光宮の手前にザックをデポし、空身で戻る事にする。目立つ位置のデポだが、人も少ないし、あんな重いザックなんて持って行こうとする人も居ないし大丈夫だろう。
ザックの重さから開放され、体が軽い。すいすいと進むが、体力を使わない訳ではない。この先は長いのに、こんな所で体力を無駄遣いする自分が情けない。溜息ばかり出る。
ポールが見つかった。やっぱり20の番号の辺りだった。往復で40分のロスといった所か。

三光宮に戻る際、コシアブラが生えているのを見つける。実に良い育ち具合だ。
私は転んでもタダでは起きないのだ。ウシシと笑って、コシアブラを採取した。

ようやくザックのデポ位置まで戻ってきた。
これだけ無駄な時間を使ってしまっては、三光宮でしようと思っていた休憩も中止とせねばならない。風景だけ写真に撮り、先に進む事にする。

残雪が多くなって来た。一面が残雪で覆われている場所もあり、ルートが解り難くなっている。
有難い事に、赤布がルート上にあるので、それを目印に進む事が出来る。雪のシーズンはルートロスが恐ろしい。

升沢避難小屋までやってきた。
予定時刻より遅れてはいるが、休憩無しという訳にもいかない。小屋で休憩させて貰う事にする。
ザックを下ろし、握り飯を頬張る。美味い。実は腹が鳴っていたのだ。本当は握り飯の友にカップラーメンや熱いお茶を飲みたい所だが、荷物を減らす関係上、テルモスもカップ麺も持って来ていない。握り飯の友は、ハイドレーションの水となった。チューチュー。
行動食もここぞとばかりに食べる。チョコ、マルセイのバターサンド、アミノバイタルプロ。
このアミノバイタルプロ、効き目が素晴らしい。摂取してから30分後の体の活力が違う。ここぞと言う時のドーピングに持って来いの行動食だ。

それはそうと、下の写真のリニューアルされたアルピニスト50、こんな違いがある。
一番の違いは、ザック下部のピッケル用のループ(ピッケルホルダー)が新たに付いた事だ。これまでのアルピニストシリーズは、独特のピッケル装着システムになっていて、ピッケルのヘッドの穴に金具を通して固定するという仕組みだった。しかし、ピッケルのヘッドの穴が小さいグリベルのピッケル等を装着する事が出来ないというデメリットがあった。これの評判が悪かった為、一般的なループ型のホルダーも付けたのだと思われる。これは非常に良い改善だ。
その他、デザインも少し変化があった。これまでは雨蓋の縁は濃い金色の生地で縁取られていたが、リニューアル後はそれが無くなった。私は前のデザインの方が好きだった。気の所為か、雨蓋が小さくなった様に感じるが、デザインの違いであって、きっと容量の差異はないだろう。

小屋を出て、直ぐ脇の沢を進む。雪渓になっている為、沢の中の石を慎重に渡っていく必要はなく、ぐんぐん高度を稼げる。
アイゼンを履き、ザクザクと雪を踏みながら進んでいく。思ったよりも、アイゼンの重さが足に来る。冬靴だった時は、靴自体も重い所為か、アイゼンを履いても大して重さを感じなかったのに、この夏靴では一歩一歩が重く感じる。
またしても失敗した事に気付く。トレースを辿って進んだ所、そのルートに誤りがあり、正規ルートの隣の沢筋へ入ってしまっていた。正規のルートに戻るが、また時間をロスしてしまった。
トラブルというのは、重なる時は重なる。何でだろうか。

正規のルートは踏み跡も多く、それを利用させて貰う。ステップをそのまま利用出来るので、楽だ。
この雪渓、大して斜度が無いからいいものの、安全の為ならピッケルも持った方が良かったかも知れない。先行者がアイゼン無しで登って行くが、安全に不安は感じないのだろうか。私が心配性なだけかも知れない。

雪渓を超えた先で目の前が一気に開けた。これから歩く先が見渡せる。
中心の右側の山が蛇ヶ岳、中心のピークが3つ並んだ山が三峰山、その遥か奥にポコッと並んだ山が北泉ヶ岳と泉ヶ岳だ。余りにも遠くて少しゲンナリしつつも、頑張るぞ、という気持ちにもなる。

船形山山頂は立ち寄って直ぐ下るので、重いザックを担ぎ上げる必要はない。泉ヶ岳への分岐点にデポし、山頂へ向かう。
空身の身軽さよ。

あっという間に頂上だ。
風が強い所為か、人が少ない。否、山開き前だからだ。これまでに3名としかすれ違っていない。人が少なすぎるのは、そういう事か。
逆に考えよう。この週末が山開きと重なって人でごった返さなくてよかった、と。私は静かな山の方が好きだ。


分岐点に戻り、泉ヶ岳方面へ向かう。

目指す先が見えるというのは、気持ちが良い。林間歩きは飽きた所だった。背丈より高い木もまだまだあるが、稜線を歩きながらチラチラ見える風景の変化がとても面白い。

蛇ヶ岳山頂だ。
靴擦れが悪化している。片足だったものが、両足になってしまった。休憩を兼ねて、ザックを下ろし、靴を脱いで患部を見る。靴下が湿っている。水溜りや沢をジャブジャブ進んだ所為か、中の湿気が外に逃げなかったのだろう。それによって内部の摩擦が強くなり、靴擦れが悪化したのだと思われる。バンソウコウを張りなおし、処置を行った。それでもヒリヒリする。
靴下を脱いだ足が風に当たると気持ちが良い。今日は仙台では、31度Cを越える気温になったのだという。山の上でも結構な気温だが、風のおかげで気持ちが良い。


この船形連峰はコシアブラが非常に多い。稜線上にも立派なコシアブラの木が沢山ある。
荷物は増やしたくなくとも、スーパー山菜人の血が騒いで採取せずには居られない。ああ、何でこんなに立派なんだ。何でこんなに沢山取れるんだ。何でこれを取りきれずに見逃して歩かねばならないのか。この採ったコシアブラをあげるから、私にもっと採らせてくれ!


蛇ヶ岳を超え、三峰山を目指す。
三峰山周辺は藪が非常に濃い。そして熊も多いらしい。突然出会うのだけは避けねばならないので、ラジオを大き目の音で鳴らし、進む事にする。
この濃い藪が苦痛だ。

濃い藪を越えると、視界が開ける。
船形山から泉ヶ岳への縦走ルートでは、この三峰山頂上付近の辺りが一番好きだ。背より高い木がないので見晴らしは良いし、縦走的な雰囲気が楽しめるからだ。
仙台で真夏日になったように、山も暑い。ハイドレーションの水を2L準備したからと景気良くチューチュー吸いまくっていた所、三峰山山頂を待たずに2Lを飲み切ってしまった。ハイドレーションはこまめに水分補給出来るという非常に大きなメリットがある一方、どれだけ飲んだか解らないというデメリットもある。
そして、飲みきった後の補給のしにくさだ。ザックから取り出して、水を補給して、ザックに戻すとなると、ザックの中身の殆どを取り出してパッキングし直さねばならなくなる。これが余りにも面倒なのだ。
プラティパスに予備の水が入っているので、休憩の時に一気にがぶ飲みして水分補給する事にしよう。

つづく。
ある理由があって、体力をつけねばならなくなったので、またロングコースの船形山から泉ヶ岳にかけての縦走テント泊をやってみよう。
この時持っていった物
服装
| 服装 | 薄手のフリース、パンツ、トレッキングシューズ |
ザック内(グレゴリー アルピニスト50)
| テント | アライテント エアライズ1、グラウンドシート |
| マット | モンベル U.L.コンフォートシステム パッド150 |
| シュラフ | モンベル スパイラルダウンハガー #3、エアピロー |
| クッカー類 | スノーピーク トレック900、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ、スポーク、割り箸 |
| 食料 | 握り飯2個、鍋の材料(ジップロック)、サトウのご飯、ビール2本、スキットル入りウイスキー、水(プラティパスビッグジップSL 2000ml入)、予備の水(プラティパス2 2000ml入)、行動食(アミノバイタルプロ、グラノーラ、チョコクッキー、チョコバー)、非常食(アルファ米2個) |
| 雨具 | ザ・ノースフェイス レインテックス FLIGHT M |
| 冬装備 | ブラックダイヤモンド セラックストラップ |
| 予備 | モンベル トレールアクショングローブ、ブラックダイヤモンド アーク、靴下 |
| 地図 | GARMIN eTrex30(GPS)、地図、コンパス |
| 服 | ダウンジャケット、ダウンパンツ、スパッツ |
| その他 | ラジオ、ナイフ、ヘッドライト、LEDランタン、熊鈴、ファーストエイドキット、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、コンパクトデジカメ、ウェアラブルカメラ、トレッキングポール、文庫本 |
荷物を小さくまとめたかったので、ザックを新調した。グレゴリーのアルピニスト50だ。アルピニスト35を日帰り用として使っていて、これが非常に良かったので、50も購入した。私は背面長(トルソー)がサイズSなので、表記上50であっても、ザックの容量は44Lとなる。44Lで一部の冬装備を含めたテント泊装備をパッキングしなければならないので、今回はより効率的な装備選びが必要だった。
それでも、テント場でビールをどうしても飲みたいので、ビール2本はどうしても持ちたかった。いつもの事だが、ビール1L、ハイドレーションに2L、予備に2Lの水は、これだけで重かった。
ツボ足でもいけそうな気はする。しかしアイゼンとピッケルを持たない事で進退窮まる状況だけは避けたかった。雪渓登りがある筈なので、アイゼンは必要だ。ピッケルも必要そうではあるが、今回は装備から外した。その他、グローブ等の冬用装備がザックの容積を圧迫した。
いざパッキングを終えてみると、パンパンだが、全て詰め込む事が出来た。しかし、非常に重い。この重さに相当苦しめられる事になった。
実は、次週、北海道の芦別岳本谷コースを登る事になっている。この芦別岳本谷コースは、「岳人あこがれの」と枕詞が付く事もある、北海道屈指の難コースらしい。
そんな難コースに挑もうというのに、しばらく山から遠ざかっていたので、私の体力は落ちてしまっている。一人で挑む訳ではなくて、ガイドも付いているが、参加者は私の他にも数名居るので、私の体力の無さで迷惑がかかりかねない。
次週の山行に向けて、今更トレーニングしても微妙だというのは解っているが、悲惨な未来を手をこまねいて待つ訳にもいかない。
規模も性格も全く違う山だが、雪渓登りとロングコース、仮想芦別岳として頑張ってみよう。
うーむ、動機が不純だ。
それと、今年の山の目標として、一つ考えている事がある。
東北にはテント泊する山文化がない。指定のテント場がないからというのもある。しかし、ゲリラ的にテント泊山行しているのもポツポツと見かける。
「東北のテント泊」と銘打って、テント泊を目的とした山歩きをやりたい。アイデアを曝け出すのもアレだが、今、頭にあるのは2つの山だ。
一つ目は、宮城と山形の県境の笹谷峠から仙台神室方面、更に大東岳方面に向かい、樋ノ沢避難小屋前のスペースでテントを張りつつ焚き火して一泊、翌日大東岳を登り、二口へ抜けるか、面白岳方面へ抜ける、というコース。
二つ目は、岩手県の焼石岳だ。ルートは何でも良いのだが、銀明水の手前がテントを張るのに適しているらしいので、焼石岳に登ってそこで一泊したい。日帰りも出来るが、テントを張りたいのだ。
うーむ、これは夢があるぞ。
さて、自宅を6時に出発し、高速を使って現地へと向かう。高速を使うと早い。1時間後の7時に到着してしまった。前回が8時スタートだったので、今回は1時間余裕を持ってスタート出来る事になる。
今回のルートも、前回船形山から泉ヶ岳にかけて縦走したのと同じで、升沢コースで船形山に登り、その後、泉ヶ岳への縦走ルートに入った後、蛇ヶ岳と三峰山を登り、長い長い長長倉尾根を歩き、テント場の水源で一泊、翌日は北泉ヶ岳と泉ヶ岳を登り、下山して縦走完了となる。全長30kmのコースだ。
さあ行こう。
旗坂キャンプ場の入り口の可愛いフクロウに挨拶してスタートする。何も無ければ、15時頃にテント場の水源に到着出来る筈だ。

歩き始めて、何だか調子が上がらない。歩いていて疲れる。歩き始めの20分位はいつもキツいのだが、40分経っても未だにキツい。
何と言うか、ザックの重さに負けている感覚がする。アルピニスト50、背負いやすい事は背負いやすいのだが、前に使ったバルトロ65よりもウェストハーネスがしっかりしている訳ではないので、それに比べると腰よりも肩に加重がかかりやすいようだ。その違いに体がついて来ていないらしい。
それもそうだ。アルピニスト50はアルパインクライミング用のザックで、ウェストハーネスも外せたり、何と背中のフレームすら外せるようになっている。縦走向きのバルトロ65とは、基本的な考え方からして違うのだ。
それと、まだグレゴリーの公式サイトにも載っていない事だが、今回私が使っているアルピニスト50は、マイナーチェンジの入ったリニューアルバージョンだ。ロゴも新ロゴになっていて、デザインや機能に改良が加えられている。ネットにも一切そんな情報は出ていなかったので、私の山行が最速の使用リポートかも知れない。

足に違和感を感じる。プチッとした痛みを感じる。これは靴擦れだ。去年と同じ靴と靴下を履いているのに、まさか靴擦れになるとは。この先30kmも歩かねばならないのに、先が心配になる。
それに加えて、私の大嫌いなブヨ(ブユ)が大群となって纏わりついてくる。噛まれた後の苦痛を思い出し、大きな嫌悪感が湧いてくる。
一度ザックを下ろし、靴擦れの処置を行う。その後、ハッカ油を取り出し、体にシュッシュと吹きかける。爽やかなハッカの香りと共に、ブヨが霧散した。ハッカ油はこの時期の必須アイテムの様だ。

靴擦れの痛みとザックの重みと戦いながら、三光宮手前まで辿り着いた。
船形山の升沢コースは、1~30の番号がルート上に表示されている。30がスタートで、1が頂上だ。この三光宮は15なので、丁度中間地点だ。
三光宮は眺めが良いので、ここで休憩しようと足を向けたその時、恐ろしい事に気が付いた。
げぇーーっ!!トレッキングポールを手に持っていない!!
どうやら、先程靴擦れの手当てをした場所に置き忘れて来たらしい。靴擦れの手当てをした場所なんて、かなり前の場所だ。番号で言うと20の辺りだ。番号を5も戻らねばならないという事は、1/6の距離を往復(つまり1/3の距離)しなければならない事になる。しかし、これからの長い距離を考えると、取りに戻らない手はないだろう。
三光宮の手前にザックをデポし、空身で戻る事にする。目立つ位置のデポだが、人も少ないし、あんな重いザックなんて持って行こうとする人も居ないし大丈夫だろう。
ザックの重さから開放され、体が軽い。すいすいと進むが、体力を使わない訳ではない。この先は長いのに、こんな所で体力を無駄遣いする自分が情けない。溜息ばかり出る。
ポールが見つかった。やっぱり20の番号の辺りだった。往復で40分のロスといった所か。

三光宮に戻る際、コシアブラが生えているのを見つける。実に良い育ち具合だ。
私は転んでもタダでは起きないのだ。ウシシと笑って、コシアブラを採取した。

ようやくザックのデポ位置まで戻ってきた。
これだけ無駄な時間を使ってしまっては、三光宮でしようと思っていた休憩も中止とせねばならない。風景だけ写真に撮り、先に進む事にする。

残雪が多くなって来た。一面が残雪で覆われている場所もあり、ルートが解り難くなっている。
有難い事に、赤布がルート上にあるので、それを目印に進む事が出来る。雪のシーズンはルートロスが恐ろしい。

升沢避難小屋までやってきた。
予定時刻より遅れてはいるが、休憩無しという訳にもいかない。小屋で休憩させて貰う事にする。
ザックを下ろし、握り飯を頬張る。美味い。実は腹が鳴っていたのだ。本当は握り飯の友にカップラーメンや熱いお茶を飲みたい所だが、荷物を減らす関係上、テルモスもカップ麺も持って来ていない。握り飯の友は、ハイドレーションの水となった。チューチュー。
行動食もここぞとばかりに食べる。チョコ、マルセイのバターサンド、アミノバイタルプロ。
このアミノバイタルプロ、効き目が素晴らしい。摂取してから30分後の体の活力が違う。ここぞと言う時のドーピングに持って来いの行動食だ。

それはそうと、下の写真のリニューアルされたアルピニスト50、こんな違いがある。
一番の違いは、ザック下部のピッケル用のループ(ピッケルホルダー)が新たに付いた事だ。これまでのアルピニストシリーズは、独特のピッケル装着システムになっていて、ピッケルのヘッドの穴に金具を通して固定するという仕組みだった。しかし、ピッケルのヘッドの穴が小さいグリベルのピッケル等を装着する事が出来ないというデメリットがあった。これの評判が悪かった為、一般的なループ型のホルダーも付けたのだと思われる。これは非常に良い改善だ。
その他、デザインも少し変化があった。これまでは雨蓋の縁は濃い金色の生地で縁取られていたが、リニューアル後はそれが無くなった。私は前のデザインの方が好きだった。気の所為か、雨蓋が小さくなった様に感じるが、デザインの違いであって、きっと容量の差異はないだろう。

小屋を出て、直ぐ脇の沢を進む。雪渓になっている為、沢の中の石を慎重に渡っていく必要はなく、ぐんぐん高度を稼げる。
アイゼンを履き、ザクザクと雪を踏みながら進んでいく。思ったよりも、アイゼンの重さが足に来る。冬靴だった時は、靴自体も重い所為か、アイゼンを履いても大して重さを感じなかったのに、この夏靴では一歩一歩が重く感じる。
またしても失敗した事に気付く。トレースを辿って進んだ所、そのルートに誤りがあり、正規ルートの隣の沢筋へ入ってしまっていた。正規のルートに戻るが、また時間をロスしてしまった。
トラブルというのは、重なる時は重なる。何でだろうか。

正規のルートは踏み跡も多く、それを利用させて貰う。ステップをそのまま利用出来るので、楽だ。
この雪渓、大して斜度が無いからいいものの、安全の為ならピッケルも持った方が良かったかも知れない。先行者がアイゼン無しで登って行くが、安全に不安は感じないのだろうか。私が心配性なだけかも知れない。

雪渓を超えた先で目の前が一気に開けた。これから歩く先が見渡せる。
中心の右側の山が蛇ヶ岳、中心のピークが3つ並んだ山が三峰山、その遥か奥にポコッと並んだ山が北泉ヶ岳と泉ヶ岳だ。余りにも遠くて少しゲンナリしつつも、頑張るぞ、という気持ちにもなる。

船形山山頂は立ち寄って直ぐ下るので、重いザックを担ぎ上げる必要はない。泉ヶ岳への分岐点にデポし、山頂へ向かう。
空身の身軽さよ。

あっという間に頂上だ。
風が強い所為か、人が少ない。否、山開き前だからだ。これまでに3名としかすれ違っていない。人が少なすぎるのは、そういう事か。
逆に考えよう。この週末が山開きと重なって人でごった返さなくてよかった、と。私は静かな山の方が好きだ。


分岐点に戻り、泉ヶ岳方面へ向かう。

目指す先が見えるというのは、気持ちが良い。林間歩きは飽きた所だった。背丈より高い木もまだまだあるが、稜線を歩きながらチラチラ見える風景の変化がとても面白い。

蛇ヶ岳山頂だ。
靴擦れが悪化している。片足だったものが、両足になってしまった。休憩を兼ねて、ザックを下ろし、靴を脱いで患部を見る。靴下が湿っている。水溜りや沢をジャブジャブ進んだ所為か、中の湿気が外に逃げなかったのだろう。それによって内部の摩擦が強くなり、靴擦れが悪化したのだと思われる。バンソウコウを張りなおし、処置を行った。それでもヒリヒリする。
靴下を脱いだ足が風に当たると気持ちが良い。今日は仙台では、31度Cを越える気温になったのだという。山の上でも結構な気温だが、風のおかげで気持ちが良い。


この船形連峰はコシアブラが非常に多い。稜線上にも立派なコシアブラの木が沢山ある。
荷物は増やしたくなくとも、スーパー山菜人の血が騒いで採取せずには居られない。ああ、何でこんなに立派なんだ。何でこんなに沢山取れるんだ。何でこれを取りきれずに見逃して歩かねばならないのか。この採ったコシアブラをあげるから、私にもっと採らせてくれ!


蛇ヶ岳を超え、三峰山を目指す。
三峰山周辺は藪が非常に濃い。そして熊も多いらしい。突然出会うのだけは避けねばならないので、ラジオを大き目の音で鳴らし、進む事にする。
この濃い藪が苦痛だ。

濃い藪を越えると、視界が開ける。
船形山から泉ヶ岳への縦走ルートでは、この三峰山頂上付近の辺りが一番好きだ。背より高い木がないので見晴らしは良いし、縦走的な雰囲気が楽しめるからだ。
仙台で真夏日になったように、山も暑い。ハイドレーションの水を2L準備したからと景気良くチューチュー吸いまくっていた所、三峰山山頂を待たずに2Lを飲み切ってしまった。ハイドレーションはこまめに水分補給出来るという非常に大きなメリットがある一方、どれだけ飲んだか解らないというデメリットもある。
そして、飲みきった後の補給のしにくさだ。ザックから取り出して、水を補給して、ザックに戻すとなると、ザックの中身の殆どを取り出してパッキングし直さねばならなくなる。これが余りにも面倒なのだ。
プラティパスに予備の水が入っているので、休憩の時に一気にがぶ飲みして水分補給する事にしよう。

つづく。
タグ :山歩き
2015年04月28日
ブユ(ブヨ)に噛まれたら(刺されたら) その2
昨年のブユ体験記からのつづき。
始めに書いておく。ブユ(ブヨ)の噛まれ痕はきっちり治せ!
実は、未だにブユの噛まれ痕に悩まされている。昨年の6月下旬にブユに噛まれ、あの時から実に10ヶ月も経つのにだ。
何がどうなって10ヶ月後も悩まされているかというと、ブユの噛まれ痕が結節なってしまっていたのだ。
結節とは、正確には結節性痒疹(けっせつせいようしん)と言う。結節は、虫さされやアトピーなどがきっかけとなって、出来る事があるのだそうだ。私の場合、ブユの噛まれ痕が結節になってしまったようだ。
この結節になると、激しい痒みが生じるようになり、最初は数箇所だった結節が別な場所に増えていくという恐ろしい皮膚疾患なのだそうだ。

経緯:
昨年6月、キャンプをしていてブユに噛まれてしまい、激しい痒みに悩まされ、皮膚科に向かった。民間治療的なお灸と、病院から処方された薬で治療に当たった。7月下旬頃には、もう痕もなくなって、治癒しきったかに思っていた。
11月頃、登山で藪漕ぎをした翌日のテントの中で、妙に手首が痒い。当時は、藪漕ぎで虫に噛まれたのかと思った。テレビでマダニに気をつけよう、と放送していたのを思い出す。
今思い返せば、痒くなった場所は、ブユの噛まれ痕の近くだった。ブユの噛まれ痕そのものが痒くなったのではなく、その近くが痒くなったので、ブユの痒みがぶり返したのだとは思わなかった。
虫刺されであれば、放っておけば治るだろうと、そのまま生活を続けた。
それは12月になっても治らず、患部が2mmほどぷっくり腫れたままとなった。この時点で既に結節になっていたと思われる。
痒いのは、その2mmほどの腫れ部分だけだったが、3月頃、全く別の場所が痒み出すようになった。上腕、足、腰に痒みを感じるようになった。寝ていると、痒みで掻いてしまうらしく、掻いたあとが傷になってしまった。
痒みの原因も解らない。虫刺されなのか、藪漕ぎした時に変な菌やウィルスを拾ってしまったのか。最初に出来た2mmほどの腫れだけであれば、虫刺されなのかとも思ったが、全く別な箇所がそうなるとすると、菌やウィルスなのではないかと思った。
病院の診断:
これは私の悪い癖なのだが、症状が酷くならないと病院に行かない。
仕事で出張が続き、病院に行きたくとも行けない状況が続き、先日、ようやく皮膚科に掛かる事が出来た。ブユに噛まれた時に掛かった医者だ。
医者は開口一番、「これはブユだね」と言った。ブユの噛まれ痕が完治していないからこうなったのだ、と。
虫刺されと全く関係のない箇所も痒くなってしまったが、本当に6月に噛まれたブユの影響なのか、と聞くと、そうだと言う。
そして、ブユの毒が残ってアレルギー反応している訳ではないそうだ。
衝撃的な診断結果だった。
6月にブユに噛まれ、7月末には一時は完治したように見えた。その後、何かしらのきっかけがあって、再び痒み始めた。時間が経てば治るだろうと放置していたら、初めに痒かった箇所以外が痒くなり始めたのだ。
医者曰く、ブユの噛まれ痕を治す時は、キッチリ治し切らないと結節になってしまうのだと言う。更に結節は、本当に酷くなると、全身にぷっくりした結節が出来、ガマガエルのようにブツブツになる事もあるのだという。うわぁ・・・。
私はまだぷっくりした患部がブユの噛まれ痕にしか出来ていないが、これを更に放置していたらと考えると、本当に恐ろしい事だ。
まさか、治癒したと思ったブユの噛まれ痕が再び痒くなり、症状が悪化してしまうとは、露程にも思わなかった。
治療:
結節は難治性だという。
飲み薬で痒みを抑え、ステロイドの軟膏を塗るという治療方法だ。痒み止めの軟膏も処方されている。掻いてしまうと治らないので、痒みを抑えて掻かないようにするのが大事なのだそうだ。
どうしても治らない場合は、結節に直接注射する方法もあるという。
朝晩の飲み薬と、軟膏塗り、これを忘れないように続けたいと思う。
ブユは侮れない、本当に恐ろしい虫だ。
以前述べた様に、ブユに噛まれた後の数日は、民間治療的方法でのお灸の効果はあると思う。しかし、綺麗に完治するかどうかは、しっかり病院から処方される薬を使って、きっちり治療しきるかにかかっている。
私の様に、治ったと思っていたら、ぶり返すという事もある。ネットで調べてみると、数ヵ月後のぶり返しというのは、よくある事のようだ。
ブユの噛まれ痕が結節になってしまう前に、しっかり治しきるという事を、心掛けて治療に当たって頂きたい。そして、ぶり返しもあるという事を念頭に置いて頂きたい。
始めに書いておく。ブユ(ブヨ)の噛まれ痕はきっちり治せ!
実は、未だにブユの噛まれ痕に悩まされている。昨年の6月下旬にブユに噛まれ、あの時から実に10ヶ月も経つのにだ。
何がどうなって10ヶ月後も悩まされているかというと、ブユの噛まれ痕が結節なってしまっていたのだ。
結節とは、正確には結節性痒疹(けっせつせいようしん)と言う。結節は、虫さされやアトピーなどがきっかけとなって、出来る事があるのだそうだ。私の場合、ブユの噛まれ痕が結節になってしまったようだ。
この結節になると、激しい痒みが生じるようになり、最初は数箇所だった結節が別な場所に増えていくという恐ろしい皮膚疾患なのだそうだ。

経緯:
昨年6月、キャンプをしていてブユに噛まれてしまい、激しい痒みに悩まされ、皮膚科に向かった。民間治療的なお灸と、病院から処方された薬で治療に当たった。7月下旬頃には、もう痕もなくなって、治癒しきったかに思っていた。
11月頃、登山で藪漕ぎをした翌日のテントの中で、妙に手首が痒い。当時は、藪漕ぎで虫に噛まれたのかと思った。テレビでマダニに気をつけよう、と放送していたのを思い出す。
今思い返せば、痒くなった場所は、ブユの噛まれ痕の近くだった。ブユの噛まれ痕そのものが痒くなったのではなく、その近くが痒くなったので、ブユの痒みがぶり返したのだとは思わなかった。
虫刺されであれば、放っておけば治るだろうと、そのまま生活を続けた。
それは12月になっても治らず、患部が2mmほどぷっくり腫れたままとなった。この時点で既に結節になっていたと思われる。
痒いのは、その2mmほどの腫れ部分だけだったが、3月頃、全く別の場所が痒み出すようになった。上腕、足、腰に痒みを感じるようになった。寝ていると、痒みで掻いてしまうらしく、掻いたあとが傷になってしまった。
痒みの原因も解らない。虫刺されなのか、藪漕ぎした時に変な菌やウィルスを拾ってしまったのか。最初に出来た2mmほどの腫れだけであれば、虫刺されなのかとも思ったが、全く別な箇所がそうなるとすると、菌やウィルスなのではないかと思った。
病院の診断:
これは私の悪い癖なのだが、症状が酷くならないと病院に行かない。
仕事で出張が続き、病院に行きたくとも行けない状況が続き、先日、ようやく皮膚科に掛かる事が出来た。ブユに噛まれた時に掛かった医者だ。
医者は開口一番、「これはブユだね」と言った。ブユの噛まれ痕が完治していないからこうなったのだ、と。
虫刺されと全く関係のない箇所も痒くなってしまったが、本当に6月に噛まれたブユの影響なのか、と聞くと、そうだと言う。
そして、ブユの毒が残ってアレルギー反応している訳ではないそうだ。
衝撃的な診断結果だった。
6月にブユに噛まれ、7月末には一時は完治したように見えた。その後、何かしらのきっかけがあって、再び痒み始めた。時間が経てば治るだろうと放置していたら、初めに痒かった箇所以外が痒くなり始めたのだ。
医者曰く、ブユの噛まれ痕を治す時は、キッチリ治し切らないと結節になってしまうのだと言う。更に結節は、本当に酷くなると、全身にぷっくりした結節が出来、ガマガエルのようにブツブツになる事もあるのだという。うわぁ・・・。
私はまだぷっくりした患部がブユの噛まれ痕にしか出来ていないが、これを更に放置していたらと考えると、本当に恐ろしい事だ。
まさか、治癒したと思ったブユの噛まれ痕が再び痒くなり、症状が悪化してしまうとは、露程にも思わなかった。
治療:
結節は難治性だという。
飲み薬で痒みを抑え、ステロイドの軟膏を塗るという治療方法だ。痒み止めの軟膏も処方されている。掻いてしまうと治らないので、痒みを抑えて掻かないようにするのが大事なのだそうだ。
どうしても治らない場合は、結節に直接注射する方法もあるという。
朝晩の飲み薬と、軟膏塗り、これを忘れないように続けたいと思う。
ブユは侮れない、本当に恐ろしい虫だ。
以前述べた様に、ブユに噛まれた後の数日は、民間治療的方法でのお灸の効果はあると思う。しかし、綺麗に完治するかどうかは、しっかり病院から処方される薬を使って、きっちり治療しきるかにかかっている。
私の様に、治ったと思っていたら、ぶり返すという事もある。ネットで調べてみると、数ヵ月後のぶり返しというのは、よくある事のようだ。
ブユの噛まれ痕が結節になってしまう前に、しっかり治しきるという事を、心掛けて治療に当たって頂きたい。そして、ぶり返しもあるという事を念頭に置いて頂きたい。
タグ :雑記
2015年04月27日
山遊び 渓流釣りと山菜採りと天ぷらと 20150426
里山は春だ。
渓流釣りだ!山菜だ!天ぷらだ!
この時持っていった物
服装
ザック内(グレゴリー Z35)
ザックの中が食料でパンパンになった。殆ど食料だ。弟のザックはデイパックなので、弟個人の装備以外は、全て私が背負う事になった。まさか、渓流釣りごときで35Lザックがこの状態になるとは思わなかった。
今回の作戦はこうだ。
弟と新緑の里山に分け入り、渓流釣りと山菜を楽しむ。採った山菜は、現地で天ぷらで食べてしまおうという計画だ。
山菜が良い状態かは賭けに近い。山菜というのは、ある短いタイミングを逃すと、育ちすぎてて食べられなくなってしまう。逆に育っていない状態というのもある。
この極端に短いタイミングに目星を付けて1ヶ月前に計画を立てたが、思ったより季節の進みが早い。例年より2週間位早いのではないだろうか。
天ぷらにするならタラノメだ。のび過ぎていないか、誰かに根こそぎ採られていないか、そんな心配をしながら現地へ向かった。
タラノメの採れる沢沿いに車を停め、目を光らせて進む。キノコもそうらしいが、目が慣れてくると、生い茂る木の中から、山菜だけを見分ける事が出来る。
早速、タラノメの木が目に入る。おほーっ!!滅茶苦茶良い状態のタラノメちゃん!実に丁度良い育ち具合。今日は期待出来そうだ。
タラノメの木は柔らかくしなるので、優しく木を曲げて、芽をポキッと折って採取する。木にはトゲが生えているので、したがって・・・げぇーっ!!絶望的な事に、厚めの手袋を忘れた事に気が付く。まぁ、弟にやらせよう。
ポキッとタラノメを採取する。これを後で食べると思うとワクワクする。

誰もここに入っていないようで、タラノメは採り放題だった。15分もしない内に、手提げのビニール袋がいっぱいになった。
採り過ぎても仕方が無いので、食べ頃の育ち具合でないものや、採るのが面倒な場所にあるものは、無視して進む事にした。まさか、人気のタラノメを無視する日が来ようとは。

少し歩くと、砂防ダムの下に到着する。
こんな所に魚が居るのか、という場所で竿を出す。イワナというのは不思議な生き物だ。水溜り程度の大きさの場所で、大きなイワナが釣れる。

弟の持つ竿にグングンとした手応えがあった。でかいイワナを抜き上げる。27cmくらいだろうか。
やはり釣れた。野生の勘は馬鹿にならない。


更に奥に進んで、次の砂防ダムの下で竿を出す。
ここは狭いので、チョウチン釣りだ。チョウチン釣りとは、仕掛けを竿の長さの半分程に作り、狭い場所でも竿を振らずにポイントへ仕掛けを投入出来る釣法だ。竿の先に短い仕掛けがついていて、チョウチンを吊るしているようだから、チョウチン釣りと言う。
エサのミミズを投入するやいなや、1秒も経たずに反応が出る。過酷な環境に生きているイワナほど、貪欲にエサを食べる。
良型だ。これも27cmくらいだろう。


沢沿いにクレソンが生えていた。
どう食べても美味しい野草だ。サラダで良し、おひたしで良し。弟はムシャムシャと食べて気に入ったのか、ビニール袋一杯に採取していた。細君に食べさせたいのだと言う。イワナも食べさせる為に、今回は持ち帰りたいそうだ。恐妻家なのに、妻思いの男だ。

タラノメが十分に採取出来たので、先程の沢の隣の沢へ車で移動した。ここは、前回ヤマメを釣って焚き火で食べた沢だ。
車が何台か停まっており、既に人が入ってしまっている。
良さそうなポイントで竿を出してみるが、スレていて、殆ど反応が出なかった。先程釣ったイワナは持ち帰り用にしてあるので、この沢で釣れないと塩焼きはお預けになってしまう。

何だか解らないけれど、可愛い花。

弟は釣りに集中したいと言う。私は、今時期しか出来ない山菜に集中したい。一旦、別行動にする事にした。
熊も居る里山なので、熊鈴を鳴らしながら進む。
タラノメ以上にタイミングがシビアなコゴミ。タイミングさえ合えば、山ほど採れるが、今回は99%が育ちきってしまっていた。
私はコゴミの天ぷらが好きだ。楽しみにしていただけに残念だ。
開ききっていないものを選び、量は取れないが、そっと採取した。

去年、この奥でキャンプした時に目をつけていたウコギだ。ウコギ飯にしたり、天ぷらで食べたりすると言う。上杉鷹山が奨励したという事で、山形では結構有名な山菜だそうだ。
芽が小さくて摘みにくいが、採取に没頭していたら、結構な量が取れた。採取している時、コシアブラの様な香りを感じた。

弟と合流する。釣果は得られなかったと言う。
その後、こんな一級ポイントはなかなかないだろう、という場所でもやってみるが、駄目だった。誰も入っていない早朝でなければ駄目なのだろう。
これで渓魚の塩焼きは無しとなった。残念だ。

いつもの砂防ダムの下に戻る。
私のビールと、運転手の弟のノンアルコールビールを冷やす。清流で冷やされるビールというのは、何とも清涼感を感じる。
山菜の天ぷらを食べ、ビールをギュッと飲む。想像しただけでたまらん。


焚き火で天ぷらをやろうと思っていたが、火加減の調整が難しいだろうという事と、飛び散る油の中、火からコッヘルを出し入れするのは難しいだろうという事から、弟のストーブと、ミニフライパンで調理する事にした。先読みして準備してくるとは、大したものだ。

タラノメ、コゴミ、ウコギ、ハリギリを天ぷらにして食べた。
タラノメはゴリゴリの歯応えと、独特の香りで期待通りの味だ。コゴミは細く小さなものだけだったので、満足な味ではなかったが、それでもねっとりとした舌触りで楽しませてくれた。ウコギをかき揚げにしてみると、コシアブラに似た香りで実に美味かった。ハリギリは、今回の天ぷら種で一番美味かった。ハリギリをもっと食べたかった。
夢中になって食べる事に集中していたら、写真を撮り忘れていた。それ位、美味かったという事だ。天ぷらの様子は、動画で見て頂きたい。

後は、いつもの焚き火汁を作って食べた。満腹也。


徒歩移動の日帰りでビールなんて飲むもんじゃねえな。歩いて戻るのが大変だった。
渓流釣りだ!山菜だ!天ぷらだ!
この時持っていった物
服装
| 服装 | Tシャツ、フリース、トレッキングパンツ、ネオプレンソックス、渓流シューズ |
ザック内(グレゴリー Z35)
| 釣り道具 | てんから竿、毛鉤、ミャク釣り仕掛け、ミミズ |
| クッカー類 | ダグ 焚火缶、エバニュー ハンドル、イワタニプリムス P-153、250OD缶、シエラカップ2個、割り箸2膳、薪 |
| 食料 | 鍋の材料(ジップロック)、天ぷら粉、油、ソーセージ、ビール、ノンアルコールビール、握り飯2個、スポーツドリンク1L |
| イス | エーライト メイフライチェア |
| 服 | ダウンジャケット |
| その他 | ナイフ、ヘッドライト、ファーストエイドキット、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、コンパクトデジカメ、ウェアラブルカメラ、トレッキングポール |
ザックの中が食料でパンパンになった。殆ど食料だ。弟のザックはデイパックなので、弟個人の装備以外は、全て私が背負う事になった。まさか、渓流釣りごときで35Lザックがこの状態になるとは思わなかった。
今回の作戦はこうだ。
弟と新緑の里山に分け入り、渓流釣りと山菜を楽しむ。採った山菜は、現地で天ぷらで食べてしまおうという計画だ。
山菜が良い状態かは賭けに近い。山菜というのは、ある短いタイミングを逃すと、育ちすぎてて食べられなくなってしまう。逆に育っていない状態というのもある。
この極端に短いタイミングに目星を付けて1ヶ月前に計画を立てたが、思ったより季節の進みが早い。例年より2週間位早いのではないだろうか。
天ぷらにするならタラノメだ。のび過ぎていないか、誰かに根こそぎ採られていないか、そんな心配をしながら現地へ向かった。
タラノメの採れる沢沿いに車を停め、目を光らせて進む。キノコもそうらしいが、目が慣れてくると、生い茂る木の中から、山菜だけを見分ける事が出来る。
早速、タラノメの木が目に入る。おほーっ!!滅茶苦茶良い状態のタラノメちゃん!実に丁度良い育ち具合。今日は期待出来そうだ。
タラノメの木は柔らかくしなるので、優しく木を曲げて、芽をポキッと折って採取する。木にはトゲが生えているので、したがって・・・げぇーっ!!絶望的な事に、厚めの手袋を忘れた事に気が付く。まぁ、弟にやらせよう。
ポキッとタラノメを採取する。これを後で食べると思うとワクワクする。

誰もここに入っていないようで、タラノメは採り放題だった。15分もしない内に、手提げのビニール袋がいっぱいになった。
採り過ぎても仕方が無いので、食べ頃の育ち具合でないものや、採るのが面倒な場所にあるものは、無視して進む事にした。まさか、人気のタラノメを無視する日が来ようとは。

少し歩くと、砂防ダムの下に到着する。
こんな所に魚が居るのか、という場所で竿を出す。イワナというのは不思議な生き物だ。水溜り程度の大きさの場所で、大きなイワナが釣れる。

弟の持つ竿にグングンとした手応えがあった。でかいイワナを抜き上げる。27cmくらいだろうか。
やはり釣れた。野生の勘は馬鹿にならない。


更に奥に進んで、次の砂防ダムの下で竿を出す。
ここは狭いので、チョウチン釣りだ。チョウチン釣りとは、仕掛けを竿の長さの半分程に作り、狭い場所でも竿を振らずにポイントへ仕掛けを投入出来る釣法だ。竿の先に短い仕掛けがついていて、チョウチンを吊るしているようだから、チョウチン釣りと言う。
エサのミミズを投入するやいなや、1秒も経たずに反応が出る。過酷な環境に生きているイワナほど、貪欲にエサを食べる。
良型だ。これも27cmくらいだろう。


沢沿いにクレソンが生えていた。
どう食べても美味しい野草だ。サラダで良し、おひたしで良し。弟はムシャムシャと食べて気に入ったのか、ビニール袋一杯に採取していた。細君に食べさせたいのだと言う。イワナも食べさせる為に、今回は持ち帰りたいそうだ。恐妻家なのに、妻思いの男だ。

タラノメが十分に採取出来たので、先程の沢の隣の沢へ車で移動した。ここは、前回ヤマメを釣って焚き火で食べた沢だ。
車が何台か停まっており、既に人が入ってしまっている。
良さそうなポイントで竿を出してみるが、スレていて、殆ど反応が出なかった。先程釣ったイワナは持ち帰り用にしてあるので、この沢で釣れないと塩焼きはお預けになってしまう。

何だか解らないけれど、可愛い花。

弟は釣りに集中したいと言う。私は、今時期しか出来ない山菜に集中したい。一旦、別行動にする事にした。
熊も居る里山なので、熊鈴を鳴らしながら進む。
タラノメ以上にタイミングがシビアなコゴミ。タイミングさえ合えば、山ほど採れるが、今回は99%が育ちきってしまっていた。
私はコゴミの天ぷらが好きだ。楽しみにしていただけに残念だ。
開ききっていないものを選び、量は取れないが、そっと採取した。

去年、この奥でキャンプした時に目をつけていたウコギだ。ウコギ飯にしたり、天ぷらで食べたりすると言う。上杉鷹山が奨励したという事で、山形では結構有名な山菜だそうだ。
芽が小さくて摘みにくいが、採取に没頭していたら、結構な量が取れた。採取している時、コシアブラの様な香りを感じた。

弟と合流する。釣果は得られなかったと言う。
その後、こんな一級ポイントはなかなかないだろう、という場所でもやってみるが、駄目だった。誰も入っていない早朝でなければ駄目なのだろう。
これで渓魚の塩焼きは無しとなった。残念だ。

いつもの砂防ダムの下に戻る。
私のビールと、運転手の弟のノンアルコールビールを冷やす。清流で冷やされるビールというのは、何とも清涼感を感じる。
山菜の天ぷらを食べ、ビールをギュッと飲む。想像しただけでたまらん。


焚き火で天ぷらをやろうと思っていたが、火加減の調整が難しいだろうという事と、飛び散る油の中、火からコッヘルを出し入れするのは難しいだろうという事から、弟のストーブと、ミニフライパンで調理する事にした。先読みして準備してくるとは、大したものだ。

タラノメ、コゴミ、ウコギ、ハリギリを天ぷらにして食べた。
タラノメはゴリゴリの歯応えと、独特の香りで期待通りの味だ。コゴミは細く小さなものだけだったので、満足な味ではなかったが、それでもねっとりとした舌触りで楽しませてくれた。ウコギをかき揚げにしてみると、コシアブラに似た香りで実に美味かった。ハリギリは、今回の天ぷら種で一番美味かった。ハリギリをもっと食べたかった。
夢中になって食べる事に集中していたら、写真を撮り忘れていた。それ位、美味かったという事だ。天ぷらの様子は、動画で見て頂きたい。

後は、いつもの焚き火汁を作って食べた。満腹也。


徒歩移動の日帰りでビールなんて飲むもんじゃねえな。歩いて戻るのが大変だった。
タグ :山遊び